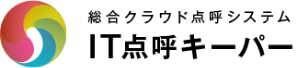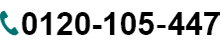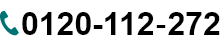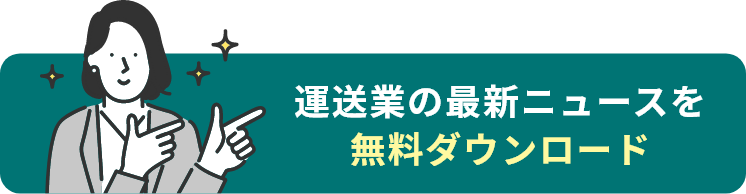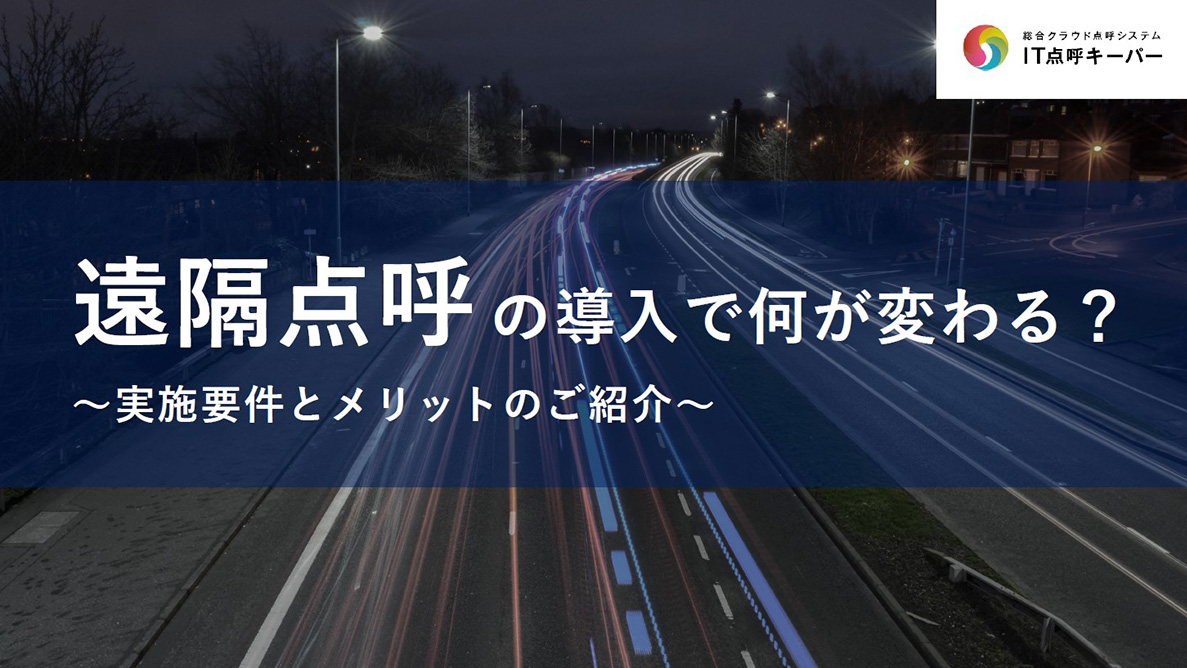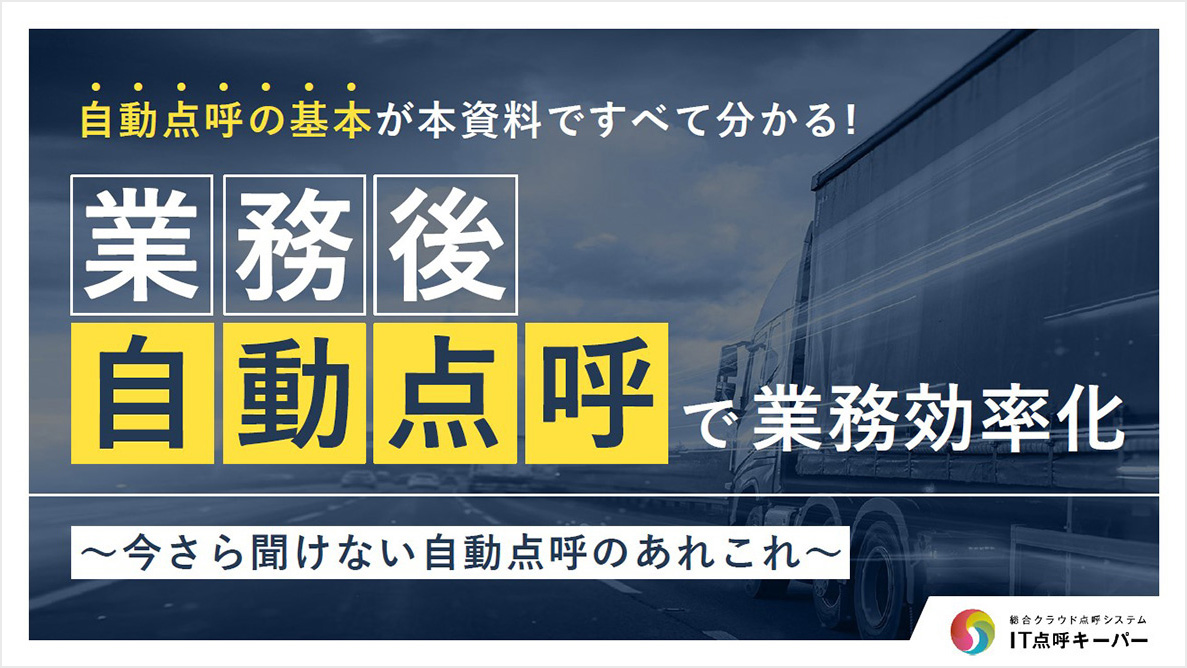コラム一覧
点呼に関する様々な情報や豆知識を、コラムとして配信しています。
カテゴリから探す
すべてのコラム
-
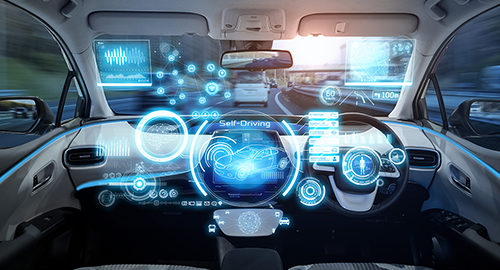 時事ネタ
時事ネタ
自動運転レベルとは?各レベルの定義や法的動向について解説
運転席に座りながらハンドルには手を触れず、景色を見渡しながら車を走らせるテレビCMを見て、自動運転が当たり前になる日は近いと感じる方も多いのではないでしょうか。今回は、運送業界が長年抱える人手不足を解消する新たな一手として期待が高まる自動運転について、できることによってランク分けされた自動運転レベルと実用化に向けた法律上の動きについてご紹介します。この記事を読むと、自動運転が運送業界に及ぼす変化の有無やポイント、タイミングがわかります。ぜひ最後までご覧ください。
-
 法改正・規制
法改正・規制
遠隔点呼とは?遠隔点呼の申請ルールが令和5年4月から変更
2022年(令和4年)4月より開始した「遠隔点呼」ですが、2023年(令和5年)3月31日以降ちょっとした変化があったことをご存じでしょうか。これに伴い、遠隔点呼の要件や申請方法が変更されました。そこで本記事では遠隔点呼の定義をおさらいし、2023年4月1日以降の申請方法について解説しますのでトラック事業者の方は参考にしてください。
-
 法改正・規制
法改正・規制
遠隔点呼とIT点呼の違いをカンタンまとめ
令和4(2022)年4月より、「遠隔点呼実施要領」に基づいた遠隔点呼の申請が開始されています。すでに実施されている「IT点呼」と新たに申請できるようになった「遠隔点呼」には、どのような違いがあるのでしょうか?
-
 時事ネタ
時事ネタ
旅客運送事業者も導入しやすい?【改訂版】遠隔点呼を徹底解説
「遠隔点呼の内容が変わったらしいけれど、何がどのように変わったの?」「当社も対面点呼に代えて遠隔点呼を導入するべき?」「簡単・低コストで遠隔点呼を導入できるシステムはないかな?」この記事では、このようなお悩みを持つ旅客運送事業者(バス・タクシー会社)向けに、以下の点をご紹介します。
-
 時事ネタ
時事ネタ
運送事業者向けの助成金・補助金一覧!IT関連や新型コロナウイルス対策支援に関する助成金も紹介
助成金や補助金は、融資と違い、返済不要な点がメリットです。うまく活用することで、金銭的負担を軽減しつつ、社内体制を整えたり、事業計画についてあらためて考えたりすることが可能です。ただし、補助金は審査があるため、必ずしも支給されるとは限りません。また目的によって活用できるものが異なるため、しっかり理解することが大切です。そこで今回は、運送事業者向けの助成金・補助金をご紹介します。運送業関連で活用できる助成金や補助金を知りたい方は、ぜひ最後までお読みください。
-
 法改正・規制
法改正・規制
日本でもライドシェアは解禁される?解禁される際の問題点やメリットも解説
海外ではすでに広まっているライドシェアは、日本でも解禁の動きがみられます。ライドシェアの解禁を巡っては、これまで度々議論が行われてきました。活用すれば便利な一方で、バス・タクシー業界などへの影響や解禁後のあらゆる問題点が懸念されています。今後ライドシェアが解禁された場合、具体的にどのような問題が生じてしまうのでしょうか?そこで今回は、ライドシェアの基本情報から日本で解禁された際に知っておきたい影響・問題点、メリットなどについて解説します。
-
 マネジメント
マネジメント
ホワイト物流推進運動とは?メリット・デメリットを解説
昨今、国内における多くの産業で人手不足の問題が浮上しています。とくに、物流業界ではドライバー不足が深刻な状態です。こうした物流業界の課題を解決しようと、国内で「ホワイト物流推進運動」が活発化してきています。そこで今回は、ホワイト物流がどういったものか解説しつつ、賛同を表明するメリット・デメリットや賛同するための方法などをご紹介していきます。最近耳にする機会が増えた「ホワイト物流」がどういったものかわからない、賛同するメリットはあるのかなどといった点を知りたい方は、ぜひ参考にしてみてください。
-
 マネジメント
マネジメント
傭車とは?利用する理由やメリット・デメリット、コスト削減方法も紹介
労働時間の上限規制に対処するため、毎日のスケジュール調整に苦労されている運行管理者の方は多いのではないでしょうか。しかし、人手が足りなくても傭車を上手に使うと労働力は確保できます。人手と仕事、お互いの足りない部分を補えば、悩みを解消しつつ利益を得られるでしょう。そこで今回は、傭車を利用するメリット・デメリットと利用コストを抑える方法をご紹介します。
-
 法改正・規則
法改正・規則
運行管理者試験とは?日程や出題内容・難易度と受験対策のポイントを解説
働き方改革関連法の適用猶予期間終了によって生じる課題、いわゆる2024年問題が話題になっていますが、その先の日本は2030年問題というさらなる課題に直面すると予想されていることをご存知でしょうか。安全運転をして当たり前と見られるトラック、バス、タクシーなどのプロドライバー。しかし彼らも人間であるため、常に万全の状態で運転できるとは限りません。体調が悪いのに無理をして運行し、事故を起こしたら当事者や会社、乗客や顧客など多くの人に被害がおよびます。
-
 法改正・規則
法改正・規則
2030年問題とは|労働人口の変化がもたらす影響や解決策を解説
働き方改革関連法の適用猶予期間終了によって生じる課題、いわゆる2024年問題が話題になっていますが、その先の日本は2030年問題というさらなる課題に直面すると予想されていることをご存知でしょうか。
-
 法改正・規則
法改正・規則
法改正で貸切バス事業は何が変わる?事業者・バス運転者への影響とは
2024年4月1日より、貸切バス事業に関する2つの制度が改正されます。バス運転者の改善基準告示、貸切バスの安全性向上に向けた対策のための制度
-
 マネジメント
マネジメント
中継輸送とは?3つの類型やメリット・デメリット、点呼の方法を解説
2024年4月1日からはじまる自動車運転者の時間外労働に対する上限規制。事実上、1人の運転者による輸送距離に上限がかかるため、長距離輸送事業者はとくに対応に苦慮されているでしょう。
-
 時事ネタ
時事ネタ
深刻化するトラックドライバー不足の対策は?運送業界が抱える課題とは
少子高齢化に歯止めがかからない日本。運送業界もトラックドライバーの高齢化が進み、現役を退いた人の穴を若い力で補えず、人材不足が慢性化しています。
-
 法改正・規則
法改正・規則
2024年問題とは?物流業界への影響や対応策をわかりやすく解説
2024年4月1日より適用されるドライバーへの時間外労働に対する上限規制。慢性的な人材不足が続く運送業界において、1人あたり1日に任せられる仕事量が抑制される今回の制度に頭を悩ませている運送事業者の方も多いのではないでしょうか。
-
 時事ネタ
時事ネタ
運送業界・物流業界向けAI活用事例~AI導入で物流危機を解決~
運送業界・物流業界が抱える課題を解決するために、人工知能(以下、AI)が活用されていることをご存知でしょうか?AIなどの最新技術を活用して、運送業界・物流業界のコスト削減・業務効率化を実現する「スマートロジスティクス」という言葉が近年注目されています。また、国土交通省も物流DXを掲げ、業務の効率化や生産性の向上をすすめ、運送・物流のあり方を革新するよう推奨しているという背景があります。本記事では、運送業・物流業向けにAI活用方法について解説いたします。現場で働く方はぜひ参考にしてください。
-
 点呼システム
点呼システム
スマホ点呼とは?スマホを活用した点呼方法の違いやメリット、導入方法までをご紹介
運送業におけるグリーン経営という言葉を聞いたことがありますか?トラック運送業においても、経営課題として環境保全に取り組むことは今や避けて通ることはできません。そこで注目を集めているのが、グリーン経営です。グリーン経営の取り組みが充実してきたら、
-
 マネジメント
マネジメント
運送業におけるグリーン経営とは?
運送業におけるグリーン経営という言葉を聞いたことがありますか?トラック運送業においても、経営課題として環境保全に取り組むことは今や避けて通ることはできません。そこで注目を集めているのが、グリーン経営です。グリーン経営の取り組みが充実してきたら、
-
 法改正・規制
法改正・規制
運送業が巡回指導の対応でやっておくべきこととは?
国土交通省は巡回指導の結果、悪質と見られるトラック運送業者への監査を強化するとし、令和5年4月1日から新しい制度の運用を開始しています。新制度のもとDあるいはEの評価を受けた運送業者数の6割減を目指して、巡回指導の頻度を半年に1回に高めることになりました。
-
 法改正・規制
法改正・規制
正しい点呼で違反を防ごう~運送業における正しい点呼とは~
自動車運送事業における点呼は、輸送の安全を確保するために法令により実施が義務付けられている業務です。ICTの技術革新が目覚ましいことから対面点呼に代わる遠隔点呼が実施できるようになり、令和4年4月1日から申請がスタートしています。北陸信越運輸局が令和元年6月に公表した平成30年度の自動車運送事業者の行政処分の内容分析結果では、自動車運送事業の最多違反は点呼でした。
-
 時事ネタ
時事ネタ
<アフターレポート>運行管理者様必見!乗務後自動点呼制度の概要と対応のポイント
2023年1月より、自動車運送事業者は乗務後自動点呼を実施できるようになりました。乗務を終了したドライバーに対する点呼を自動化することで、運行管理の高度化はもとよりドライバーや運行管理者の働き方改革につながるとして期待されています。乗務後自動点呼の導入にあたっては、自動で点呼を行うための点呼機器に関する要件や認定制度について知ることが大切です。
-
 時事ネタ
時事ネタ
運送業の働き方改革で、ドライバーの労働時間・労働環境はどう変わる?
2024年4月からトラックドライバーの時間外労働に上限規制が適用されるため、働き方改革実現に向けてトラック運送事業者は対応に迫られています。2023年現在、働き方改革関連法のトラック運送業への適用は猶予されていますが、2024年になるとトラック運送業界に大きな変化が起きるでしょう。
-
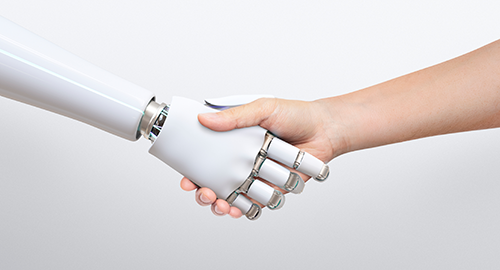 法改正・規制
法改正・規制
今知りたい、乗務後自動点呼のあれこれ
国土交通省は2023年(令和5)年1月から、乗務後自動点呼の運用がスタートしております。自動点呼は、遠隔点呼、運行指示者一元化などと一緒に「運行管理高度化検討会」で検討されている施策の1つです。トラックなどの自動車運送事業者に義務付けられている点呼を自動化する目的で、すでに機器認定制度が創設されています。
-
 時事ネタ
時事ネタ
Gマーク更新|2023年度(令和5年)|Gマーク認定を継続するメリットを解説
皆様は2023年に「Gマーク制度」が、創設から20年を迎えることをご存知でしょうか。Gマークはトラック運送事業者の安全性を客観的に示す評価指標として浸透し、トラック業界において差別化を図る手法として、注目を集めています。
-
 時事ネタ
時事ネタ
Gマーク認定の取得条件とは~IT点呼の導入資格を解説~
お客様からよく「IT点呼は誰でも導入できるの?」という質問をいただきます。現在、IT点呼の導入はGマークがなくても所定の条件下であれば使用することができますが、少し前まではGマークの取得が必須でした。
-
 法改正・規則
法改正・規則
働きやすい職場認証制度について
本制度は、平成30年6月より、国土交通省が旗振り役となり『自動車運送事業のホワイト経営の「見える化」検討会』において議論が行われ、制度設計について進められました。
-
 マネジメント
マネジメント
初めての安全運転指導~効果が出るためのポイントとは~
事業用自動車を使用していたり社用車で営業活動を行ったりしている企業にとって、安全運転を徹底させることは重要な課題です。社員を危険な目にさらさないことは勿論ですが、万が一社員が事故を起こしてしまうことにより発生する企業へのレピュテーションリスクも測り知れません。車を運転する従業員に対して、法的に安全運転指導を実施することが必要とされています。
-
 時事ネタ
時事ネタ
運送業の業務効率化に欠かせない4つのポイント
運送業界をはじめ物流業界は、トラック輸送にまつわるさまざまな問題に直面しており、業務効率化に取り組む必要性に直面しています。中でも差し迫った課題として知られる「物流の2024年問題」に向けた対応策について、社内で協議されていますでしょうか?本記事では、運送業界においてなぜ業務効率化が叫ばれているのか、その背景や参考にしたい業務改善のポイント、おすすめのシステムについて解説します。
-
 マネジメント
マネジメント
点呼時の体温測定の重要性-非接触式体表温計と体温計の違いは?
新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、従来の脇下で検温する接触式の体温計ではなく、非接触式体表温計を見かける機会が増えました。点呼時にはアルコール検知器を使用したアルコールチェックが義務付けられていますが、体温測定も運転者の健康状態を把握するために重要です。記事では、点呼時の体温測定の重要性や非接触式体表温計と体温計の違いをご紹介します。
-
 マネジメント
マネジメント
事業用自動車の事故防止のための点検ポイント
業務で旅客や貨物を預かり移動するトラックやバス、タクシーなどは、事故に遭遇すると社会的に大きな影響を与えます。スムーズな運行と重大事故防止のために、運送事業者が行うのが車両の日常点検や定期点検です。本記事では、自家用と事業用の違い、事業用自動車の事故や飲酒運転状況のほか、今後の事故防止対策として点検ポイントについて説明します。
-
 法改正・規制
法改正・規制
飲酒運転事故(酒気帯び運転)と罰則について
平成18年8月に、福岡県で幼児3人が死亡する飲酒運転による重大事故が発生しました。この事故が社会問題化したことを受けて、飲酒運転厳罰化や行政処分強化などの取り組みのほか、警察による飲酒運転根絶に向けた取り締まりの強化が行われています。悲惨な死亡事故につながる危険性は広く知られているにもかかわらず、飲酒運転による交通事故の発生が後を絶ちません。令和3年度には、飲酒運転の死亡事故率(交通事故件数に占める死亡事故件数の割合)は、飲酒なしの約9.2倍という結果がでています。
-
 法改正・規制
法改正・規制
運行管理者とは?選任方法や届出のポイントを解説
2020年から流行している新型コロナウイルスの感染拡大により、運行管理者試験が中止されるなどの影響がでています。運行管理者の選任予定が大幅に狂い、困惑されている事業者の方も多かったのではないでしょうか?
-
 点呼システム
点呼システム
点呼システム=IT点呼?概要から運用方法までご紹介
デジタル化の波を感じて、運行管理者や経営者の方はデジタコの導入やアルコールチェック機器のIT化を検討されているのではないでしょうか。点呼システムを導入すると、何ができるのか?本コラムでは、点呼システムの概要や導入のメリット、導入した企業様の声まで幅広くご紹介いたします。
-
 白ナンバー
白ナンバー
白ナンバーのアルコールチェック義務化が気になる方へ押さえるべきポイントまとめ
白ナンバー事業者は、自動車の運転前後のアルコールチェックが2022年4月1日から義務化されています。2022年10月1日からは段階的に、アルコール検知器の使用義務化が施行される予定でした。しかしアルコール検知器の供給状況が逼迫していることから、警察庁は当面の間の延期を発表し「道路交通法施行規則及び自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の施行に伴う道路交通量施行規則の規定の読替えに関する内閣府令の一部を改正する内閣府令案」に対するパブリックコメントを募集しておりました。
-
 白ナンバー
白ナンバー
安全運転管理者とは~企業の安全運転の守るためのポイントを解説~
安全運転管理者と言えば来年2022年から業務が拡充されるという通達がありました。2022年4月からドライバーに対し目視でアルコールチェックを行った記録の保管義務が業務として追加、同年10月からはアルコール検知器を使ったアルコールチェックが義務化されます。このような動向から安全運転管理者の業務について、来年度以降の対策を検討されている企業様も多いのではないでしょうか。今回は安全運転管理者の選任条件や業務、役割などについてご紹介いたします。
-
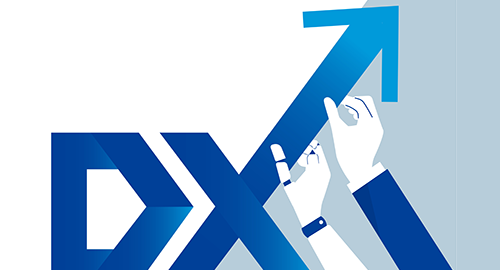 時事ネタ
時事ネタ
物流DXで運送業界の課題を解決
DX(デジタルトランスフォーメーション)という単語を最近よく目にしますが、具体的にどのようなことを指すのかご存じでしょうか?DXとは「最新のデジタル技術を駆使して業務上の課題を解決し、新たなビジネスモデルを生み出すこと」を意味しています。
-
 白ナンバー
白ナンバー
運送業界でよく聞く白ナンバートラックとは?
緑ナンバートラックとの比較解説2021年9月に運送業界で白ナンバーの車両を一定台数以上保有する事業所にも義務化する道路交通法施行規則の改正案が発表されました。この背景に2021年6月の千葉で起こりました白ナンバートラックの交通事故があり、ドライバーは飲酒運転でした。
-
 時事ネタ
時事ネタ
自動車運送事業における労働環境の改善について
~社員の定着と労働生産性の向上~ここ数年、運送事業における労働力不足や長時間労働、他業種に比べて低賃金傾向にある現状…
-
 時事ネタ
時事ネタ
トラック運送業界における感染予防対策について
ここ数年、運送事業における労働力不足や長時間労働、他業種に比べて低賃金傾向にある現状について、各所で指摘されてきていますが、中々改善が進まないのが現状のようです。2019年には改正労働基準法が施工され、運送事業の運転者においては5年の猶予が与えられましたが、2024年の適用開始までは残り3年となりました。
-
 マネジメント
マネジメント
アルコールチェッカー(アルコール検知器)のメンテナンスの重要性
平成23年の5月より、事業用自動車の運転者の飲酒運転を根絶するため、運送事業者が運転者に対して実施することとされる点呼において、運転者の酒気帯びの有無を確認する際にアルコールチェッカー(検知器)を使用すること等が義務化されました。
-
 マネジメント
マネジメント
点呼業務の重要性と健康把握について
自動車運送事業に携わる方々にとって、「点呼」とは日々の業務の中で必ず行うものであり、ごく当たり前の事であると思います。「点呼」の内容やその重要性については、改めて説明するまでもありませんが、自動車運送事業に従事する方の健康維持や労働環境の改善などの観点から、改めて「点呼」の重要性が強く叫ばれる様になってきました。
-
 時事ネタ
時事ネタ
ロジスティクス導入で輸送コスト削減・業務効率の向上へ
トラック運送業界は「安全で安心な輸送サービスを提供し続けること」が社会的使命であり、常に「安全」を最優先課題とされています。運送業界の主役のトラック事業は、自然災害が発生した際には支援物資の輸送・新型コロナウイルス感染症により物流の維持が求められた際には日本のライフラインとして活躍しています。
-
 法改正・規制
法改正・規制
バス・タクシー事業所−車庫間のIT点呼が可能に−
平成30年3月に国土交通省が旅客自動車運送事業運輸規則を一部改正したことにより、バス・タクシー事業でも、一定の要件を満たす優良な事業所での事業所−車庫間のIT機器を用いた点呼(IT点呼)が可能になりました。
-
 点呼システム
点呼システム
クラウドサービスとは?概要からメリットまで分かりやすく解説
世間でよく耳にするようになった「クラウド」という言葉ですが、なんとなく知っていても詳しくは分からないという方も多いのではないでしょうか。最近では企業向けのクラウドサービスがCMで流れるなど、色々な面で話題となっています。
-
 法改正・規制
法改正・規制
IT点呼キーパーの導入で運行管理者の働き方が変わる
2018(平成30)年6月、働き方改革関連法が成立し、2019年4月から改正労働基準法が全産業を対象に施行されています。ワークライフバランスを改善しつつ労働生産性向上を図るとの考え方が示されており、トラックドライバーについては一般則とは別の取り扱いとなり、2024年4月から年960時間の時間外労働の罰則付き上限規制が適用されます。
-
 法改正・規制
法改正・規制
点呼とトラック運行指示書のポイント
2016年1月に発生した軽井沢スキーバス転落事故では、運行前点呼を実施しておらず、会社がドライバーに渡していた運行指示書には出発地と到着地のみしか記載されていないなどの杜撰な運行管理が明るみに出て大きな問題になりました。国土交通省では、軽井沢スキーバス事故を受け、緊急対策として全国の貸切バス事業者計310事業者を対象に集中監査を実施した結果、何らかの法令違反を確認した事業者数240(77.4%)、そのうち「運行指示書の作成等が不適切」として96事業者(31.0%)で記載内容や携行に問題があることが分かりました。
-
 マネジメント
マネジメント
血圧測定の重要性
近年、高血圧の運転者に突然発生する病気が起因となる交通事故のニュースを耳にすることが増えているのではないでしょうか。そこで今回のコラムでは、点呼時の血圧測定の健康状態を把握するための有益な情報をお伝えしていきます。
-
 点呼システム
点呼システム
点呼システム導入による点呼品質の向上
近年の交通事故数は減少の傾向にありますが、運輸業における重大事故のニュースを目にする機会はあまり減っていない様にも感じられます。また、ドライバーの健康状態に起因する事故も多く耳にするようになり、ニュースでも乗務時の確認の重要性が叫ばれるようになって来ました。
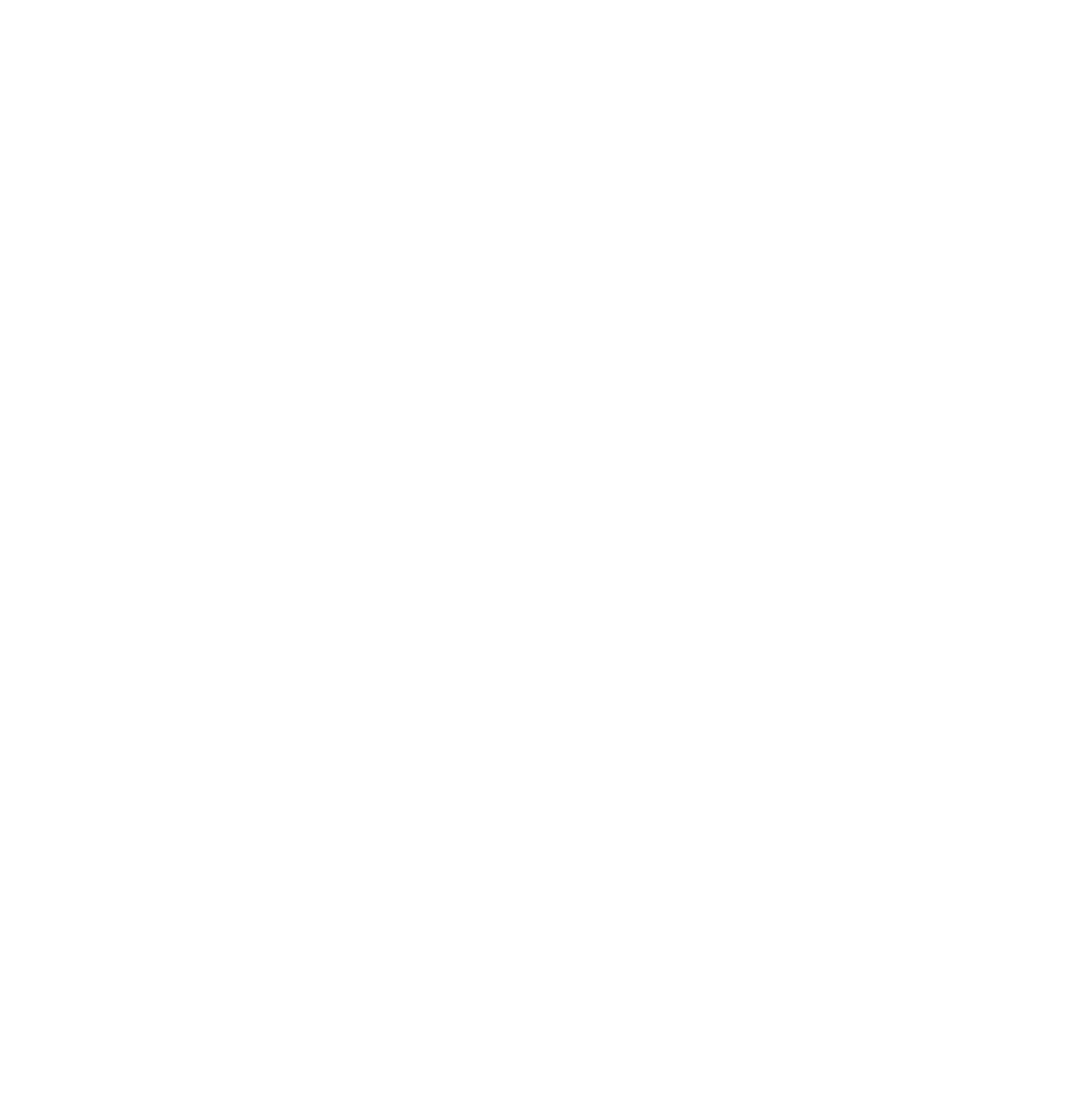 この記事をシェアする
この記事をシェアする
人気のコラム 月間ランキング
-
1

-
法改正・規制
正しい点呼で違反を防ごう~運送業における正しい点呼とは~
自動車運送事業における点呼は、輸送の安全を確保するために法令により実施が義務付けられている業務です。ICT技術の高度化が目覚ましいことから対面点呼に代わる遠隔点呼が実施できるようになり、令和4年4月1日から申請がスタートしています。また令和5年1月からは、乗務を終了したドライバーに対する点呼を自動で実施できる業務後自動点呼がスタートしました。北陸信越運輸局が令和元年6月に公表した平成30年度の自動車運送事業者の行政処分の内容分析結果では、自動車運送事業の最多違反は点呼でした。点呼においては運転者の名前以外にも様々な確認項目があり、確実な点呼を行えていると思っていても違反となる場合や、分かっていても確実な点呼を実施することが負担となる場合など理由は色々とあるでしょう。
-
2

-
法改正・規制
遠隔点呼とは?遠隔点呼の申請ルールが令和5年4月から変更
2022年(令和4年)4月より開始した「遠隔点呼」ですが、2023年(令和5年)3月31日以降ちょっとした変化があったことをご存じでしょうか。これに伴い、遠隔点呼の要件や申請方法が変更されました。そこで本記事では遠隔点呼の定義をおさらいし、2023年4月1日以降の申請方法について解説しますのでトラック事業者の方は参考にしてください。
-
3

-
法改正・規制
運行管理者試験とは?日程や出題内容・難易度と受験対策のポイントを解説
安全運転をして当たり前と見られるトラック、バス、タクシーなどのプロドライバー。しかし彼らも人間であるため、常に万全の状態で運転できるとは限りません。体調が悪いのに無理をして運行し、事故を起こしたら当事者や会社、乗客や顧客など多くの人に被害がおよびます。そこで、事故を防ぎ業務を円滑化する運行管理者が必要なのですが、選任には資格が必要です。この記事では、運行管理者試験の受験方法や試験の難易度、合格への対策などをご紹介します。最後までご覧いただき、あらゆる人を事故から守るキーマンを目指してください。
-
4

-
法改正・規制
遠隔点呼とIT点呼の違いをカンタンまとめ
令和4(2022)年4月より、「遠隔点呼実施要領」に基づいた遠隔点呼の申請が開始されています。すでに実施されている「IT点呼」と新たに申請できるようになった「遠隔点呼」には、どのような違いがあるのでしょうか?対面点呼と比べると遠隔点呼とIT点呼は同義に見えることから、どうしても混乱しがちです。本記事では遠隔点呼とIT点呼の違いをまとめましたので、ぜひ参考にしてください。
-
5

-
時事ネタ
Gマーク更新|2023年度(令和5年)|Gマーク認定を継続するメリットを解説
皆様は2023年に「Gマーク制度」が、創設から20年を迎えることをご存知でしょうか。Gマークはトラック運送事業者の安全性を客観的に示す評価指標として浸透し、トラック業界において差別化を図る手法として、注目を集めています。各地方ト協を通じて毎年7月に申請受付が行われ、当該年度に認定された安全性優良事業所が12月に公表される流れです。2021年12月には、全国の認定事業所および認定事業者数は28,026でした。これは全事業所の32.1%、緑ナンバートラック車両全体の約5割に相当し、Gマーク認定事業所数は増加傾向にあります。実際に全ト協の2022年12月15日付発表によると、Gマーク認定事業所数は28,696にのぼり、全事業所の33%まで増加しました。本記事では、Gマーク制度の概要、2023年度の更新申請について特別措置や変更点などを見ていきましょう。Gマーク更新継続のメリットやインセンティブなど、Gマークの最新情報についても紹介するので、トラック運送事業者の方はぜひ参考にしてください。