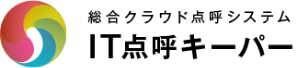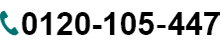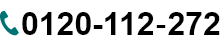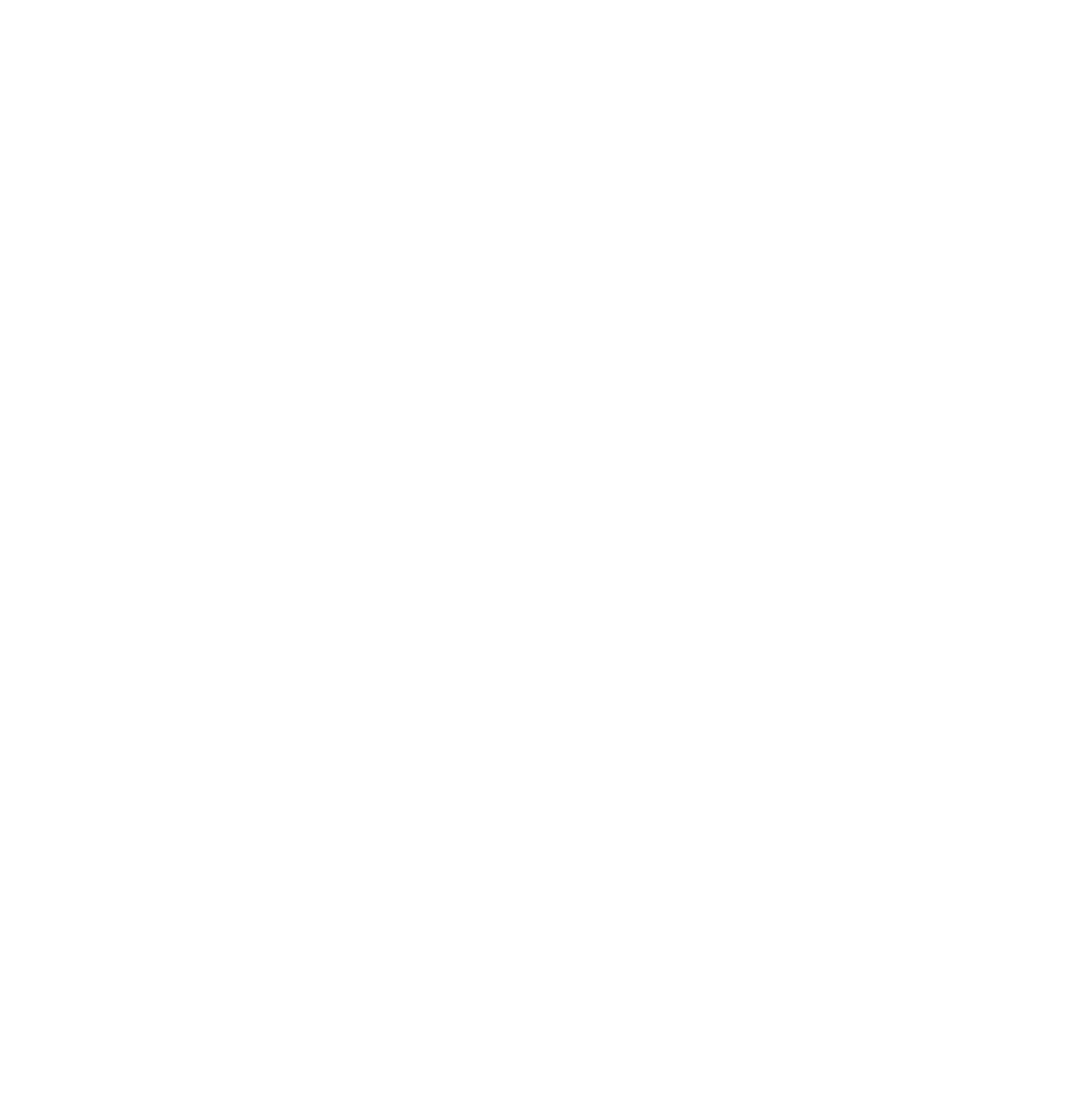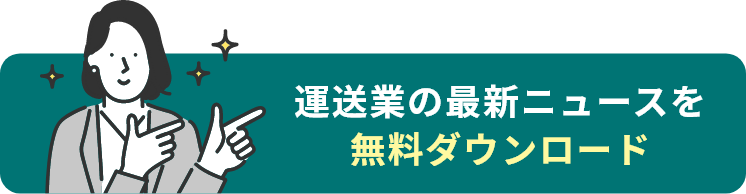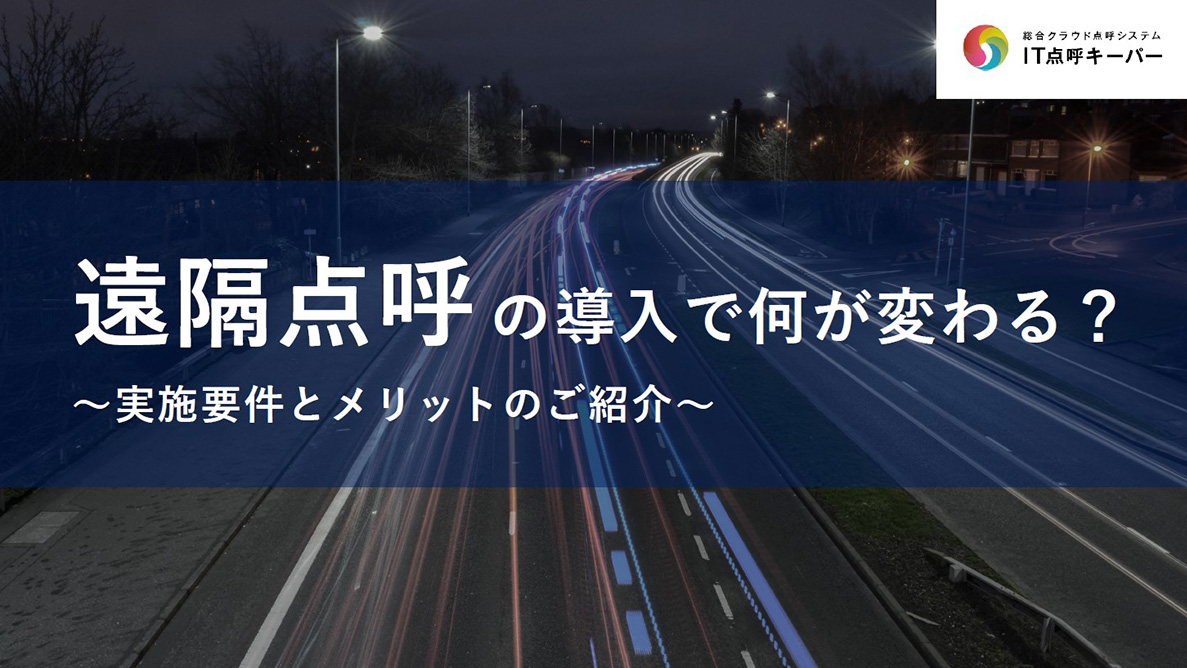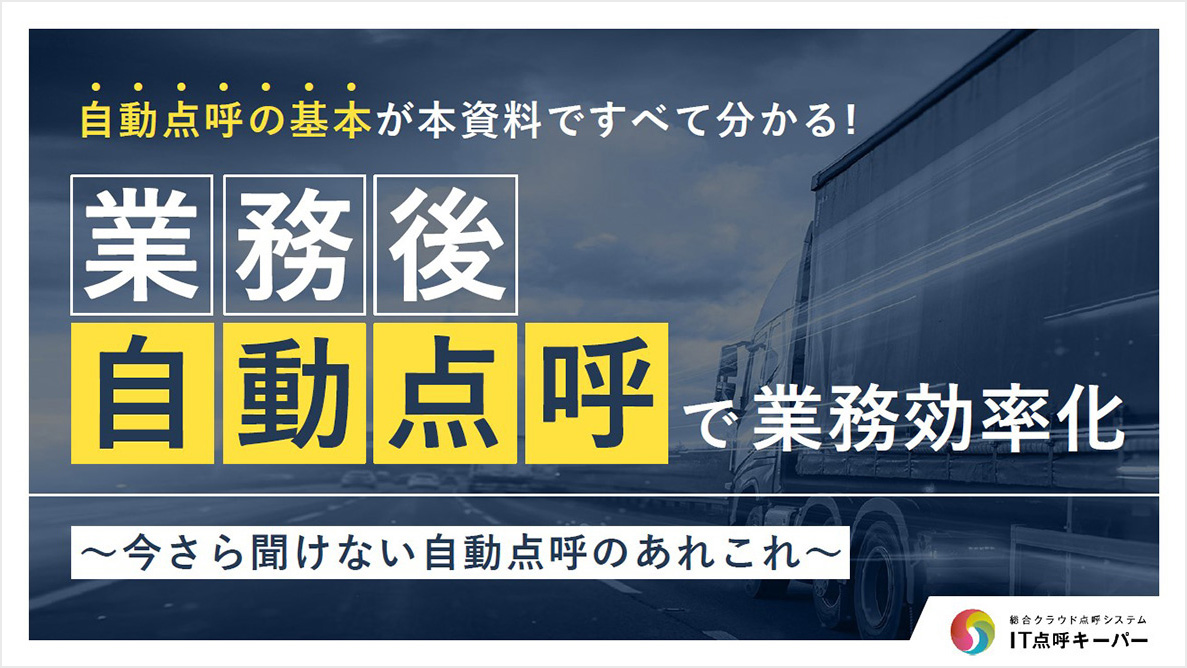Gマーク更新|2023年度(令和5年)
ここでは、2023年度のGマーク更新についてご紹介します。
Gマーク更新に必要なこと
Gマークの更新手続きには、全ト協から4月中旬に送付される「Gマーク更新のご案内」ハガキが必要になります。上述の更新対象とされる認定番号を保有しているにもかかわらず、4月末になっても届かない場合には、都道府県トラック協会に問い合わせるようにしましょう。
Gマークの更新申請の方式には「通常申請(A)」と「特例申請(BからEのいずれか)」の2種類があり、特例申請はさらに4タイプに分かれていました。しかし、2023年度(令和5年度)より「D方式」は廃止されますので注意してください。
つまり更新申請の方式は、合計4タイプです。更新案内のハガキには、利用可能な申請方式が記載されているのでチェックしてみてください。
なお申請案内は、2023年4月中旬以降に公表される見込みです。申請期間は2023年6月下旬から7月中旬となるように、また申請書類の一部を電子申請とするように調整されています。システムの稼働期間は、例年4月中旬以降です。
申請期間内は、申請書情報を入力する人でシステムが大変混雑するため、時間に余裕をもって「申請書作成システム」を利用しましょう。
6回目更新を迎える事業所の申請方法
制度開始から20年を迎える2023年度からは、6回目更新を迎える事業所は20年間認定を更新していることになります。そこで安全運行の実績から「長期認定取得事業所」と認定されると、ゴールドステッカーが付与される予定です。
また「評価項目3.安全性に対する取組の積極性」について、挙証書類の提出は原則不要となります。取組内容については「自認」するなどして、申請手続きが簡素化される予定です。ただし「評価項目2.事故や違反の状況」については、従来通り、新たに評価が実施されます。
なおGマーク更新申請の方式の選択方法は、従来通り(「D方式」は廃止)です。
Gマーク更新の評価項目と申請方式
Gマーク更新の評価項目は次のとおりです。「2.事故や違反の状況」については、更新希望の全ての事業所を対象に評価が行われます。いずれかの項目の評価を受けたくない場合には「特例申請(B・C・Eのいずれか)」を選ぶことで、該当項目の前回の評価点数を適用可能です。
ただし、特別申請を2回連続して選択できない点に留意しましょう。つまり前回「特別申請」を選んだ事業所は、今回の更新申請においては自動的に「通常申請(A)」を選ぶことになります。
| 評価項目 |
配点 |
基準点数 |
更新時に新たに評価する方式 |
前回の評価点数を用いる方式 |
| ①安全性に対する法令の遵守状況 |
40点 |
32点 |
A/B |
C/D/E |
| ②事故や違反(行政処分)の状況 |
40点 |
21点 |
A/B/C/E |
なし |
| ③安全性に対する取組の積極性 |
20点 |
12点 |
A/C |
B/E |
2023年度以降のGマーク申請の変更点
2023年度以降のGマーク申請においては、6回目更新を迎える事業所の申請方法が追加になったほか、取り扱いの一部が変更になる予定です。ここでは主な変更点について見ていきましょう。
「評価項目1.安全性に対する法令の遵守状況」において、次のような小項目の配点の一部が変更になります。
| 小項目 |
旧配点 |
新配点 |
| 運転日報の作成・保存 |
3点 |
1点 |
| 特定運転者に対する特別指導 |
1点 |
2点 |
| 健康診断の実施及び記録・保存 |
1点 |
3点 |
| 運輸安全マネジメント |
3点 |
2点 |
また「運輸安全マネジメント」の評価は、申請書類によるのではなく巡回指導結果による評価へと変更されます。
「評価項目3.安全性に対する取組の積極性」について、配点が「20→21点」に変更になりました。さらに自認項目を4つにグループ分けして、各グループごとに得意項目を選択できるようになります。また以下の項目において大きな変更点があるので、詳細について確認するようにしてください。
- 1-(3)定期的な「運転記録証明書」の入手による事故・違反実態の把握に基づく指導の実施
- 2-(2)事業所内の安全に関するQC活動の定期的な実施
- 3-(2)効果の高い健康起因事故防止対策(脳検査・心電計・ SAS)
- 3-(3)車両の安全性を向上させる装置の装着
- 4-(1)健康起因事故防止対策に向けた取り組み(脳検査・心電計・SAS以外の実施)