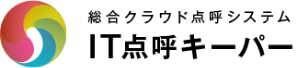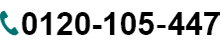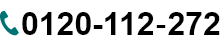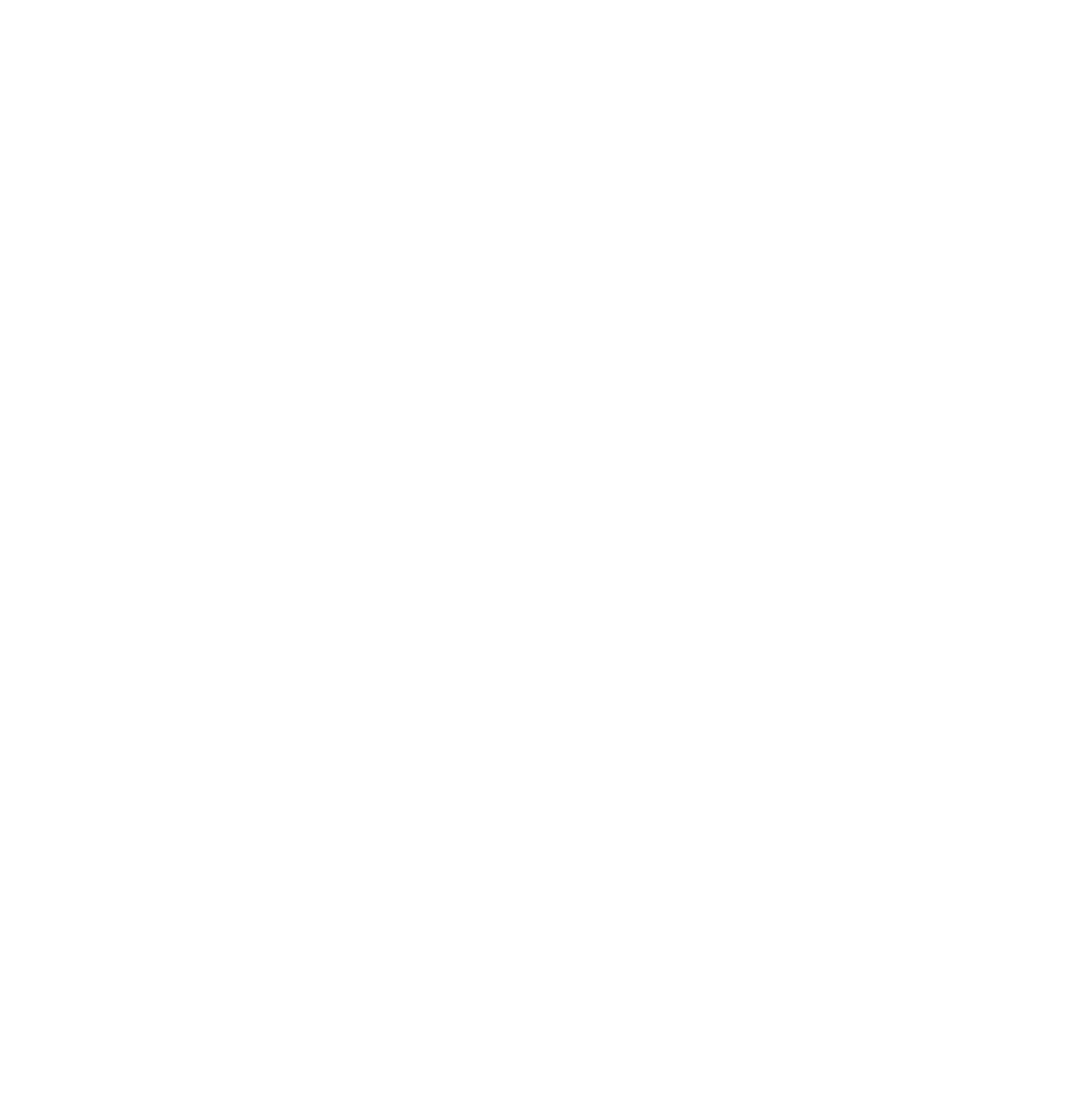点呼の種類と正しい実施ルールについて
点呼にはさまざまな種類があり、それぞれに応じたやり方や実施ルールがあります。
以下で、各点呼の種類と正しい実施ルールについて解説します。
- 対面点呼
- 電話点呼
- IT点呼
- 遠隔地IT点呼
- 遠隔点呼
- 業務後自動点呼
対面点呼
運転者が営業所、又は車庫の定められた場所で点呼執行者と直接立ちあい行う点呼です。運行上やむを得ない場合以外は、原則、所属の営業所、車庫で業務前、業務後に対面点呼を実施しなければいけません。
電話点呼
一泊二日や、二泊三日などに及ぶ運行により、運転者が営業所、または車庫の定められた場所で点呼が行えない(運行上やむを得ない場合)に電話等による点呼執行者と直接対話できる方法で行う点呼です。
※携帯電話や業務無線等ドライバーと直接対話できるもので行います。
※電子メール、FAXなどの一方的な連絡方法は該当しないため注意が必要です。
※営業所と車庫が離れている、点呼執行者が出勤していない、などの理由も該当しません。
IT点呼
IT点呼とは、同一の事業者内のGマーク営業所において認められる点呼方法です。
Gマーク制度は、国土交通省が推進する「安全性優良事業所」の認定制度で、貨物自動車運送事業安全性評価事業とも呼ばれています。Gマーク営業所は、従来は対面で実施されていた点呼方法に加え「国土交通大臣が定めた機器」を使用して、営業所間または営業所と車庫間で点呼が実施できるわけです。
IT点呼を導入すると、カメラあるいはモニターを駆使して、離れた場所でも対面と同様の点呼を実施することが可能になります。少ない人員でも早朝や深夜の点呼に対応できるため対面点呼よりも人件費を削減できるほか、点呼記録が自動保存される点も大きなメリットです。
IT点呼が認められる範囲・時間帯については以下のとおりです。
IT点呼が認められる範囲
- Gマーク取得営業所の場合
- 営業所とその車庫間
- 営業所の車庫と当該営業所の他の車庫間
- 営業所と他の営業所間
- 営業所と他の営業所の車庫間
- Gマーク未取得営業所の場合
- 営業所とその車庫間
- 営業所の車庫と当該営業所の他の車庫間
Gマーク未取得営業所は以下4要件をクリアすることでIT点呼が認められています。
- 営業所開設後3年を経過していること。
- 過去3年間、第1当事者となる自動車事故報告規則に規定する事故を発生させていないこと。
- 過去3年間、点呼の違反に係る行政処分等を受けていないこと。
- 適正化実施機関の直近の巡回指導評価がD、E以外であり、点呼に関する指摘がない、または点呼に係る改善報告書が3ヵ月以内に提出され改善が図られていること。
IT点呼が認められる時間帯
- 1営業日のうち連続する16時間以内(ただし、同一営業所内の車庫間は制限なし)
IT点呼を導入すると、カメラあるいはモニターを駆使して、離れた場所でも対面と同様の点呼を実施することが可能になります。少ない人員でも早朝や深夜の点呼に対応できるため対面点呼よりも人件費を削減できるほか、点呼記録が自動保存される点も大きなメリットです。
遠隔地IT点呼
遠隔地IT点呼とは、電話(スマートフォン)を使って遠隔地にいるドライバーと「IT点呼」を執行する非対面での点呼方式です。
通常、他営業所に所属するドライバーとの電話点呼は認められていませんが、一定の条件を満たすことで、遠隔地IT点呼の執行が認められます。
遠隔地IT点呼には、IT点呼の基本ルールが適用されます。
国土交通省の定める要件をクリアできるIT機器等を用いる必要があります。
また、点呼時には映像付きで相手の表情が確認できる必要があります。
遠隔点呼
遠隔点呼とは、対面点呼に代わる点呼方法として登場した、労働生産性向上・輸送の安全を確保したうえで、運行管理の効率化を図るための点呼方式です。
バス・ハイヤー・タクシー・トラックなどの自動車運送事業者が、機器を利用して「車庫間」あるいは「営業所間」及び「グループ企業(100%子会社)等の営業所間」のいずれかの遠隔拠点間で実施する点呼を指します。
「新・点呼告示(旧・遠隔点呼実施要領)」で定める要件を満たせば、遠隔拠点間の点呼「遠隔点呼」が可能になります。「新・点呼告示(旧・遠隔点呼実施要領)」で定義されたのは、次の8つの実施パターンです。
| 遠隔点呼を実施する場所 |
実施パターン |
| 営業所内 |
①営業所と当該営業所の車庫間
②当該営業所の車庫と当該営業所の他の車庫間 |
| 営業所等間 |
③営業所と他の営業所間
④営業所と他の営業所の車庫間
⑤営業所の車庫と他の営業所の車庫間
⑥営業所とグループ企業の営業所間
⑦営業所とグループ企業の営業所の車庫間
⑧営業所の車庫とグループ企業の営業所の車庫間 |
| 宿泊地・待合所・車内等間 |
⑨営業所と宿泊地・待合所・車内等間
⑩車庫と宿泊地・待合所・車内等間
⑪グループ企業の営業所と宿泊地・待合所・車内等間
⑫グループ企業の車庫と宿泊地・待合所・車内等間 |
従来は、法令遵守の意識が高いとみなされるGマーク取得営業所の優良性を前提条件としてIT点呼が実施されていました。しかし、ICTの目覚ましい技術の発展から、事業所の「優良性」というしばりが緩和され、Gマーク未取得営業所でも実施可能な遠隔点呼という制度がスタートしたのです。
ただし、遠隔点呼の導入にあたっては、「新・点呼告示(旧・遠隔点呼実施要領)」で定められた「機器・システム要件」「施設・環境要件」「運用上の遵守事項」を満たす必要があります。
なお、同一の事業者間だけでなく、100%の資本関係がない事業者や資本関係がない事業者同士でも遠隔点呼を行うことができます。この仕組みは「事業者間遠隔点呼」と呼ばれます。事業者間遠隔点呼を行う場合、遠隔点呼告示の第5条・第6条・第7条を遵守し、運行管理者が選任されている営業所や車庫、または運行管理者が所属する事業者の配車センターなどで実施されます。
2024年10月時点では、事業者間遠隔点呼は先行実施中であり、許可を受けた場合、最長で令和7年3月31日まで行うことが可能です。申請の締め切りは令和6年12月28日までで、開始予定日の40日前までに申込書に必要事項を記入し、国土交通省委託事業事務局(株式会社野村総合研究所)にメールで電子データを送信してください。
業務後自動点呼
業務後自動点呼は、2023年1月より開始された新しい点呼制度です。
業務後自動点呼実施要領に定められた要件を満たすとして認定を受けた機器を使用して、当該事業者の営業所または営業所の車庫において乗務終了後に行う点呼(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条2項及び4項の規定に適合する対面点呼)です。
機器に求められる基本要件は、こちらのページをご覧ください。
業務後自動点呼では、認定を受けた機器、すなわち自動点呼機器で自動化することから運行管理者は点呼に立ち会う必要はありません。しかし機器が故障したりアルコールが検知されたりといった非常時においては、常に人が対応できる体制を必要とするため「条件付き」の自動点呼とされています。
また、日々の点呼をすべて 自動点呼機器に任せてしまうと運行管理者とドライバーのコミュニケーションの機会がなくなる・携行品の確認など自動点呼機器では確認が困難なケースもあります。非常時の機器から運行管理者 への切り替えは、現状認められている点呼方法であれば適用できます。
そこで業務後自動点呼を運用する際には、IT点呼キーパーなどの遠隔地でも点呼ができる仕組みと組み合わせるといった工夫がおすすめです。