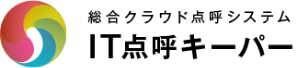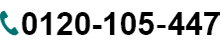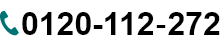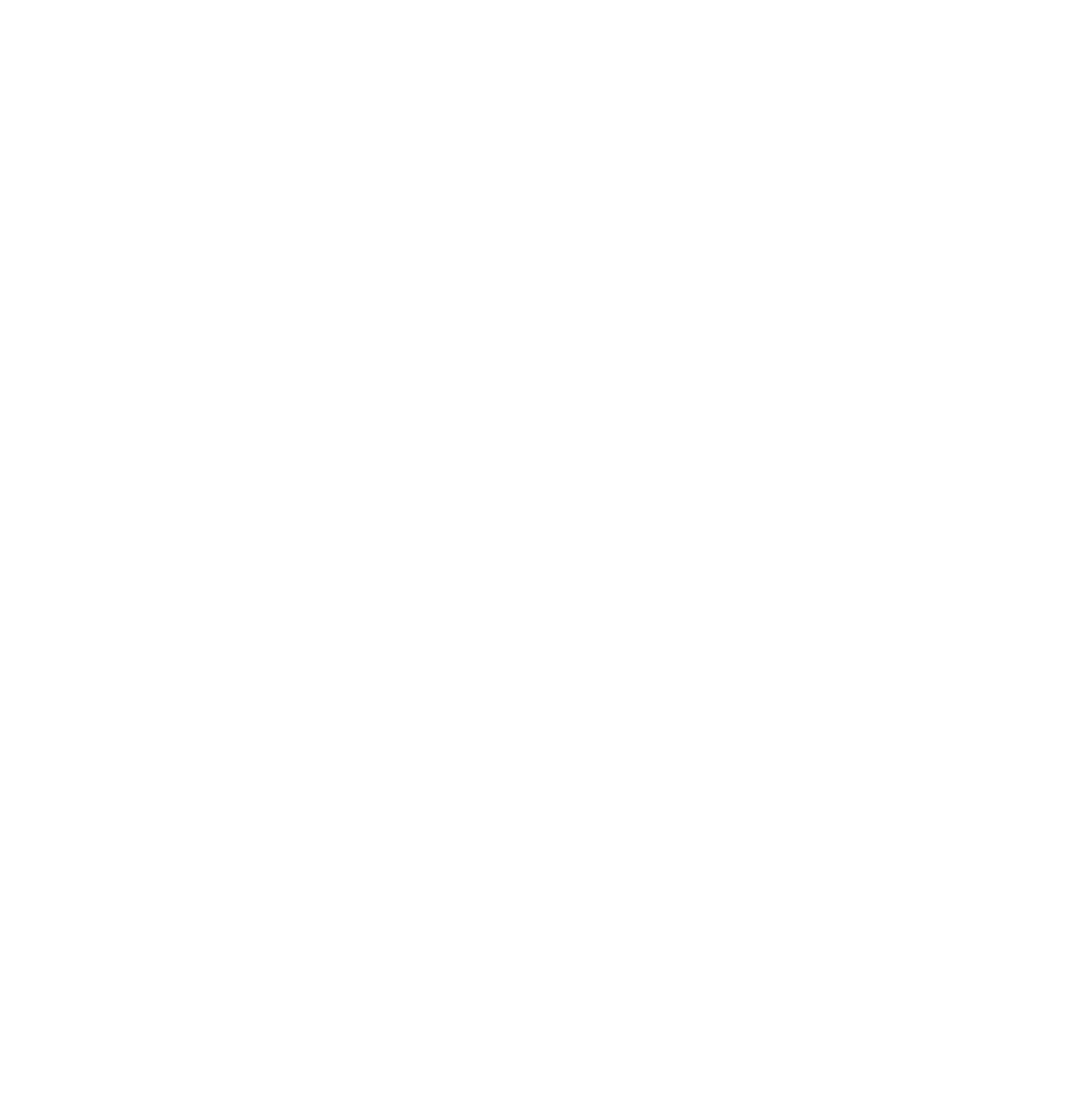Gマークの取得条件
Gマークを取得するためには、事業者が一定の評価基準を満たす必要があります。
具体的な条件を見ていきましょう。
申請資格を得ている
Gマークの申請を行うには、まず運送事業の許可を取得し、適正に事業を運営していることが大前提です。過去に重大な法令違反や事故が頻発していないか、営業所全体の安全意識が高いかどうかも問われます。
対象となる申請資格には、以下の2パターンが存在します。
- 全ての申請者が対象の申請資格
- 申請や認定の取り消しを受けた事業所のみが対象の申請資格
全ての申請者が対象の申請資格
- 事業を開始してから3年が経過している
- 事業用自動車の数が5両以上ある
申請や認定の取り消しを受けた事業所のみが対象の申請資格
- 虚偽申請など不正な手段等によって申請の却下や評価の取消しを受けた事業所の場合、その処分年度から事業年度が2年経過している
- 不正申請等によって認定の取消しを受けた事業所の場合、取消し処分から2年が経過している
- 認定証や認定マーク、認定ステッカー等の偽造・変造・不正使用により是非勧告を受けた事業所の場合、その是非勧告の履行状況の確認および偽変造等の認定証等の提出を受けた日から3年を経過していること
これらの条件をクリアして初めて審査を受ける資格が得られるため、日頃から違反や事故を減らす努力が必要不可欠です。特に運転者の教育や運行管理者の配置など、基本的な運営体制を整えておくことが重要です。
評価基準をクリアしている
Gマーク取得の対象になる基準は、3つの評価項目と4つの認定要件をもとに認定されます。
各テーマの基準点を満たしたうえで、100点満点中80点以上の得点を得ていることが認可条件です。
- 安全性に対する法令の遵守状況:配点40点・基準点数32点
- 事故や違反の状況:配点40点・基準点数21点
- 安全性に対する取組の積極性:配点20点・基準点数12点
| 項目 |
点数 |
内容 |
| 安全性に対する法令の遵守状況 |
配点40点
(基準点数32点) |
巡回指導結果
運輸安全マネジメントの取組状況 |
| 事故や違反の状況 |
配点40点
(基準点数21点) |
重大事故・行政処分状況 |
| 安全性に対する取組の積極性 |
配点20点
(基準点数12点) |
安全対策会議の実施、運転者の教育などの取り組みの自己申告事項 |
2023年度からの変更点
2023年度から、評価項目や配点、および申請の取り扱いについて一部変更が実施されます。
「評価項目I安全性に対する法令の遵守状況」における変更点は、次のとおりです。
- 「小項目」の配点を一部変更
- 「運輸安全マネジメント」の評価が申請書類から巡回指導結果による評価へ変更
「評価項目III安全性に対する取組みの積極性」においては配点が21点から20点に変更になったほか、自認項目は4つのグループに分けられ、各グループから得意項目を選択できるようになりました。
また全日本トラック協会は2023年度から、6回目更新を迎える事業所を「長期認定取得事業所」としてさらなる差別化を図ります。20年間もの長きにわたり輸送における安全運行を実現している実績に敬意を払い、「評価項目III安全性に対する取組みの積極性」においては挙証書類提出を原則不要とするなど申請手続きが簡素化される見込みです。
また通常のステッカーとは異なる「ゴールドステッカー」の付与が検討されています。
認定要件
従来の認定要件は次のとおりです。
- 上記1〜3の評価連数の合計点が80点以上
- 上記1〜3の各評価項目において上記の基準点数以上
- 法に基づく認可申請、届出、報告事項が適正になされていること
- 社会保険等の加入が適正になされていること
認可申請・届出・報告事項を行っている
事業許可や運行管理者、事業所の変更など運送事業者を取り巻く各種の変更点は、法令に基づく届け出が義務付けられています。これを適正に行っていないと、認定の際に大きな減点要素となる可能性があります。定期報告や許可書の更新操作を怠っている場合も同様に、厳しい評価対象となるため注意が必要です。法令に沿った手続きを随時行いながら、適切な記録管理を行うことが合格の鍵になります。
認可申請・届出・報告事項については、9つの項目を満たす必要があります。
- 主な活動拠点である事業所および営業所の名称、位置に変更がないか
- 営業所に配置している事業用自動車の種別および数に変更がないか
- 自動車車庫の位置および収容能力に変更がないか
- ドライバーの休憩・睡眠施設の位置、収容能力に変更がないか
- 届出事項に変更がないか
- 自動車事故報告書を提出しているか
- 事業報告書・事業実績報告書を提出しているか
- 運行管理者の選任等に関する内容を届出しているか
- 整備管理者の選任等に関する内容を届出しているか
指導があった場合でも、以下の期日までに改善し、報告を行えば認定条件をクリアすることができます。
- 申請基準日前に指導を受けた場合:指定の期日まで
- 申請基準日以後に指導を受けた場合:指導から1か月以内
社会保険等へ適正に加入している
社会保険や雇用保険は、従業員の雇用環境を守るうえで欠かせない制度です。したがって、これらに適正に加入していない事業所は、Gマーク取得の審査において大きなマイナスとなります。特に運転者や事務スタッフなど、すべての従業員が正しく保険に加入しているかを証明できるような書類の整備が重要です。これら法定保険を正しく管理することで、安全性だけでなく企業としての社会的責任も果たしていると認められます。
労災保険・雇用保険への加入状況
労災保険・雇用保険への加入状況としては、以下の項目を満たす必要があります。
- 適用事業所として労働基準監督署に正しく届出している
- 法に定められた従業員が保険に加入している
- 雇用保険について、所定の保険料を控除している
- 労働基準監督署へ適切に保険料を納付している
健康保険・厚生年金保険への加入状況
健康保険・厚生年金への加入状況としては、以下の項目を満たさなければなりません。
- 適用事業所として、健康保険を年金事務所または健康保険組合に正しく届出している
- 適用事業所として、厚生年金保険を年金事務所に正しく届出している
- 法に定められた従業員が保険に加入している
- 所定の保険料を控除している
- 年金事務所または健康保険組合に保険料を適切に納付できている