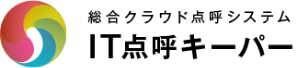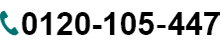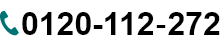自動運転レベルとは?
自動運転とは、以下のように定義されています。
(引用)
運転者ではなくシステムが、運転操作に関わる認知、予測、判断、操作の全てを代替して行い、車両を自動で走らせること。
左右にスライドすると画像を見ることができます。
| システムが周辺監視 | レベル5 | 完全自動運転 |
| レベル4 | 特定条件下における 完全自動運転 |
|
| レベル3 | 特定条件下における 自動運転 |
|
| ドライバーが周辺監視 | レベル2 | 高度な運転支援 (自動の追い越し等) |
| レベル1 | 運転支援 (衝突被害軽減ブレーキ等) |
※特定条件とは、場所、天候、速度など自動運転が可能な条件
【出典】:自動運転の実現に向けた動向について|国土交通省(参照2024-06-25)
次の章以降で、各運転レベルについて詳しくご紹介します。
自動運転レベル1:「運転支援」
自動運転レベル1についてご紹介します。ポイントは以下のとおりです。
- ドライバーが主体となって運転する
- ドライバーの運転を支援する機能を有している
- 対応車両は「運転支援車」と呼ばれる
自動運転レベル1の定義・機能
自動運転レベル1の車両は「運転支援」ができることと定義されています。ゆえに、運転操作のメインは人です。
レベル1による運転支援は、アクセル・ブレーキ操作またはハンドル操作のいずれかを部分的に自動化し、縦方向もしくは横方向の動きをアシストします。
代表的な機能として以下のものがあります。
- 衝突被害軽減ブレーキ
- 前車追従機能(ACC)
- 車線逸脱防止機能(LKAS)
衝突回避はもちろん、車間距離の保持や車両のふらつきを監視し、周囲の人や車に不安を与えない運転ができます。頻繁な加減速が必要な渋滞時には疲労軽減にも一役買ってくれるでしょう。
自動運転レベル1の市販車
2021年11月から国産新型車には衝突被害軽減ブレーキの搭載が義務化されています。その他車種への衝突被害軽減ブレーキの搭載義務化時期は以下のとおりです。
| 国産車 | 輸入車 | |
|---|---|---|
| 新型車 | 2021年11月 | 2024年7月 |
| 継続生産車 | 2025年12月 | 2026年7月 |
自動運転レベル2:「部分運転自動化」
自動運転レベル2についてご紹介します。ポイントは以下のとおりです。
- ドライバーが主体となって運転する
- ドライバーの運転を支援する「高度な機能」を有している
- レベル1同様、対応車両は「運転支援車」と呼ばれる
自動運転レベル2の定義・機能
自動運転レベル2もレベル1と同じく「運転支援車」と定義されますので、運転は人がメインとなります。
レベル1との違いは、運転を支える機能がより高度な点です。具体的には、アクセル・ブレーキ操作とハンドル操作の両方に、自動化された機能が搭載されていなければなりません。代表的な機能として、自動追い越し機能が挙げられます。
また、レベル1の機能を組み合わせた自動運転機能はレベル2となります。車線をキープしつつ、前車に追従する機能などがレベル2の一例です。
自動運転レベル2の市販車
現在の自動車業界では、自動運転レベル2=ハンズオフ(手放し)運転が可能な車と認識されています。
2024年時点で、ハンズオフ運転が可能な国産車種をまとめましたので参考にしてください。
左右にスライドすると画像を見ることができます。
| メーカー | システム名 | 搭載車種 |
|---|---|---|
| トヨタ | Advanced Drive | MIRAI アルファード・ヴェルファイア ノア・ヴォクシー クラウン ランドクルーザー”250” センチュリー |
| 日産 | プロパイロット2.0 | アリア セレナ |
| ホンダ | Honda SENSING | ほぼ全車種に搭載 |
| スバル | アイサイトX | レイバック レガシィアウトバック レヴォーグ WRX S4 |
自動運転レベル3:「条件付き運転自動化」
自動運転レベル3についてご紹介します。ポイントは以下のとおりです。
- システムが運転の主体になる
- 場合によっては人が操作をフォローする
- 走行できる場所は限定される
自動運転レベル3の定義・機能
自動運転レベル3からは、自動運転システムが主体となって自動車をコントロールします。
ただし、レベル3では走行する領域に限りがあること、自動運転中にシステムが正常に作動しない場合に備えて、自動車を運転できる人が乗って対応できる状態にしておくことが求められます。
基本的にはシステム任せで、運転者が視線を前方から外しても問題ないことから、レベル3はアイズオフ運転が可能な車と認識されており、高速道路でのみ使用が可能です。
自動運転レベル3の市場規模
自動運転レベル3を実現するために必要なシステムはまだ価格が高いため、レベル2から敷居が高くなります。
株式会社富士キメラ総研が自動運転車の世界市場について調査した「自動運転車の世界市場を調査」によると、2030年では生産台数ベースで自動運転レベル3以上の車両は580万台程度と見込まれています。レベル2は6,176万代ほどと見込まれているので、その差は歴然です。
【出典】:自動運転車の世界市場を調査|富士経済グループ(参照2024-06-25)
自動運転レベル3の法的動向
日本では、2019年5月に道路運送車両法が改正されました。この改正で、自動運転者等の安全性を一体的に確保するために、「自動運行装置」を保安基準の対象としました。同法は2020年4月に施行され、事実上、自動運転レベル3が解禁されています。
また、損害賠償責任に関する検討もされていますが、2024年現在では迅速な被害者救済のため、自動運転レベル4までの自動運転システム利用による交通事故については、自賠法第3条に定める運行供用者責任を適用することとしています。
自動運転レベル3の市販車
市販車向けに自動運転レベル3を実装しているのは、2024年1月現在でホンダのレジェンドとメルセデスベンツのSクラス・EQSのみです。
レジェンドは100台限定のリース販売であることやコストの高さから、レベル3の市販車が大衆向けに発表されるのはまだ先となりそうです。
自動運転レベル4:「高度運転自動化」
自動運転レベル4についてご紹介します。ポイントは以下のとおりです。
- 特定条件下で運転をすべてシステムに任せられる
- 貨物、旅客輸送サービスを視野に入れた自動運転に必要なレベル
自動運転レベル4の定義・機能
自動運転レベル4は走行条件とエリアこそ限定されますが、従来の人による運転操作を自動運転システムが完全に代替すると定義されています。
人による運転操作をそもそも想定しておらず、ブレインオフ車と呼ばれています。
- 高速道路での自動運転
- 限定地域内での無人自動運転配送サービス
- 限定地域内での無人自動運転移動サービス
自動運転レベル4では、これらの運転が可能となる機能が必要です。
自動運転レベル4の市場規模
自動運転レベル4は移動(バス・タクシー)、物流(トラック)サービス向けの実証実験が市販車向けより先に行われています。
走行ルートや地域を限定するため、路線バスやスクールバス、空港など広い敷地内で走行する送迎用の車両への搭載が実用性・需要が共に高いこと、実装コストがまだ高いことが理由です。
また、走行エリアが限定されていれば、国や自治体の運行許可も出やすくなると予想されており、レベル4に関しては市販車より商用車優先の開発、実用化を目指す動きが活発化しています。
さらに、2024年4月のライドシェア解禁が自動運転車の需要に影響する可能性があります。
ライドシェアによる交通事故等が増加した場合、安全性を担保できれば自動運転車の需要が大きく上がるかもしれません。
ライドシェアの解禁や解禁に伴う問題点、メリットについて詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
自動運転レベル4の法的動向
国内では、2023年4月に施行された改正道路交通法で、自動運転レベル4による運転者不在の運転を「特定自動運行」と定義し、特定自動運行に関するルールを整備したことで自動運転レベル4の実用を解禁しています。
自動運転レベル4の市販車
2023年12月現在、市販車で自動運転レベル4が実装されている車はまだありません。
レベル4相当の運転装置は高価で販売価格が高騰しやすいこと、輸送・送迎サービス向けの車両から段階的に導入する方針であることから市販化にはまだ時間がかかると予想されます。
自動運転レベル5:「完全運転自動化」
自動運転レベル5についてご紹介します。ポイントは「完全自動化」です。ルートやエリア、交通状況を限定しない「自動運転レベル4」が自動運転レベル5の目指すところです。
自動運転レベル5の定義・機能
自動運転レベル5の定義は完全自動運転車です。
人が運転操作はもちろん、周囲の状況を見る必要もありません。また、レベル5はルートやエリアを特定しません。目的地を決めたら運行ルートは車任せとなります。特定のエリア内でしか動けないといったこともありません。
事故や工事、悪天候による突然の通行止めにも車が自動で迂回路を探し、見つからなければ安全な場所を見つけて停止するなどの措置を取ります。
公道を走るうえで必要なことをすべてシステムが行い、安全かつ遅れを最小限に抑えて人や物を目的地まで輸送する。それが自動運転レベル5のゴールです。
自動運転レベルの今後の動向は?
ご紹介した内容を加味すると、今後の自動運転は利用目的によって目指すレベルと課題が異なります。
自家用車向けにメーカーが目指すのはレベル2の標準化とレベル3の普及と予想できます。
レベル2を可能にする装置を標準装備として運転をフォローしつつ、レベル3によって運転者の長時間・長距離ドライブの負担軽減を目指すのが現実的です。また、高速道路でのシステム主体の運転が当面の目標として考えられるでしょう。
商用車では、レベル4の実用化を目指す動きが今後も続くと予想されます。
トラック、バス、タクシーなどの輸送業界における人員不足は今後も続く可能性が高いです。これは労働人口が増えないのでどうしても避けられません。
レベル4が実用化すれば、空港や大規模な商業施設(ディズニーリゾートやUSJなど)内の客の輸送を無人で行えます。
人を必要としない自動運転を企業が人件費以上にコストをかけず導入できれば、衰退の一途をたどる輸送業務の助けとなるでしょう。
また、自動運転技術において、日本は他国より大きく後れを取っています。米国や中国など、先を行く海外の技術を積極的に導入することも、早期の自動運転実用化に向けて検討が必要でしょう。
自動運転によって運送業界は変わる?
自動運転によって運送業界は変わるでしょうか。
結論から言うと、自動運転で運送業界が変わる可能性はあります。しかし、変わるまでには時間とお金が必要です。
運送業界にはレベル4以上の自動運転が必須です。運送業界の悩みは人手不足。人手をかけずに業務改善できなければ導入する価値がありません。
自動運転はまだレベル3すら実施できているとはいえない段階です。そのため、レベル4実用化に必要な自動運転技術の開発にはまだ時間がかかるでしょう。
また、コストがかかり過ぎてもいけません。コストをかけられるなら、現在働いている従業員の給与を上げればよいだけです。一時的にコストがかかっても、長期的視点で費用が回収できれば問題ありませんが、その段階に到達するにもまだ時間がかかると考えられます。
さらに、自動運転に安全性が担保されないと運送業界への導入は不可能です。ここでいう安全性とは、交通事故以外に荷物の破損や運送の遅延への対応なども含まれます。「自動運転車はこのような性質がある」など、ドライバーへの安全運転教育も必要になるはずです。
以上から、自動運転はあくまで運送業界活性化の一手段になり得ますが、実用化にはまだ多くの時間がかかるでしょう。
まとめ
運送業界への自動運転導入は将来的には行われるでしょうが、サービス提供に役立つレベルになるまではまだ時間がかかります。その間、業務改善に向けて私たちは今できることを積み上げていかなければなりません。
いろいろある改善策の中で効果が高いのは、毎日必ずやらなければならない作業の効率化です。
- 車両の日常点検
- 業務日報の作成
- ドライバーの健康管理・アルコールチェック
- 乗務前後の点呼
上記のような毎日の作業。
もし、まとめて実行・管理できるツールが自社にあれば便利ではないでしょうか。
そこで導入を検討していただきたいのがテレニシの「IT点呼キーパー」です。
- 営業所ごとにデータを作成
- 作成データは一元管理が可能
- データはクラウド管理によっていつでもどこでも確認可能
- 点呼記録の自動保存機能で点呼の不正を排除
日常業務をIT点呼キーパーひとつに凝縮できるのに、導入・管理費用は安価なのが特徴です。
さらに、21日間の無料体験デモで工数の削減具合と製品の操作感を知ったうえで導入できます。
こうして導入までの敷居を徹底的に低くした結果、IT点呼キーパーは2024年4月末時点で2,100社・6,800を超える営業拠点で導入いただいております。
ご相談内容に応じて担当者が最適なプランを無料でご提案いたします。まずはお気軽にご相談ください。
【出典】
自動運転車両の呼称|国土交通省(参照2024-06-25)
自動運転のレベル分けについて|国土交通省(参照2024-06-25)
自動運転の実現に向けた動向について|国土交通省(参照2024-06-25)
事業者間の遠隔点呼の先行実施要領について|公益社団法人全日本トラック協会(参照2024-06-25)
自動運転車の世界市場を調査|富士経済グループ(参照2024-06-25)
自動運転とは?(2024年版)レベル別の開発状況・業界動向まとめ|自動運転ラボ(参照2024-06-25)
自動運転レベルとは?定義や実用化状況は?(2024年最新版)|自動運転ラボ(参照2024-06-25)
手放し運転(ハンズオフ)が可能な車種一覧(2024年最新版)|自動運転ラボ(参照2024-06-25)
自動運転車の市場調査・レポート一覧(2024年最新版)|自動運転ラボ(参照2024-06-25)
人手不足に終止符!?物流業界歓迎の「自動運転レベル4」解禁へ|自動運転ラボ(参照2024-06-25)
迫りくる2024年問題、カギを握る「自動運転化」|自動運転ラボ(参照2024-06-25)
自動運転でトラックドライバーはどうなる? 次の職が見当たらない“厳しい未来”とは|Seizo Trend(参照2024-06-25)
自動運転トラックの実現で、運送業界はどう変わる?|ドラEVER(参照2024-06-25)
物流ニュースのLNEWS|2026年に自動運転トラックで幹線輸送の自動化目指す(参照2024-06-25)
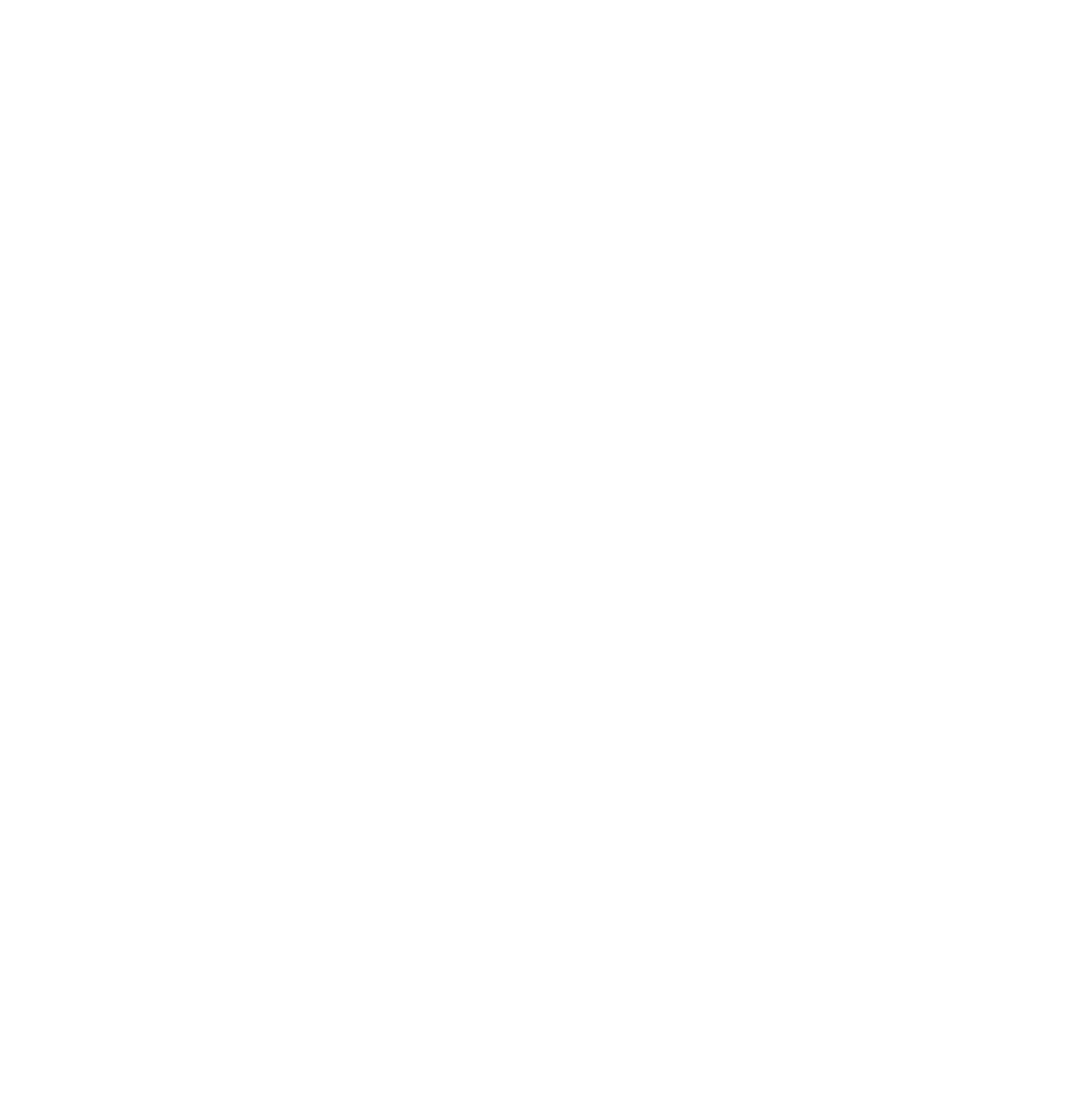 この記事をシェアする
この記事をシェアする
人気のコラム 月間ランキング
-
1

-
法改正・規制
正しい点呼で違反を防ごう~運送業における正しい点呼とは~
自動車運送業における点呼業務は、貨物自動車運送事業輸送安全規則の第7条で実施が義務付けられています。基本は対面で実施しなければなりませんが、近年はICT技術の高度化によって対面点呼や電話点呼に代わる「遠隔点呼」が実施できるようになりました。法令で義務付けられている一方で、守っていない運送事業者が存在するのも事実です。国土交通省近畿運輸局が令和6年度7月26日に公表した、令和5年度「自動車運送事業者に対する監査と処分結果」の内容分析結果によると、運送事業者の最も多い違反は点呼だと判明しています。そこで今回は、あらためて正しい点呼の方法や点呼に関する違反時の罰則をご紹介します。点呼業務を効率化させるための方法もご紹介しているので、ぜひ最後までご覧ください。
-
2

-
法改正・規制
遠隔点呼とは?遠隔点呼の申請ルールが令和5年4月から変更
2022年(令和4年)4月より開始した「遠隔点呼」ですが、2023年(令和5年)3月31日以降ちょっとした変化があったことをご存じでしょうか。これに伴い、遠隔点呼の要件や申請方法が変更されました。そこで本記事では遠隔点呼の定義をおさらいし、2023年4月1日以降の申請方法について解説しますのでトラック事業者の方は参考にしてください。
-
3

-
法改正・規制
遠隔点呼とIT点呼の違いをカンタンまとめ
令和4(2022)年4月より、「遠隔点呼実施要領」に基づいた遠隔点呼の申請が開始されています。すでに実施されている「IT点呼」と新たに申請できるようになった「遠隔点呼」には、どのような違いがあるのでしょうか?対面点呼と比べると遠隔点呼とIT点呼は同義に見えることから、どうしても混乱しがちです。本記事では遠隔点呼とIT点呼の違いをまとめましたので、ぜひ参考にしてください。
-
4

-
法改正・規制
軽貨物における点呼とは?軽貨物運送事業の登録に必要な要件も解説
新型コロナウイルス感染症の流行後、通販や宅配サービスの利用が急増し、狭い住宅地でも荷物をスムーズに運べる軽貨物運送の需要が高まっています。しかし、軽貨物運送事業を始めるにはさまざまな規定があり、「何から手をつけてよいかわからない」と悩んでいる方も多いのではないでしょうか。そこで今回は、軽貨物運送の基本情報や登録に必要な要件、そして点呼についてわかりやすく解説します。軽貨物車を使った事業を始めたい方はもちろん、すでに事業を営んでいる方もぜひ最後までご覧いただき、顧客の多様なニーズに対応できる事業展開にお役立てください。
-
5

-
法改正・規制
点呼記録簿とは?点呼を実施するタイミングや記載事項について解説
自社のドライバーだけでなく、他のドライバーや歩行者などの安全確保のために法律で義務付けられている点呼。平成23年5月1日より、運送事業者がドライバーに対して実施することとされている点呼において、ドライバーの酒気帯びの有無を確認する際にアルコール検知器を使用することとなりました。そういった経緯もあり、点呼内容の記録や保管は複雑で、運用に不安を抱えている管理者の方も多いのではないでしょうか。そこで本記事では、事業用自動車(緑ナンバー)運送業者向けに点呼記録簿に関するさまざまな情報をご紹介します。点呼に関する不安がなくなり、管理が楽になるツールもご紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。