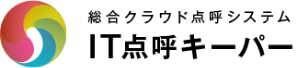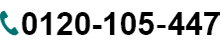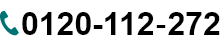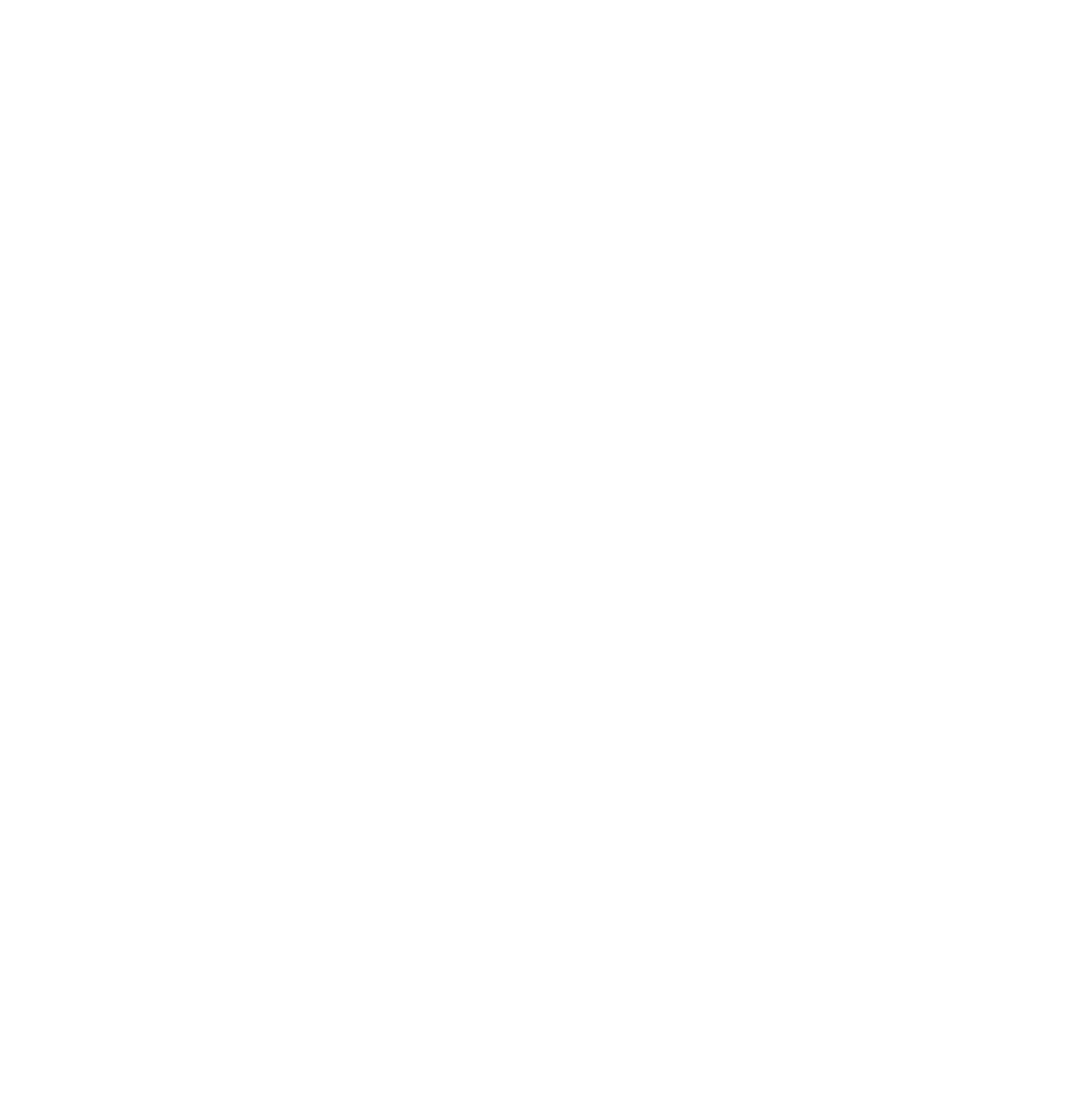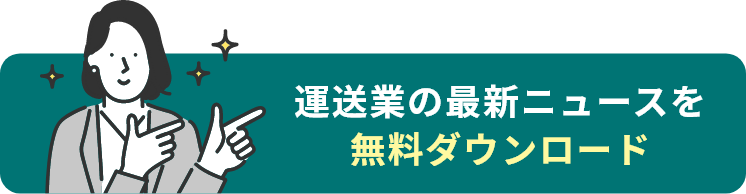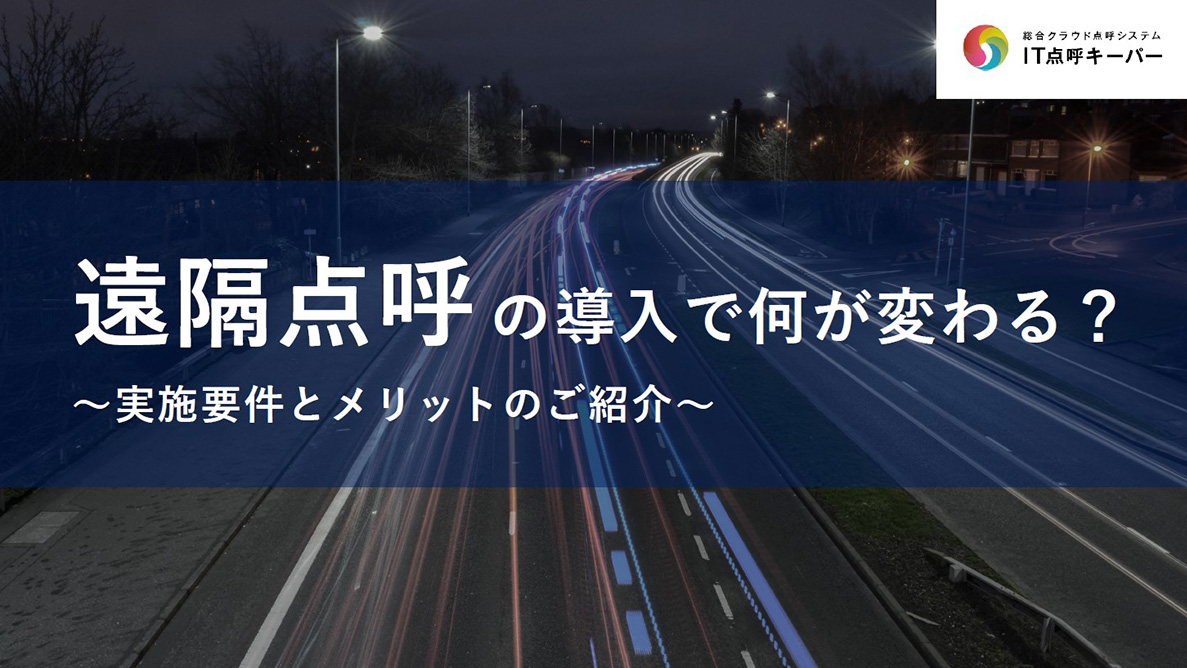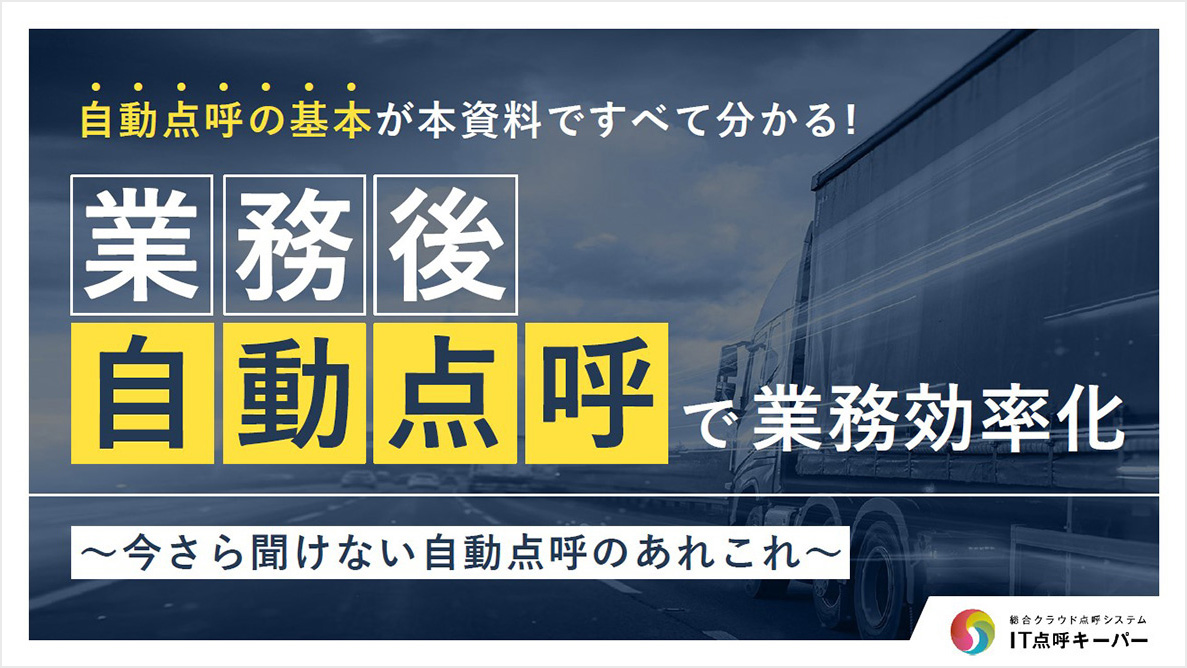クラウドサービスのメリット
クラウドサービスを導入することで、様々な面でメリットが生まれます。
今回は具体的な5つのメリットについてご説明いたします。
① サーバーやソフトウェアを購入する必要がない
クラウドサービスは、サーバーやソフトウェアなどのサービスがネットワーク経由で提供されるため、利用者側がサービスを所有・管理するのではなく、必要な機能を必要なときに利用する仕組みです。またクラウドの場合、初期はスペックを抑えて導入し、後から必要な分だけ拡張していくことが可能です。サービスの購入費用について悩むことはなく、無駄が発生しません。
② スピーディーに導入することができ、システム構築の時間を削減
クラウドサーバーはアカウントを発行するだけで導入でき、およそ30分程度で初期設定を完了し利用を始められるものが多いです。自社で用意したサーバーへソフトウェアをインストールし、利用するタイプのサーバーを構築する場合、ネットワーク構築のために導入決定から利用開始まで半年から1年ほどかかります。
そのため早期に利用を開始したい企業やスモールスタートで導入したい企業は、クラウドは有効活用できると言えるでしょう。
③ インフラ管理・運用・コスト等の負担削減
クラウドサーバーを利用するメリットとして最も大きいのが、自社内でのサーバー管理・運用の負担を軽減することができると言う点です。
インフラ管理専門の担当者が社内にいる場合、社内サーバーが不要なので負担を減らすことができます。また担当者や専任者がいない場合でも、サーバー提供事業者に管理・運用を任せて、事業やサービスの構築・運営に集中することができます。
さらにクラウドサーバーの料金体系は、使用した利用時間やデータ量によって課金される従量課金制のため、初期コストだけでなく、毎月の利用料を削減できます。
④ メンテナンス不要
自分のパソコンやハードウェアにインストールやデータを保存している場合、定期的なメンテナンス作業が発生します。しかし、クラウドサービスは運営元が管理及びメンテナンス作業を行なっており、常に最新の状態で利用できます。もちろん利用者側によるメンテナンスは不要です。
⑤ バックアップ・BCP対策ができる
BCP対策においても、クラウドサーバーは有効です。BCP対策(Business Continuity Plan:事業継続計画)とは、企業が自然災害やテロ被害などの緊急事態に備えて、被害を最小限に抑え、事業を継続させるための対策のことをいいます。
クラウドサーバーは国内外の堅牢なデータセンターにバックアップし管理されています。地震対策として耐震・免震構造のビルに格納していたり、停電などでサーバー稼働が止まらないように副電源や自家発電装置を取り入れていたりします。
クラウドなのでどこからでも安全に接続できるため、様々なリスク対策に有効です。