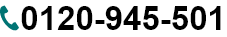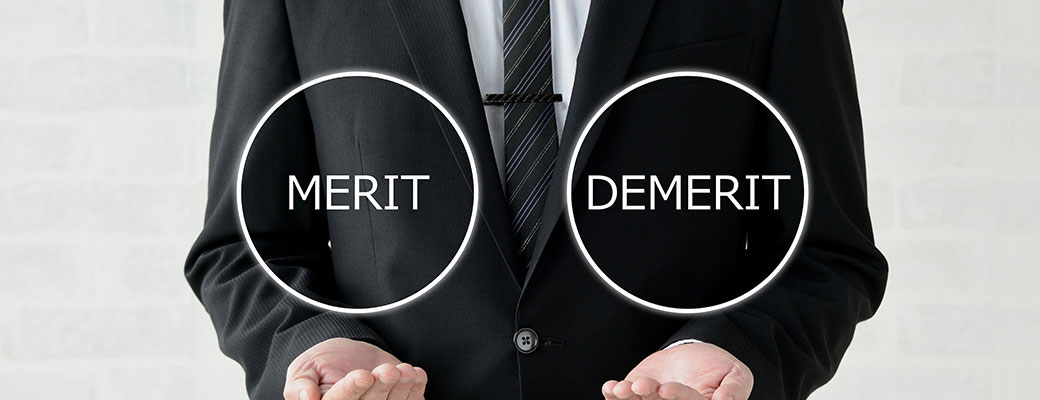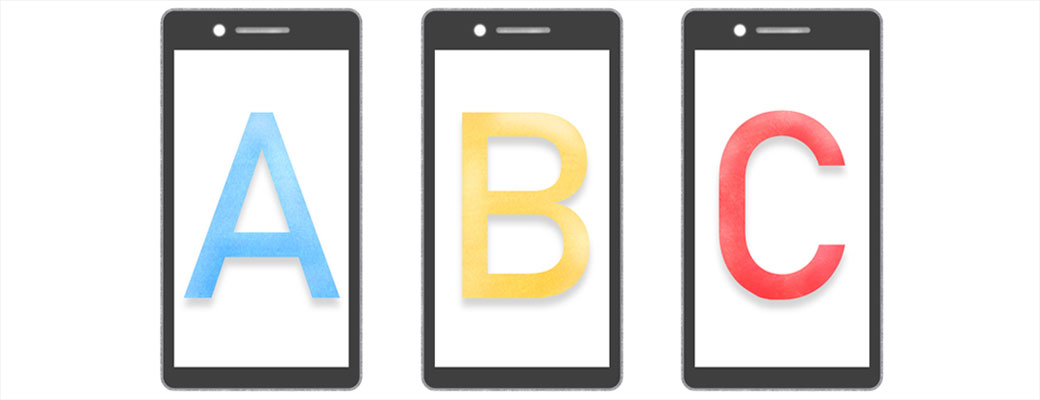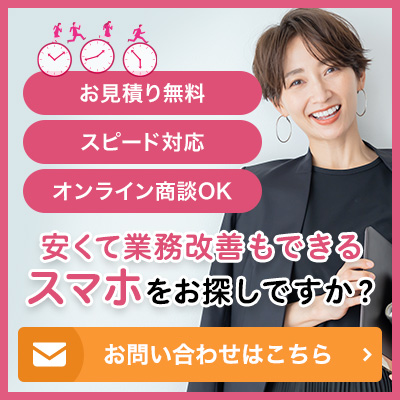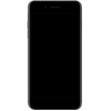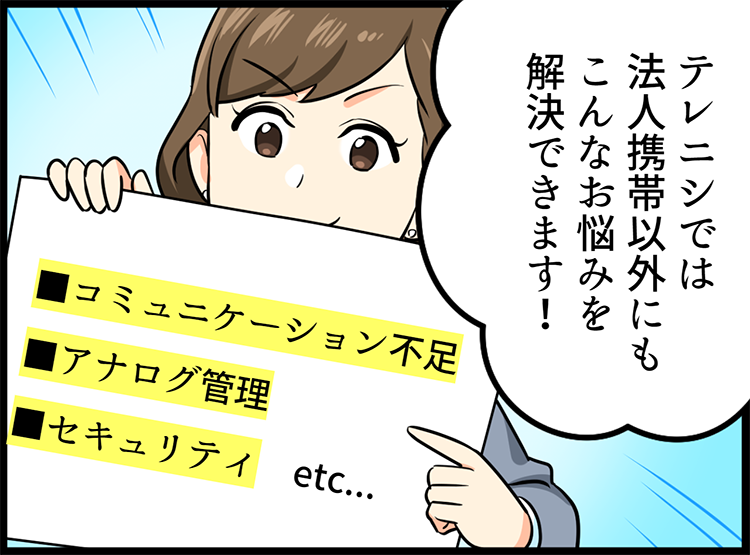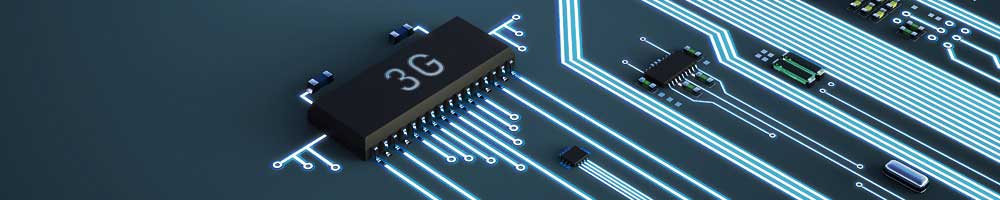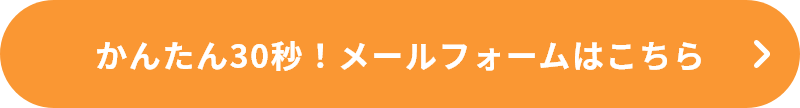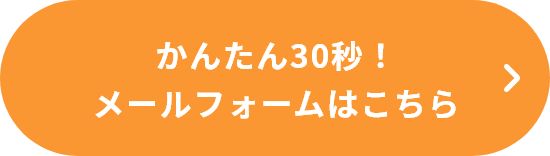1.法人携帯の契約に必要な書類
法人携帯の契約は「携帯電話不正利用防止法」の定めにより、契約シーンごとに所定の書類が必要です。
この項目では、ソフトバンクで法人契約する場合に必要な書類をシーン別にご紹介します。
新規契約時に必要な書類
新規契約時に必要な書類は下記の4点です。
①法人確認書類
下記のいずれか1点、発行日から3か月以内のもの
- 登記簿謄本
- 現在(履歴)事項証明書
- 印鑑証明書
➁ご担当者様の本人確認書類
下記のいずれか1点が必要になります。
- 運転免許証
- パスポート
- マイナンバーカード
③ご担当者様の名刺もしくは社員証
④法人印
口座振替の場合は、金融機関お届け印と通帳またはキャッシュカード。
丸印、角印どちらでも可
機種変更するときに必要な書類
すでに法人契約していて機種変更する場合は、基本ソフトバンクショップにて手続きを行います。手続きに必要な書類は以下のとおりです。
- ご担当者様の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- ご担当者様の在籍確認書類(社員証、名刺など)
- ご利用中の携帯電話機とUSIMカード
- 法人印(分割払いで購入の場合)
弊社では、ソフトバンクショップに行かなくても、諸々のお手続きをサポートいたしますので、ご検討中の方はお気軽にご相談ください。
乗り換えるときに必要な書類
法人携帯のキャリアを乗り換えるときに必要な書類は、新規契約と同じです。加えて、電話番号を引き継ぎたい場合は、乗り換え前のキャリアで「MNP予約番号」を発行します。
左右にスライドすると表を見ることができます
| Webサイト | 店舗 | 電話 | |
|---|---|---|---|
| ドコモ | My docomo 受付:24時間 |
各店舗の営業時間内 | 151 (ドコモ携帯から無料) 0120-800-000 (一般電話から) 受付:9~20時 |
| au | My au 受付:24時間 |
0077-75470 (au携帯・一般電話共通、無料) 受付:9~20時 |
|
| ソフトバンク | My SoftBank 受付:24時間 |
*5533 (ソフトバンク携帯から、無料) 0800‐100-5533 (一般電話から無料) 受付:9~20時 |
|
| 楽天モバイル | my 楽天モバイル 受付:24時間 |
- | - |
契約内容を変更するときに必要な書類
ソフトバンクで法人契約したプランやオプションの変更手続きに必要な書類は、以下のとおりです。
①ご担当者様の本人確認書類
下記のいずれか1点が必要になります。
- 運転免許証
- パスポート
- マイナンバーカード
➁ご担当者様の在籍確認書類(名刺、社員証など)
③法人印(角印、丸印、ご担当者様のサイン)
ただし、機種変更などの手続きで携帯電話機を割賦購入契約または個別信用購入あっせん契約でご購入の場合は法人印が必要
解約するときに必要な書類
ソフトバンクでの法人契約を解約するときに必要な書類は以下のとおりです。
①ご担当者様の本人確認書類
下記のいずれか1点が必要になります。
- 運転免許証
- パスポート
- マイナンバーカード