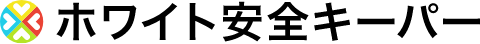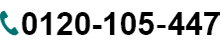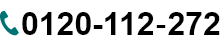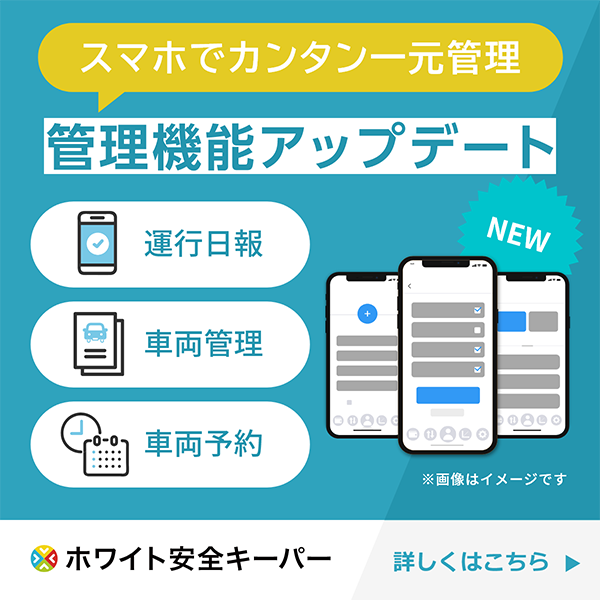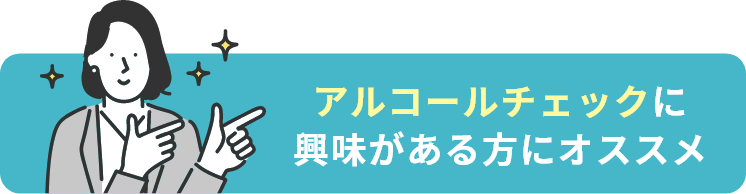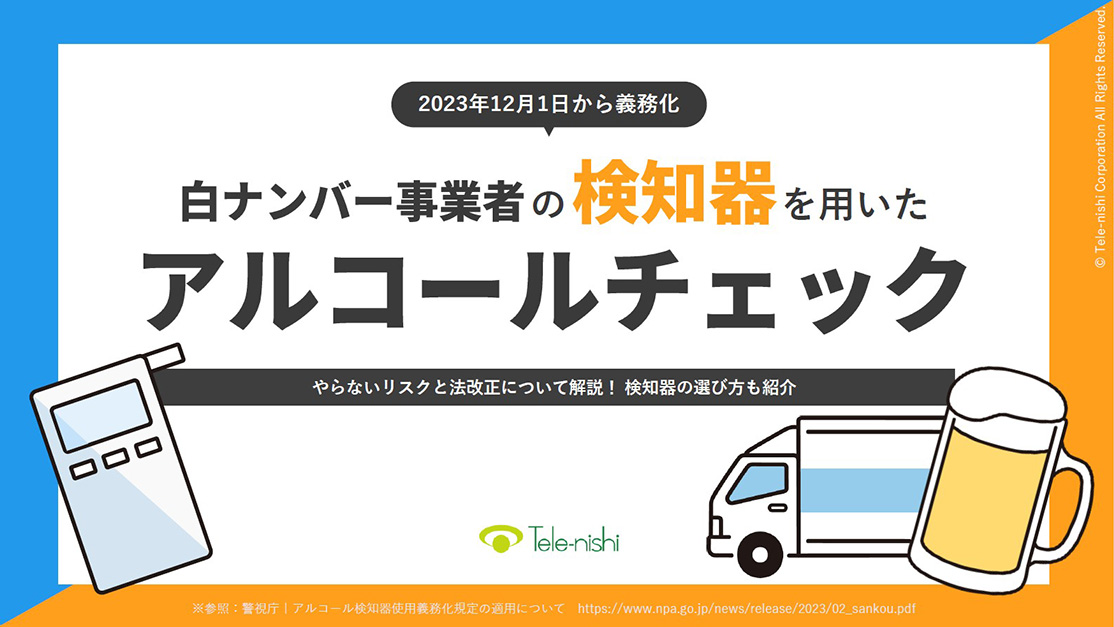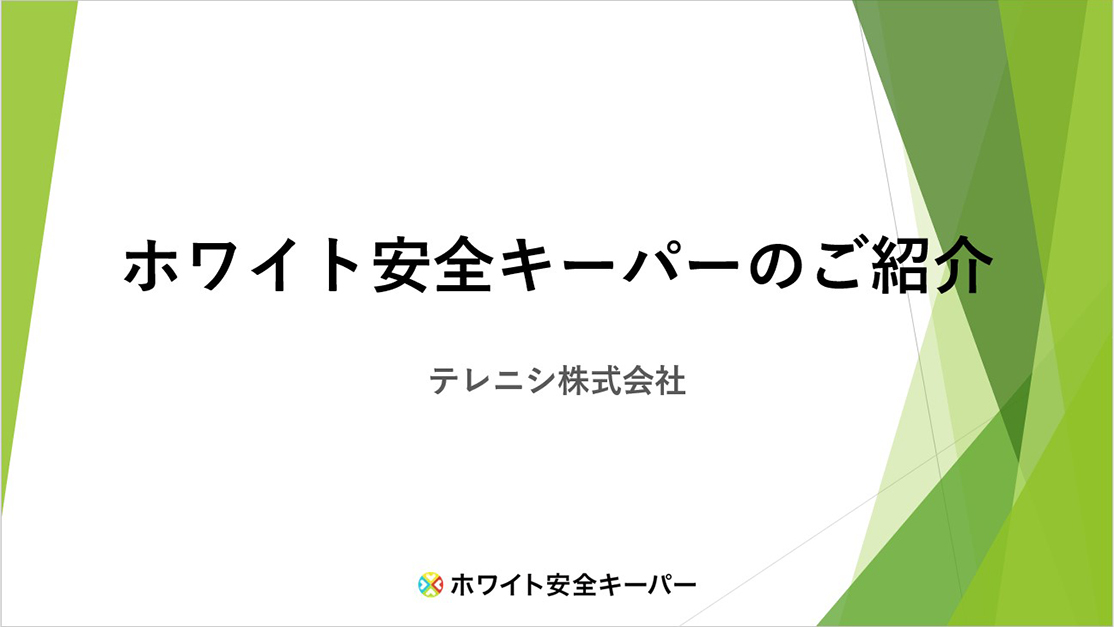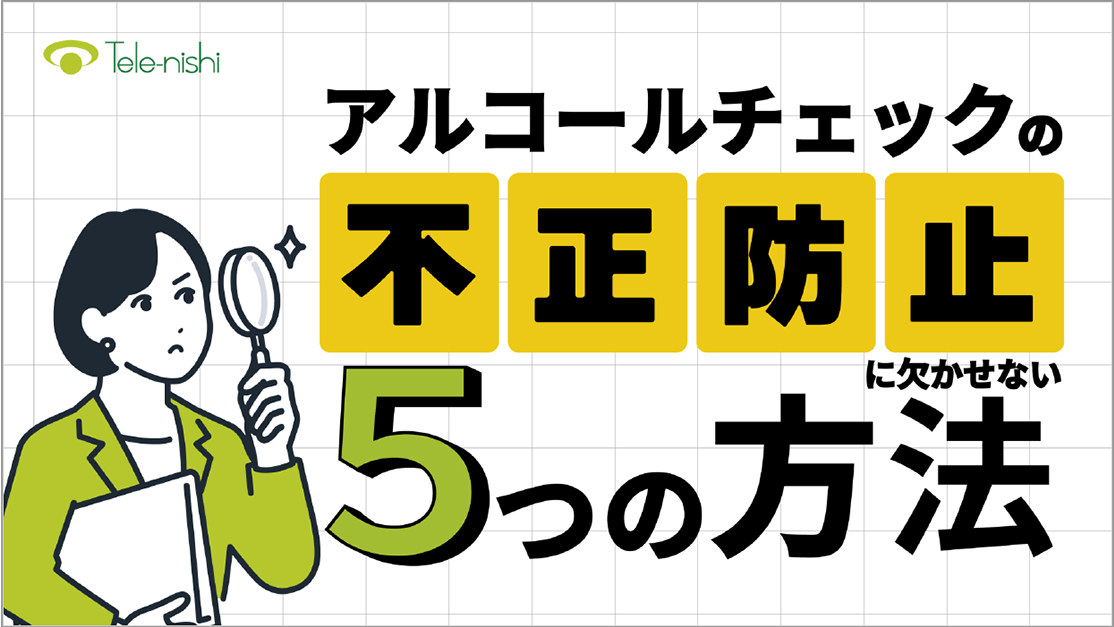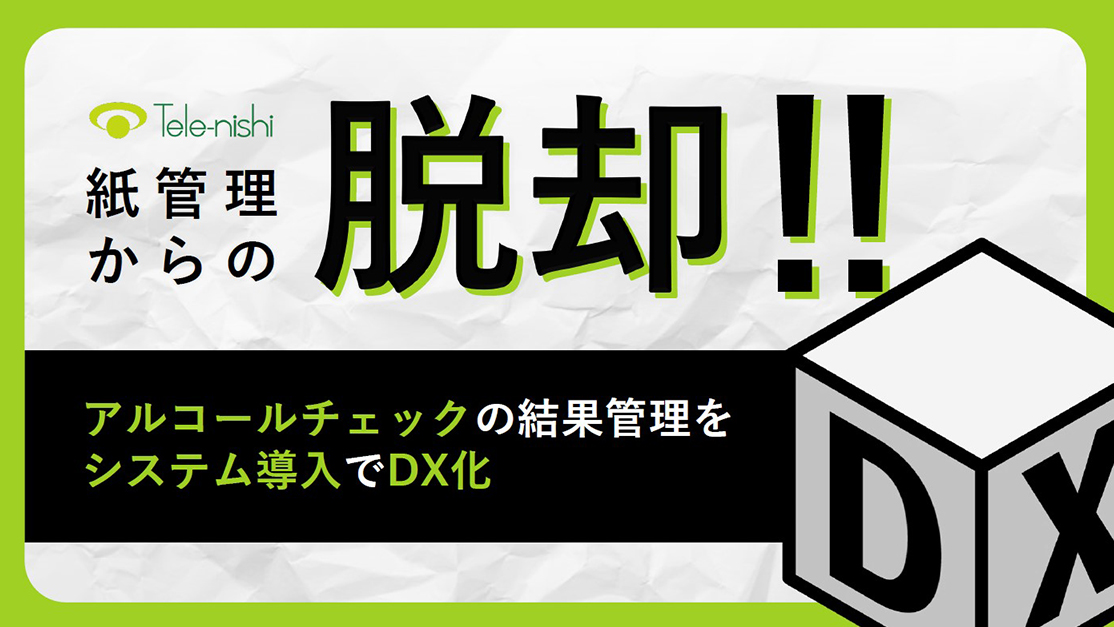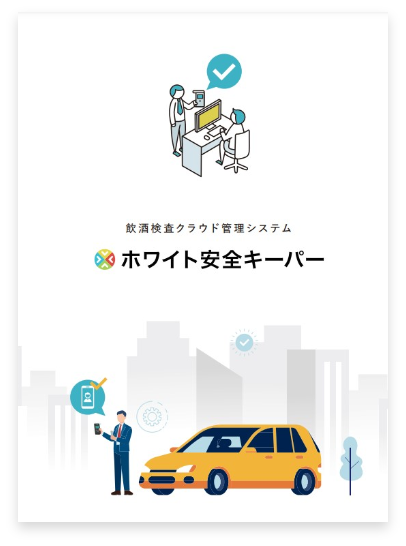1.白ナンバーのアルコールチェック義務化が2022年4月より開始
白ナンバー事業者向けのアルコールチェック義務化は、次のとおり2022年4月・2022年10月※・2023年12月の3段階に分けて施行されました。
2022年4月時点では、社用車の運転前・運転後にアルコールチェックを実施することが義務付けられましたが、アルコールチェッカー(以下アルコール検知器)を保有する必要はありませんでした。
2022年10月には、アルコールチェックを実施する時にはアルコール検知器を使用することが義務付けられました。しかし、世界的な半導体不足の影響により十分な数のアルコール検知器が市場に流通する見通しが立っていなかったため、アルコール検知器の義務化は無期延期となりました。
その後、2023年6月に警察庁より「2023年12月1日より施行予定」としてパブリックコメント※の募集が開始されました。パブリックコメントは「道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令案」という掲題で2023年7月まで募集が行われ、同年8月に提出された意見が全て公示されました。
【出典】:e-Gov法令検索|「道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令案」に対する意見の募集結果について
そして2023年12月1日、ついにアルコール検知器を使用したアルコールチェックが義務付けられました。
| 段階 | 改正の概要 |
|---|---|
| 2022年4月1日施行 |
|
| 2022年10月1日施行 |
※2022年9月時点:アルコール検知器を用いた酒気帯び確認の義務化は延期と警視庁より発表 |
| 2023年12月1日施行 |
|
もともとタクシーやトラックなど有償で旅客や貨物を運ぶ運送事業者(緑ナンバー)を対象に、アルコールチェック義務化は2011年から施行されていました。そのため緑ナンバー事業者は、事業所用自動車の安全運行を管理する「運行管理者」を配置することが義務付けられており、点呼時のアルコールチェックは運行管理者が実施しています。
今回、緑ナンバーに加えて白ナンバー事業者もアルコールチェック義務化の対象となったきっかけは、2021年6月に千葉県八街市で発生した飲酒運転による交通事故(八街児童5人死傷事故)でした。
この死亡事故を受けて、2021年9月3日に道路交通法施行規則の改正案が告示され、その後2021年11月10日に安全運転管理者業務の拡充についての通達が警察庁より発せられたのです。