
運転日報とは
運転日報とは、業務で自動車を使用した場合に運転者の氏名、乗務開始・終了地点や日時、走行距離などを記録する日誌のことです。とくに「トラックによる運送など一般貨物自動車運送事業を営む企業」と「業務における使用車両が一定台数を超える企業」については、法律で運転日報の作成・保管が義務付けられています。
【365日24時間対応】サポート窓口お気軽にお問い合わせください

運転日報は、企業活動において自動車を使用する際に必須とされる記録です。実際に運送業や、社有車で商品の配達などに活用している企業では、社内で運転日報の作成が義務付けられているでしょう。
ところでなぜ運転日報を作成し保管する必要があるのか、その理由をご存じでしょうか?
本記事では、運転日報を義務付ける法律・記載事項などの基礎知識・業務フローについてわかりやすく解説します。運転日報の活用方法についてもご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

運転日報とは、業務で自動車を使用した場合に運転者の氏名、乗務開始・終了地点や日時、走行距離などを記録する日誌のことです。とくに「トラックによる運送など一般貨物自動車運送事業を営む企業」と「業務における使用車両が一定台数を超える企業」については、法律で運転日報の作成・保管が義務付けられています。

そんな運転日報ですが、どのような企業が記録と保存を義務付けられているのでしょうか?
貨物運送業を営む企業では「貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条」により、運転日報の記録と保存が義務付けられています。
運送業では、事業用自動車の安全運行を管理する「運行管理者」の配置が義務付けられています。
一定数以上の車両を保有する営業所ごとに、車両台数に応じた人数を配置しなければなりません。
この運行管理者の業務の1つが「乗務記録の管理」です。
乗務記録の管理は、トラックドライバーの乗務状況を正しく把握し確認することを目的として行われます。
日々の安全運行の確保や運行管理上の資料として活用するために実施されている点がポイントです。
安全運行の確保により、次のような効果が期待できます。
なお運転日報の保存期間は、1年間と定められています。
ただし改正労働基準法第109条「記録の保存」においては、労働関係に関する重要な書類は「5年間」保存することになっています(改正前は3年間)。この中で労働者名簿が挙げられており、運転日報にはドライバーの氏名が情報として含まれることから、運転日報も5年間保存すべきという考え方もあります。
企業が一定数の社用車や営業車で営業活動を行っている場合は、道路交通法施行規則第9条の8により「安全運転管理者」等の選任が義務付けられています。
安全運転管理者等の選任が必要になる車両台数は、次のとおりです。
この安全運転管理者の主な業務の1つとして、運転日報の記録が義務付けられています(道路交通法施行規則第9条の10の8項)。具体的には、運転状況を把握するために必要な事項を記録する書類を備え付けておき、運転を終了した従業員に記入させることです。
なお運転日報の保管期間は、1年間と定められています。
2021年8月に千葉県で飲酒運転による交通死亡事故が発生したことから、道路交通法施行規則が改正されました。
そのため2022年4月から安全運転管理者の業務が拡充されているので、運転日報についても見直すようにしましょう。
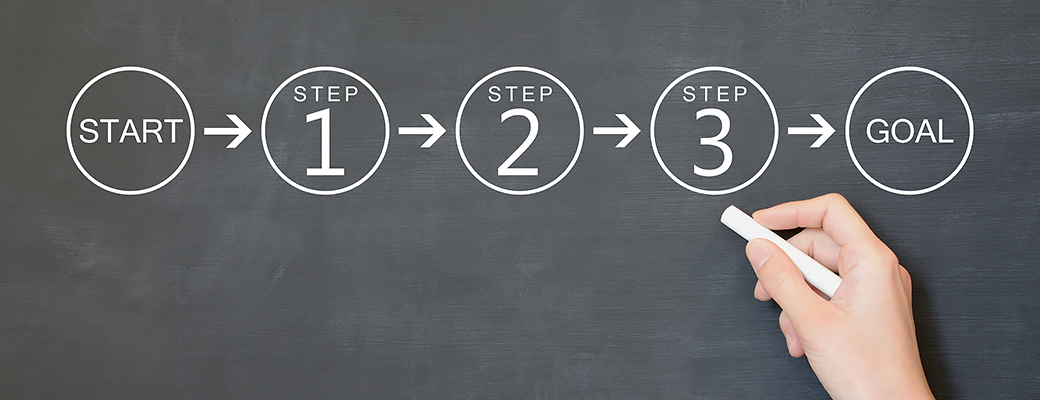
運転日報の運用業務のフローは、以下の3ステップです。
1つずつ詳細をご紹介します。
運転日報の記入はドライバーの仕事です。運転業務の前後に必要項目をドライバー自身に記入してもらいます。
ただし、ここで注意したいのが、ドライバーに丁寧に記入してもらうよう、あらかじめ伝えておくことです。
運転前であれば疲れていないので自然と丁寧に記入できますが、運転後は疲れている状態で日報の記入をしてもらうことになります。緊張から解放されてホッとしたのも束の間、慣れない事務作業を任されるのは面倒と感じるドライバーもいるはずです。
しかし、日報を雑に書かれ、読み取れない状態で提出されてしまった場合、当然ですが書き直してもらわなければなりません。これはお互いに無駄な工数が発生するだけなので、避けたいところです。
そのため、書き直しを頼むことがないよう、事前に丁寧な記入をお願いしましょう。マニュアルを用意し、記入例を共有しておくといった具体的な注意喚起も行っておくと効果的です。
運転日報は、運行管理者又は安全運転管理者へ提出し、運行管理者又は安全運転管理者がチェックするのが基本です。
記入漏れ、明らかな記載間違い、判別しづらい文字などを確認し、必要に応じてドライバーへ聞き取りや修正依頼を行います。
運転日報は、緑ナンバー車両、白ナンバー車両を扱ういずれの事業者も1年間の保存義務があります。
しかし、労働に関する重要な書類には保存の義務があり、労働基準法の改正により保存期間は3年から5年に延長されます。ただし、経過措置として当面の間は3年が適用されます。
よって、運転日報も最低3年間、できれば5年間保存しておくのが望ましいです。

ここでは現場の業務フローに役立てられるように、運転日報の記載項目についてご紹介します。
運送業を営む企業の乗務記録(運転日報)における主な必要項目は、次のとおりです。(貨物自動車運送事業輸送安全規則(第八条)
社用車とは業務に使用する車を指します。会社所有の車両でない業務に利用するレンタカーや私有車も含みます。
社用車で営業活動をおこなっている企業の運転日報において、法令で規定されている必要項目は次のとおりです(道路交通法施行規則第9条の10の8項)。
【出典】:e-Gov法令検索|道路交通法施行規則(第九条の十)
運転日報に次のような記載事項も追加すれば、自社の車両管理や勤怠管理に役立ちますので参考にしてください。
社用車の役割は、企業によってさまざまです。幼稚園や介護サービスなどの送迎で利用する場合もあるでしょう。自社の業種特有の事情にそった記載内容を加えることも、ぜひ検討してみてください。
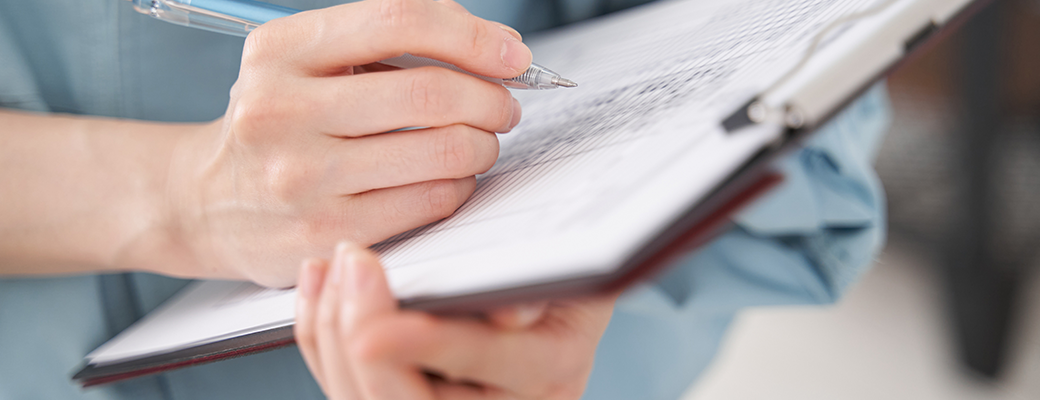
ここでは、運転日報の書き方と管理方法についてご紹介します。
運転日報には、「このように書いて保管しなさい」というルールはなく、必要な項目がすべて書かれてさえいれば、紙ベースでも電子データベースでも構いません。
しかし、長期保存やデータの取り扱いといった観点から考えると、電子データベースやクラウドシステムの導入をおすすめします。
とはいえ、紙ベースと電子データベース、それぞれに固有のメリットがあるため、事前に確認しておき、自社に合った方法で保管しましょう。
詳しくは、以下で解説します。
運転日報を紙で作成・保管するメリットは、以下の2つです。
運転日報を紙ベースで作成・保管すると、PCやソフトといった新たに導入しなければならないシステムなどにかかるコストを抑えられるため、初期費用を抑えられます。
フォーマットも一から手書きで用意する必要はありません。必要項目が記載できれば書式は自由です。出回っているフォーマットから使いやすそうなものをダウンロードし、印刷すればよいだけなので、費用は紙とインク代程度で済みます。
紙に印刷した運転日報をドライバーに渡せば、ドライバーはPCが使えなくても日報を作成できます。
ドライバーの高齢化により、PCに苦手意識を持つ人は少なくありません。自社のドライバーがPC操作を苦手としているのであれば、紙ベースの日報の方が抵抗感やストレスなく記入に応じてくれることでしょう。
PCでExcelやアプリなどを使い、日報を作成・保管するメリットは以下の3つです。
電子データで運転日報を作成・保管すると、データの集計や検索が容易になります。
手書きでは集計するのに電卓を使わなければなりませんが、電子データの場合Excelなどを使えば入力した数値を自動計算できるため、計算ミスも防ぐことが可能です。
検索機能を使えば、必要な情報を瞬時に閲覧できるため、情報探しに時間がかからなくなるといったメリットもあるでしょう。
紙ベースの運転日報は、ファイルに綴じてラックにしまう必要があるため、保管場所も必要です。
さらに、量が増えるほど過去のデータを調べるのに時間がかかり、業務効率が悪くなります。
一方、電子データベースで管理するとPC内にデータを保管できるうえに、クラウド上に保存していれば、どのパソコンからでも瞬時に閲覧が可能です。
電子データで管理すれば、当然ですが紙は不要になります。そのため、至るところで取り上げられるペーパーレス化を自社でも導入できるでしょう。
業務効率化、生産性向上などが期待できる点も考えると、ペーパーレス化ができる電子データベースでの管理は非常に便利かつ経済的といえます。

運転日報の作成や保管の義務を怠った場合の罰則はありません。
ただし、社用車で営業活動を行っている企業でなぜ作成・保管ができていないのかを調べた結果、業務を行うべき安全運転管理者の選任をしていない、選任したが届出をしていないことが原因であった場合は、それぞれの行為に対して罰則があります。
| 怠った義務の内容 | 罰則 |
|---|---|
| 安全運転管理者の未選任 | 50万円以下の罰金 |
| 安全運転管理者の未届け | 5万円以下の罰金 |
また、運送事業者においては、巡回指導で運転日報のチェックが行われます。
巡回指導は、実施状況によりA~Eの5段階で評価され、DまたはE評価を受けた場合に監査の対象となります。
そして、監査で悪質・重大な法令違反を起こした運送事業者には、「車両使用停止」「事業停止」「許可取消」などの行政処分が下されます。
運転日報の保管を怠り、巡回指導で焦らないためにも日々の保管をしっかり行いましょう。

一般的に、運転日報に記された情報を単なる記録として保存しているケースが多いのではないでしょうか。しかし積極的に情報を活用すれば、次のような業務改善につなげられるのでぜひ参考にしてください。
| 活用方法 | 業務改善のポイント |
|---|---|
| 燃費 |
|
| 車両点検 |
|
| 従業員の 労務管理業務 |
|
| 走行ルート |
|
2024年に時間外労働の上限規制(年720時間)が適用されると、トラックドライバーの働き方が変わります。そのため物流業界は、労務管理の徹底と一層の生産性向上といった対応に迫られています。運転日報をデジタル化して情報をデータとして活用できるようになれば、こういった問題を解決する一助となります。

すでに少し触れましたが、運転日報の作成・管理はシステムの導入がおすすめです。
ここでは、システム導入時の注意点やメリットについてご紹介します。
システム導入にあたって、従業員に2点注意してもらう必要があります。
1つ目は、「システム導入の目的を理解してもらう」ことです。システムの利用は、ドライバー側からすると「監視されている感」が強くなるためです。
便利な反面、ドライバーは「自由を奪われている」と感じるリスクがあるでしょう。そのため、以下のような、システム導入の目的を従業員に理解してもらう手間を惜しんではいけません。
2つ目は、「システムを使い慣れてもらう」ことです。ドライバーの中には、PCどころかスマホの扱いも苦手という人も一定数いることでしょう。比較的簡単な操作とはいえ、最初は戸惑うはずです。
最初の時点で面倒と思われてしまうと抵抗感がさらに強まってしまいます。図解を多く取り入れたマニュアルを用意しておくなど、とっつきにくい印象を与えない工夫をしましょう。
正しい作業を、すでに日常化している作業にくっつけてしまえば、習慣化へのハードルはより低くなります。
運転日報の作成にシステムを導入するメリットは、以下の2つです。
運転日報の自動作成システムを導入することで、日報の一部項目を自動入力してもらえます。
走行距離や時間、運行経路などの情報をドライブレコーダーの記録から引っ張り、日報へ自動入力してくれるのです。
そのような機能を利用することで、以下のようなメリットを得られます。
管理する側、される側双方の工数が減り、習慣化しやすくなることでしょう。
運転日報の作成にシステムを導入すると、データの連携・活用が容易になります。
先ほどご紹介した日報の自動作成も、ドライブレコーダーのデータを日報の作成に連携させて行っています。
システムを導入すると、データはクラウド上に保存されるケースがほとんどです。
会社に備え付けのPCだけでなく、管理者が持ち運ぶノートPCなどからもデータを確認・活用できるため、作業効率の向上も期待できます。
運転日報を作成する本来の目的は、安全な運行を確保することです。運転日報で集めたデータを活用すれば、業務効率化や生産性の向上、労務管理の徹底につながります。Excelへの入力や紙ベースの管理は導入コスト面での負担は非常に少ないものの、長期的にみれば人件費や保管スペースの確保といった費用負担が膨らむ場合があるため注意が必要です。
弊社の飲酒検査クラウド管理システム「ホワイト安全キーパー」は、アルコールチェック結果をCSVでダウンロードすることができるので、運転日報とアルコールチェック結果をまとめて管理したい方におすすめです。
「運転日報のデジタル化によって、自社が抱えている課題を解決できるのか?」
気になる事業者様は、ぜひお気軽に弊社までお問い合わせくださいませ。
【出典】
自動車運送事業の運行管理者になるには|国土交通省(参照2024-01-31)
運行管理者とは|公益財団法人運行管理者試験センター(参照2024-01-31)
運転日報(乗務記録)|公益社団法人長野県トラック協会(参照2024-01-31)
改正労働基準法等に関するQ&A|厚生労働省(参照2024-01-31)
トラック運送業界の2024年問題について|公益社団法人全日本トラック協会(参照2024-01-31)
エコドライブ普及・推進アクションプラン|環境省(参照2024-01-31)
自動車の燃費への影響等|内閣府(参照2024-01-31)
 この記事をシェアする
この記事をシェアする
1

仕事後の晩酌は1日の疲れを癒し、明日への活力源になる一方で、深酒がたたり翌日にお酒が残ってしまっては事業者としては困ってしまいます。プライベートでの飲酒は個人の自由。プロとして節制は必要でも強制的に禁止するわけにもいかず、対応に苦慮されている事業者の方もいらっしゃるでしょう。業務に支障をきたさない範囲で飲酒を許可する指導法はないものか?このようにお悩みの事業者や管理者向けに、当記事では以下の点について解説します。
2

「アルコール検知器での検査はごまかせる」このような話を聞いたことはありませんか。飲酒運転による悲惨な事故は、誰も得をしません。だからこそ、アルコール検知器を使って検査をすることは重要で、不正を防ぐことは大切です。そこで今回は、過去にあった不正事例とそれに対する防止策をご紹介します。さらに、さまざまな不正な手法を防げるツールもご紹介しますので、飲酒運転による事故撲滅を強化したい管理者の方はぜひ最後までご覧ください。
3

運転日報は、企業活動において自動車を使用する際に必須とされる記録です。実際に運送業や、社有車で商品の配達などに活用している企業では、社内で運転日報の作成が義務付けられているでしょう。ところでなぜ運転日報を作成し保管する必要があるのか、その理由をご存じでしょうか?本記事では、運転日報を義務付ける法律・記載事項などの基礎知識・業務フローについてわかりやすく解説します。運転日報の活用方法についてもご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
4

街で走っているトラックのナンバープレートを見ると、白いナンバーと緑のナンバーの2種類があると思いますが、皆様はこの違いについてご存知でしょうか?今回は運送業界でよく聞く白ナンバートラックとはどういう仕事・役割なのか、緑ナンバーとの違いとは何かを紹介したいと思います。
5

令和4年(2022年)4月より、改正道路交通法施行規則が順次施行され、アルコールチェックの義務化など安全運転管理者の業務が拡充しています。安全運転管理者になるためには資格要件が定められており、誰でもなれるわけではありません。また安全運転管理や交通安全教育等を行うにあたり、必要な知識を得られる法定講習を受講する必要があります。本記事では、安全運転管理者等およびその法定講習の概要や受講前に知っておきたい注意点について見ていきましょう。
 ホワイト安全キーパーをフォローする
ホワイト安全キーパーをフォローする