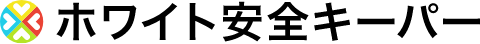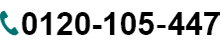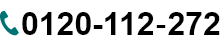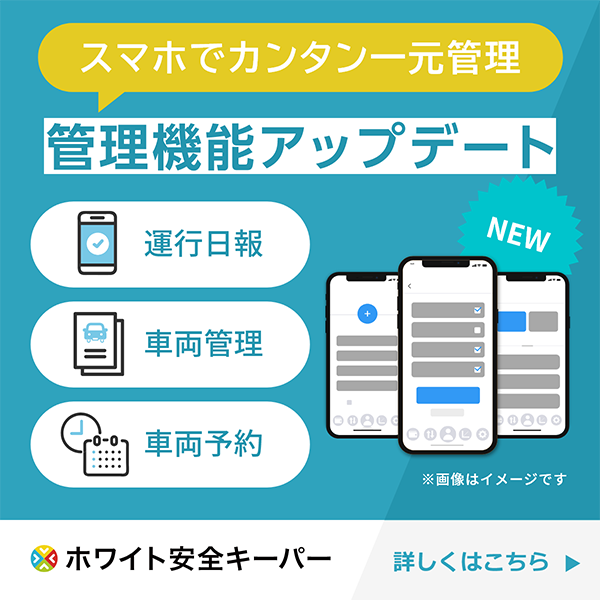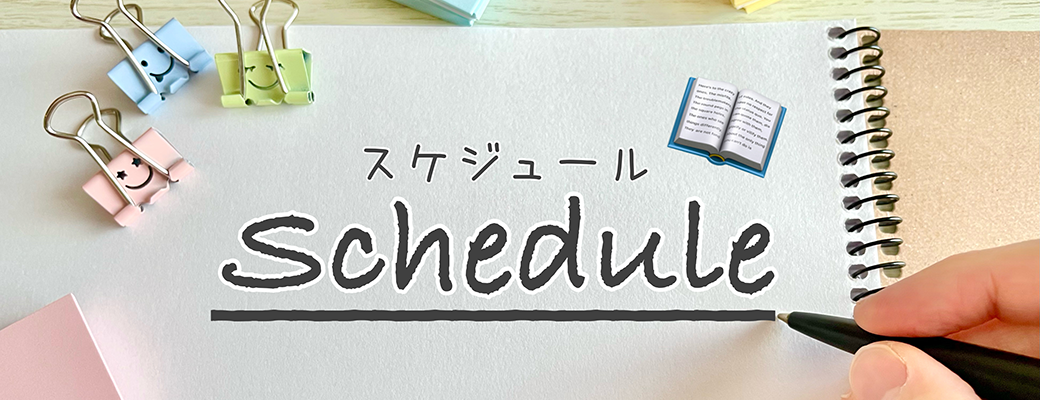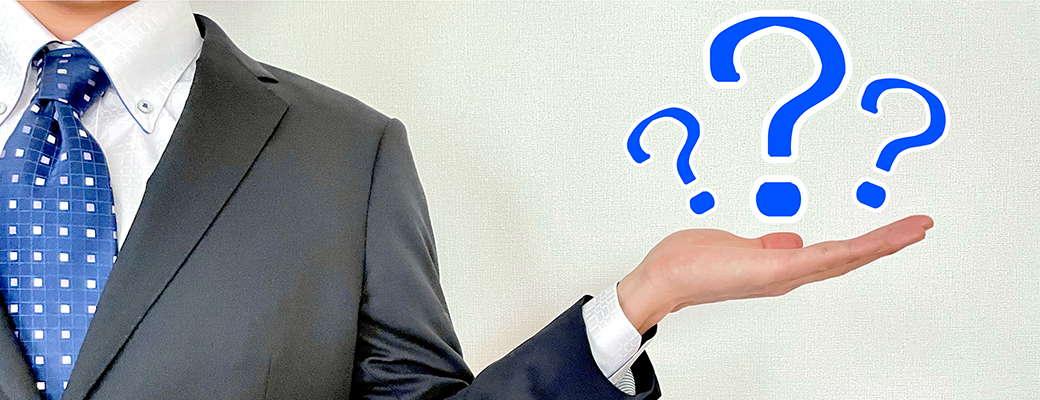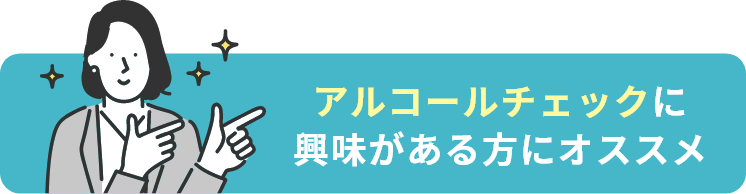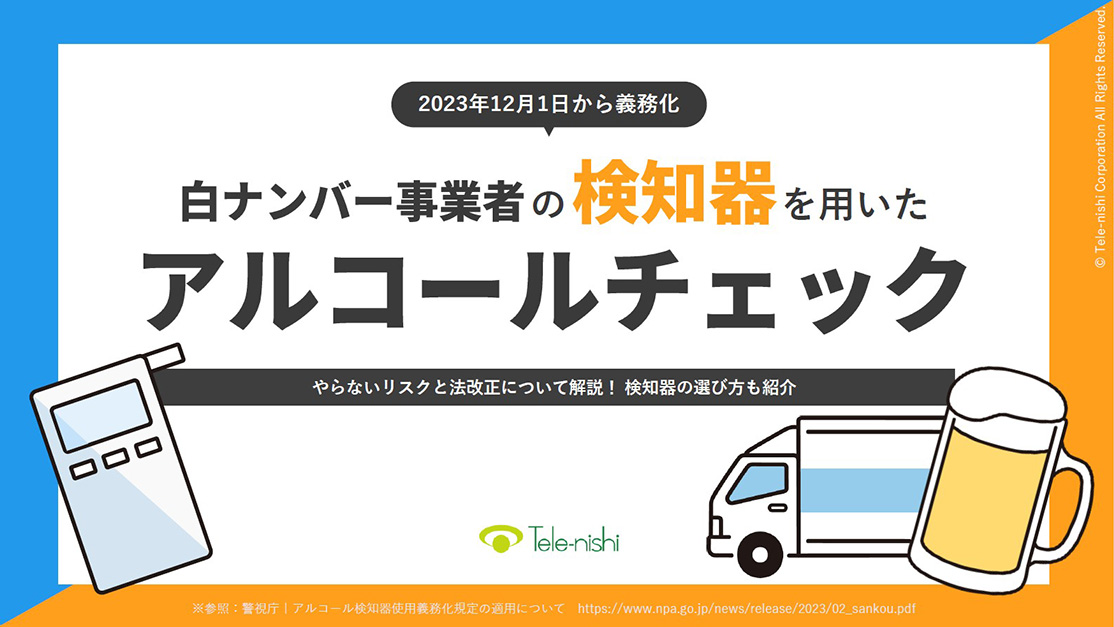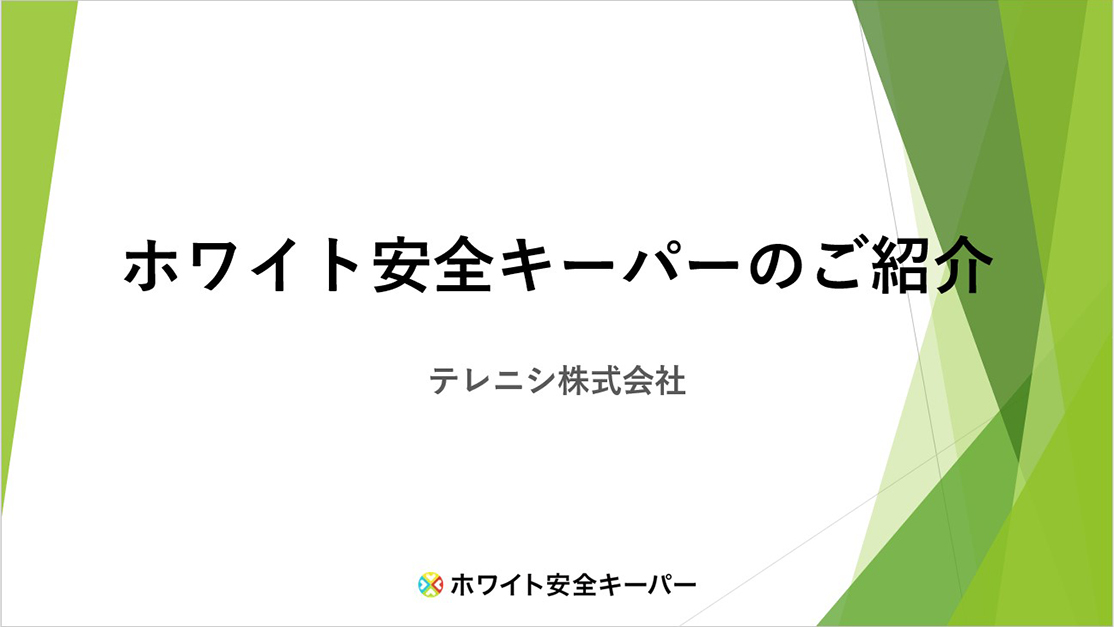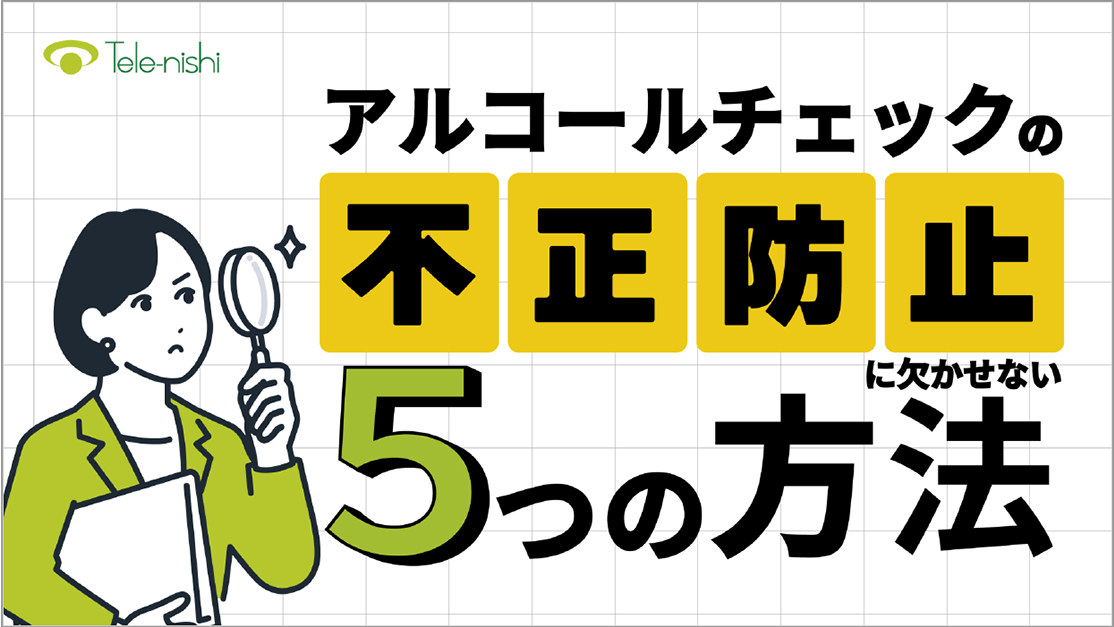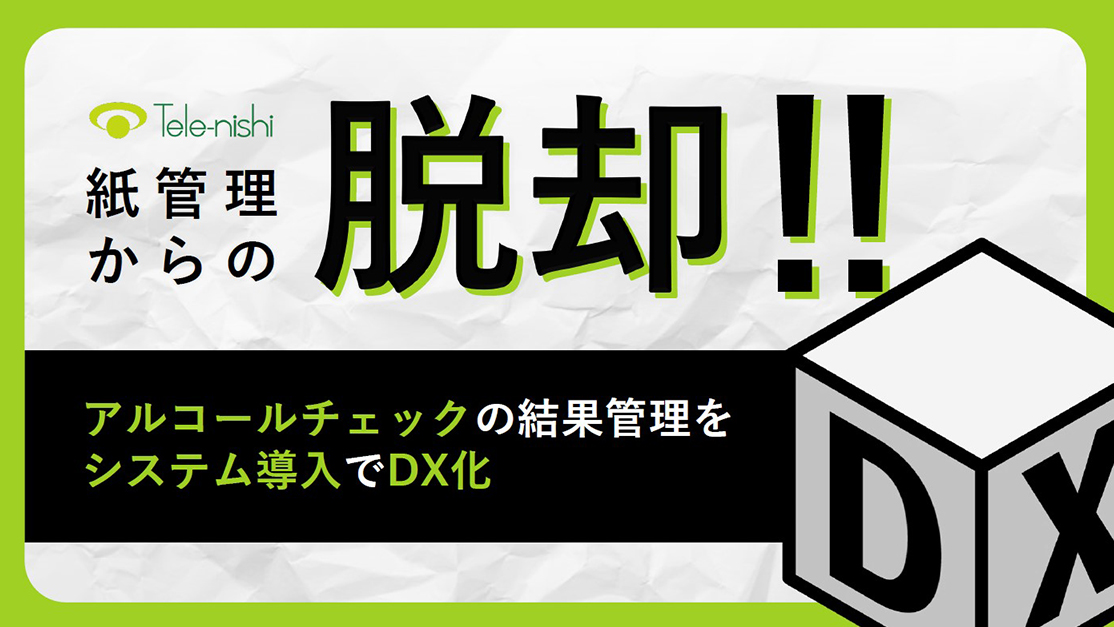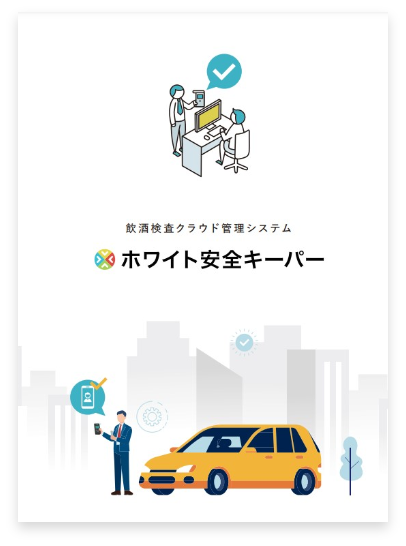アルコールチェック義務化で準備しておくこと
アルコールチェック義務化に向けて準備しておくことは以下の4点です。
- 安全運転管理者の選任
- 安全運転管理者の業務内容の確認
- 適切なアルコール検知器の準備
- アルコールチェックの管理体制の構築
- アルコールチェック記録の保管方法も検討
1つずつ詳細を見ていきましょう。
安全運転管理者を選任する
アルコールチェック義務化で準備しておくことの1つ目は、安全運転管理者の選任です。(※道路交通法第74条の3に記載)
アルコールチェックは原則、安全運転管理者が行います。安全運転管理者の選任要件は20歳以上(副安全運転管理者を置く場合は30歳以上)という年齢要件があります。また、自動車の運転管理に関して、2年以上の実務経験を持っていることも要件に含まれます。
ただし、以下に挙げる要件(欠格要件)に該当する人は安全運転管理者に選任できません。
- 過去2年以内に公安委員会から安全運転管理者等の解任命令を受けた者
- ひき逃げ、無免許運転、酒気帯び運転など一定の違反から2年を経過していない者
安全運転管理者の業務内容を確認しておく
アルコールチェック義務化で準備しておくことの2つ目は、安全運転管理者の業務内容の確認です。
安全運転管理者の業務には以下のものがあります。
- 運転者の適性、処分の把握
- 運行計画の作成
- 長距離、夜間運転時の交代要員の配置
- 異常気象時の措置
- 点呼による健康のチェック、日常点検
- 運転日誌の備え付け
- 運転者への安全運転指導
- アルコールチェック業務
緑ナンバー事業者の運行管理者とほぼ同じ内容が課せられるので、確認しておきましょう。
適切なアルコール検知器を準備する
アルコールチェック義務化で準備しておくことの3つ目は、適切なアルコール検知器の準備です。
使用するアルコール検知器は、国家公安委員会が定めるもので、音、色、数値などで呼気に含まれるアルコールを検知できればよいとされています。
特定のメーカーや製品を指定・推奨することはなく、性能上の要件もありません。
また、アルコールインターロック装置(車載式のアルコールを検知するとエンジンがかからなくなる装置)もアルコール検知器として認められます。
アルコールチェックの管理体制を構築する
アルコールチェック義務化で準備しておくことの4つ目は、管理体制の構築です。
- 事業所の規模に応じて、安全運転管理者だけでなく副安全運転管理者を選任する
- アルコール検知器は営業所ごとに備え付ける
- 長距離・夜間運転者には携帯型アルコール検知器を携行させる
上記の措置を必要に応じて準備します。
とくに、アルコール検知器は「常時有効に保持すること」と定められています。「常時有効に保持」とは「使おうとした時に確実に動作するようにしておく」ことです。
- 取扱説明書にもとづいて、電源が入るかの確認
- 損傷の有無の確認
- 故障や不具合がないかの定期的な確認
アルコールチェック記録の保管方法も検討
アルコールチェックを実施したらその結果を記録し、1年間は保管しておかなくてはなりません。そのため、記録簿の保管方法についても検討しておく必要があります。
記録簿は様式だけでなく、保管方法もとくに指定はありません。そのため、保管方法の選択肢としては以下の3つが挙げられます。
紙媒体は記録簿さえ用意すれば即座に始められるメリットがあります。ただし、保管場所を確保しないといけなかったり、紛失しやすかったりする点には注意が必要です。
パソコン上(オフライン)やクラウド上での記録なら保管場所に悩む心配もありません。また、記録自体もしやすいため運転者数が多い事業所にとってメリットの多い保管方法といえます。Excelなどを使えば自社に合った記録簿も作成できますが、その分手間もかかってしまうため、アルコールチェック専用のシステムを導入するのがおすすめです。