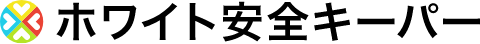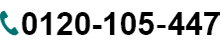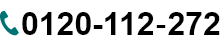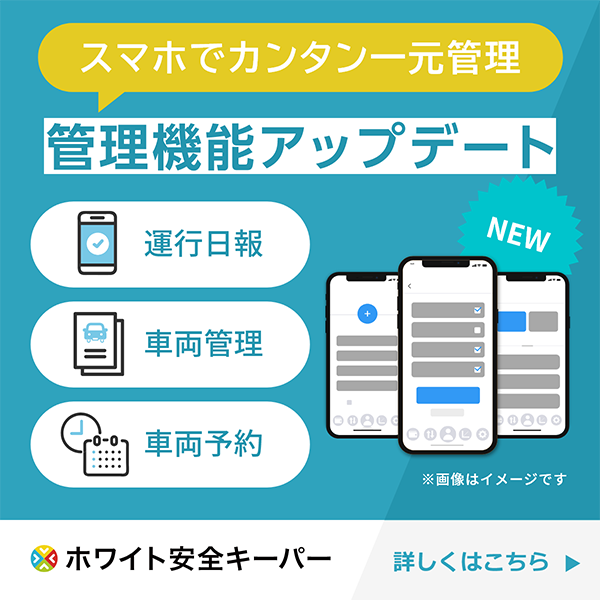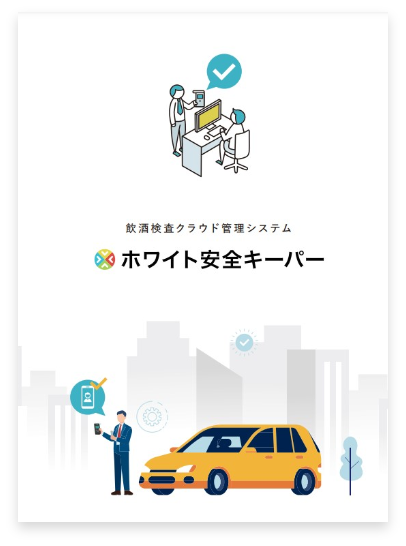事故の報告書とは?
社会人として働き始めると、さまざまな報告書を提出する機会があります。業務中に、交通事故が発生した場合に記載する事故報告書もその一例です。車両事故報告書においては、時系列で事故対応について記入します。
ここでは、事故報告書の概要について見ていきましょう。
報告書の役割
事故報告書の役割は「どのような事故が発生したのか」、第三者でも理解できるように分かりやすく正確に伝えることです。客観的かつ具体的な事実の記録が重要視されていることから、個人的な意見を記述する必要はありません。
また情報を共有することで事故の原因と発生状況を分析し、今後の事故再発防止につなげる目的もあります。さらに会社の担当者が保険会社に保険金請求の連絡をとる際にも、状況確認や説明をするために事故報告書は必要です。
原因と発生状況
5W1Hを活用すれば、事故発生時の現場の状況を客観的かつ具体的に記録できます。下記の6つの項目を参考に、事故に遭遇した当事者や発生日時などの詳細を記述しましょう。
- 誰が(Who)
- いつ(When)
- どこで(Where)
- 何を(What)
- どのように(How)
- どうして(Why)
車両事故の発生原因についても記述しますが、明確な原因だけにとどめるように注意します。これは事故の内容によっては、さまざまな原因が複雑にからんでいるケースがあるからです。そこで明確な原因以外の要因については、「調査中」と記述しておくといいでしょう。
実際の被害状況
被害者の有無や、被害者がいれば意識があるのか、その様子や怪我の程度を記載します。また衝突した場合であれば、車両や車両以外の物損の状況などを詳しく報告します。
当事者である自分自身が病院を受診した場合には、治療費も被害状況に含むといいでしょう。
事故の対応策
事故発生直後であれば、どのような対応をして事故処理をしたり解決したりしたか記入できないケースもあるでしょう。そのような場合には、「被害者は現在治療中」など状況のみを記載します。
また今後同じような事故発生を回避するために、検討すべき再発防止策についても記載が必要です。しかし「安全運転を心がける」といった、中身のない内容であれば上辺だけだと思われる可能性があるのでおすすめしません。
そこで、できるだけ具体的な対応策を記入するようにしましょう。
事故の反省点
事故報告書の最後に、事故を発生させた当事者として反省点を記述します。軽微な事故のケースでは次の例文を参考にして記載すれば、とくに問題はありません。
【例文】
約束の時間に遅れてしまうと焦っていたため、安全確認を怠ってしまった
しかし多額の金銭的な損害が発生するような重大事故のケースになると、合わせて始末書を書くことになるでしょう。