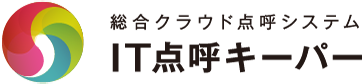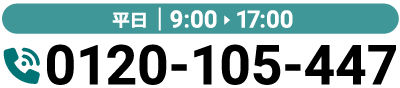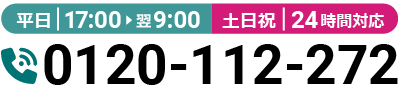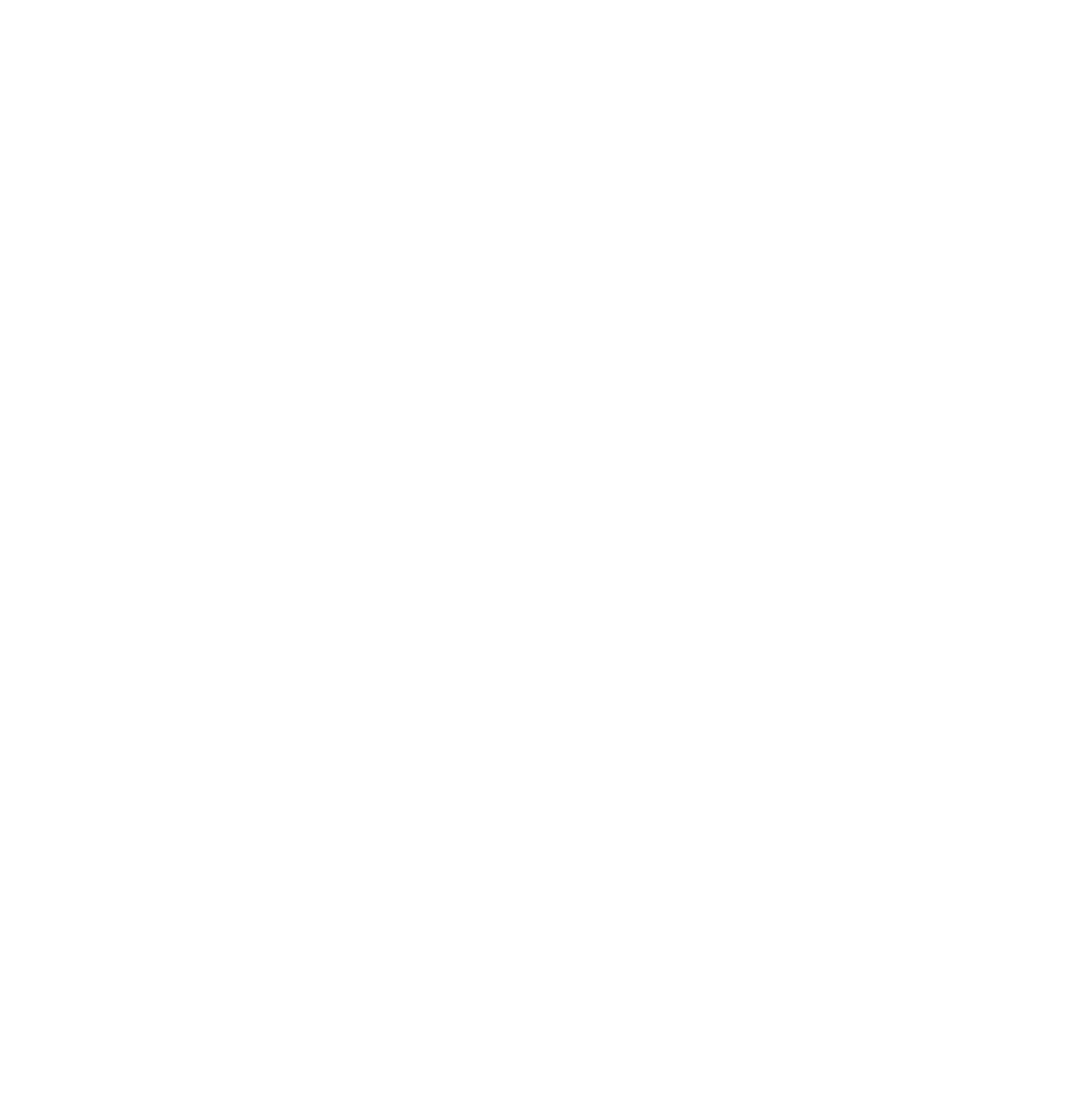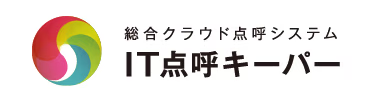白ナンバーのアルコールチェック義務化が気になる方へ押さえるべきポイントまとめ
白ナンバー

-
白ナンバー事業者は、自動車の運転前後のアルコールチェックが2022年4月1日から義務化されています。
2022年10月1日からは段階的に、アルコール検知器の使用義務化が施行される予定でした。
しかしアルコール検知器の供給状況が逼迫していることから、警察庁は当面の間の延期を発表し「道路交通法施行規則及び自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の施行に伴う道路交通量施行規則の規定の読替えに関する内閣府令の一部を改正する内閣府令案」に対するパブリックコメントを募集しておりました。
アルコール検知器の使用義務化は延期されたものの、飲酒運転防止のためにも使用することが推奨されています。企業の社会的責任の追及や懲役や罰金、行政処分などを課せられないためにも、安全運転管理者をはじめ企業全体で法令遵守の意識を高めることが大切でしょう。
本記事では、アルコールチェック義務化について押さえるべきポイントについて解説します。
道路交通法施行規則の改正内容の概要
2021年6月28日に、千葉県八街市で発生した交通死亡事故を受け、道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令が、同年11月10日に公布されました。
下校中の小学生の列に白ナンバーの大型トラックが突っ込み、5人の死傷者が出た事故を受けて検討された法改正案です。この事故において、運転手から基準値以上のアルコール反応が検知されたことが問題視されました。
一般的に緑ナンバーといわれる一般貨物自動車運送事業のトラックや旅客事業者のバスやタクシーでは義務化されているアルコール検査が、自社の荷物を運ぶための白ナンバートラックや営業利用などの社用車を所有している事業者には義務化されていなかったことから、飲酒運転撲滅のために法改正が検討されたのです。
この内閣府令を受けて、2022年(令和4年)4月1日から安全運転管理者の業務が拡充されました。これがいわゆる「アルコールチェック義務化」と呼ばれる法改正です。
アルコールチェック義務化に対して対応が必要な白ナンバー事業所は、下記いずれかのケースです。
- 安全運転管理者等の選任を必要とする自動車5台以上を保有する事業所
※自動2輪車(原動機付自転車除く)は1台を0.5台として計算
- 乗車定員が11人以上の自動車1台を以上保有する事業所
上記に該当するものの、安全運転管理者をまだ選任していない企業・事業所は、安全運転管理者を選任する必要があります。
自動車の使用者は、安全運転管理者等を選任・改任・解任した場合や、届出事項を変更した場合には、変更等が生じた日から15日以内に事業所を管轄する都道府県公安委員会に届出するようにしましょう。
安全運転管理者とは
今回の法改正にあたり着目されている安全運転管理者とはどのような業務を行っているのでしょうか。
安全運転管理者の選任については道路交通法施行規則に定められています。乗車定員が11人以上の自動車にあっては1台、その他の自動車にあっては5台以上を使用している事業所(自動車使用の本拠)ごとに1名を選任するという規則があります。
また副安全管理者についても道路交通法に定められており自動車を20台以上所有する場合は専任の必要があり、20台毎に1人の追加選任が必要となります。
| 自動車の台数 |
副安全運転管理者 |
| 19台まで |
不要 |
| 20台から39台まで |
1人 |
| 40台から59台まで |
2人 |
| 20台ごとに1人の追加選任 |
ではこの安全運転管理者の選任にあたり資格はあるのでしょうか。
安全運転管理者については、年齢20歳(副安全運転管理者が選任しなければならない場合は30歳)以上の方と定められており、副安全運転管理者も同じく年齢20歳以上の方という定め(道路交通法施行規則第9条の9)があります。
しかし20歳以上であればだれでも安全運転管理者になれるというわけではなく、過去2年以内に公安委員会の安全運転管理者等の解任命令(道路交通法第74条の3)を受けた者やひき逃げや無免許運転、酒気帯び運転などの違反をしてから2年を経過していない者については安全運転管理者になることはできません。

今回の法改正で安全運転管理者に課せられる任務
2022年4月1日施行の改正道路交通法によって、安全運転管理者に新たに追加される業務はどのようなものでしょうか。追加される業務については、内閣府令等(府令第9条の10第6号、府令第9条の10第7号)に定められています。
従来の業務に加わるのは、以下の4つの業務です。
- 業務としての運転前後のタイミングに、運転者の酒気帯びの有無について「目視等で確認(運転者の顔色、呼気の臭い、応答の声の調子等で確認する)」
- アルコールチェック測定結果などのデータを記録簿やクラウド上で1年間保存する
- アルコール検知器を常時有効に保持する
- アルコール検知器の使用義務化(2022年10月1日施行予定だったが、警察庁が2022年7月に当面の間、延期を決定)
ここでいうアルコール検知器とは、国家公安委員会が定める「呼気中のアルコールを検知し、その有無またはその濃度を警告音、警告灯、数値等により示す機能を有する機器」のことです。
なお従来の安全運転管理者等の業務は、次のとおりです。
- 交通安全教育
- 運転者の適性等の把握
- 運行計画の作成
- 交替運転者の配置
- 異常気象時の措置
- 点呼と日常点検
- 運転日誌の備付け
- 安全運転指導
これまでアルコールチェッカーを活用した運転手の酒気帯び確認は義務ではなかったことから、「安全運転管理者の業務工数が増えそう」「どのような管理が一番飲酒運転を防げるのか」と模索されている企業様も多いのではないでしょうか。
そこでおすすめなのが、アルコールチェックデータのデジタル管理です。
従来車両管理などでも管理者が手入力で台帳に記入し、ファイリングしていた企業様もいらっしゃると聞きますが、最近では手書きやエクセルシートへの記入ではなくクラウドシステムやアプリを管理で導入される企業様も増えてきております。
アルコールチェックの確認に関しても便利な活用方法ができるものがあります。
例えばスマホ連動を行っているアルコール検知器であれば、運転手が息を吹きかけるとアルコールチェックの測定結果がアルコール検知器を通してスマホのアプリに記録されるというものです。アルコールチェックの結果を手入力で記録する必要がなくなるので、手間を軽減することができます。もちろん、スマホだけでなくパソコンと連携しているアルコール検知器もありますので、自社の管理方法にあったアルコール検知器を選定することが重要です。