
貨物軽自動車安全管理者とは?
貨物軽自動車安全管理者とは、軽貨物運送の安全対策強化のため、令和7年4月から選任が義務化された役職です。運転者の指導・管理、点呼、事故記録・報告など多岐にわたる業務を通じ、事故防止と法令遵守を促進します。選任義務違反には罰則が設けられています。
最終更新日:

貨物軽自動車業界では事故防止や安全対策の強化が重要な課題となっています。近年はネット通販の普及などにより軽貨物車両を利用する機会が一段と増え、それに伴って事故リスクも高まっています。
こうした状況を踏まえ、令和7年4月(2025年4月)から新たに「貨物軽自動車安全管理者」の選任が義務化されました。これにより、車両や運転者に関する記録体制が強化され、安全教育の充実を図ろうとする取り組みが本格化します。
本記事では制度創設の背景や具体的な選任手続き、講習の内容から罰則に至るまでをわかりやすく解説します。制度のポイントを理解し、適切に対応することで、自社の安全管理を強化し、信頼性を高めることにつながります。軽貨物車両の安全対策を支援する便利なシステムも紹介しますので、最後までぜひご覧ください。

貨物軽自動車安全管理者とは、軽貨物運送の安全対策強化のため、令和7年4月から選任が義務化された役職です。運転者の指導・管理、点呼、事故記録・報告など多岐にわたる業務を通じ、事故防止と法令遵守を促進します。選任義務違反には罰則が設けられています。

貨物軽自動車安全管理者と似た役割を持つ「安全運転管理者」や「運行管理者」という役職も存在しますが、それぞれ管理する自動車の種類や、選任に必要な資格要件が異なります。
貨物軽自動車運送事業者(黒ナンバー)が対象。指定の講習を受講していることが資格要件です。監督官庁は国土交通省です。
一定数以上の自家用自動車(白ナンバー)を使用する事業所が対象。運転者の健康状態や酒気帯びの有無を確認したり、運転日報などの記録類をとりまとめたり、交通安全に関する社内教育を実施します。監督官庁は警察庁です。
トラック・タクシー・バスなどの事業用自動車(緑ナンバー)を使用する事業所が対象。運転者の過労防止を考慮した運行計画の作成や、乗務員の健康状態と酒気帯び確認、乗務記録に基づいた指導・監督などを行います。運行管理者資格者証を取得していることが資格要件です。監督官庁は国土交通省です。
すでに安全運転管理者や運行管理者を選任している場合、これらの管理者が貨物軽自動車安全管理者を兼務することが可能です。ただし、貨物軽自動車安全管理者としての選任・届出は別途行う必要があるため注意が必要です。

前述のとおり、軽貨物車両を使った小口配送の需要は年々上昇しています。インターネットを使用したEC市場が拡大し、それに伴い宅配便の取扱件数も増加しているからです。物流センターから顧客へ荷物を届ける手段として、軽自動車による運送の需要が高まっています。
しかし、その一方で、事業用軽自動車による死亡・重傷事故の件数が年々増加傾向にあります。特に平成28年から令和4年にかけて、保有台数1万台あたりの事業用軽自動車の死亡・重症事故件数は約5割増加しました。
こうした背景を受け、国土交通省は早急に安全対策を講じる必要があると判断し、令和6年5月に「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律」(令和6年法律第23号)が公布されました。
この改正に伴い「貨物自動車運送事業輸送安全規則」も改正され、貨物軽自動車運送事業者には安全管理者の選任や講習の受講、国土交通大臣への事故報告などが義務付けられました。
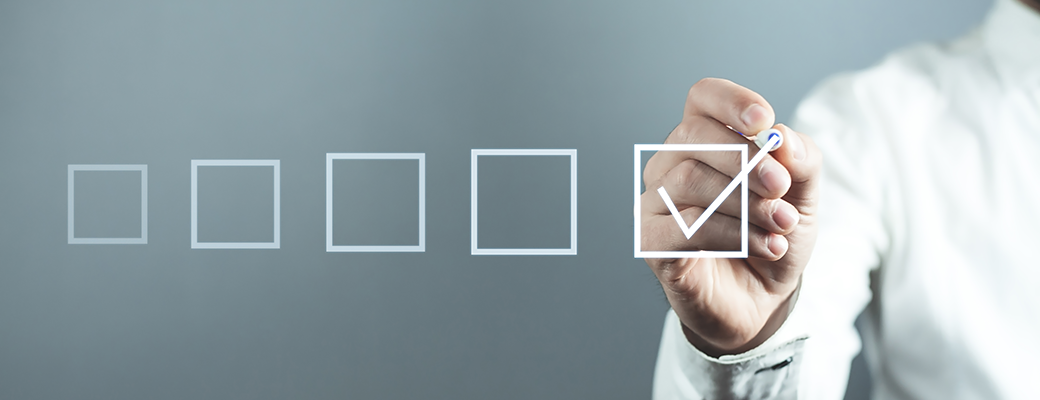
令和7年4月から本格的に施行される貨物軽自動車安全管理者制度は、軽貨物運送事業者に対して明確な安全管理義務を課すことで、事故数の抑制と運転者の安全確保を目指しています。
新制度では、以下の6項目が新たに義務化されます。
どのような内容が義務化されたのか、順に詳しく解説します。
まず営業所ごとに貨物軽自動車安全管理者を最低1名選任することが必要です。事業規模にかかわらず適用されるため、個人事業者であっても営業所単位での対応が必要となります。
個人事業主の場合は、自身を安全管理者として選任するか、配偶者や家族従業者を選任することも可能です。バイク便事業者は安全管理者選任義務の対象外です。
選任後は所定の書類を国土交通省または管轄の運輸支局等に届け出します。選任漏れや届出の不備がある場合は後に罰則を受ける可能性があるため、書類の作成時には十分注意が必要です。
貨物軽自動車運送事業者は、安全管理者として選任する者に対し、「貨物軽自動車安全管理者講習」を受講させることが必須となります。この講習では法律や規則の基礎知識に加え、事故防止の具体的な指導方法など実践的な内容も学ぶことができます。
さらに、選任後も2年に一度、「貨物軽自動車安全管理者定期講習」を受講させる必要があります。これらの講習では、安全管理に関する基本的な知識や、最新の技術・事例を学ぶことができ、受講後は学んだ知識を現場に活かし、効果的な安全対策を講じることが求められます。
選任後も定期講習を継続的に受けることで最新の法改正や業界動向を把握し、安全管理のレベルを維持・向上させることが要求されます。
前述のとおり、すでに一般貨物・特定貨物運送事業において、運行管理者として選任されている者であれば、貨物軽自動車安全管理者講習を受けずに選任が可能です。安全運転管理者は貨物軽自動車安全管理講習の受講が必要です。
運転者ごとに以下の8項目について記録を残し、一定期間保存することが義務付けられました。
これは一般的に「運転日報」と呼ばれます。
運転日報の保管期間は、1年間の保管義務が定められています。運転日報は労働者の運転時間を記録する書類でもあるため、労働基準法にも関わってきます。労働基準法によれば労働関係に関する重要書類は5年間保存しなければならないと定められているため、5年分保管しておくとより安心です。
保管方法は、紙・電子データどちらでも問題ありませんが、電子データでクラウドサーバーなどへ保存するのがおすすめです。電子データで管理すれば、当然ですが紙は不要になりますので、ペーパーレス化にもつながります。紙ベースの運転日報は、ファイルに綴じてラックにしまう手間や、量が増えるほど過去のデータを調べるのに時間がかかり、業務効率が悪くなります。
事故が発生した場合、以下の6項目を記録し、3年間保存することが義務付けられました。
業務記録や事故記録の作成・保存を徹底することで、事業者の管理責任を明確にし、万が一のトラブル時にも適切な対応が行われるように設計されています。
万が一、重大な事故が発生した場合、以下の7項目について所定の様式に記入し、30日以内に運輸支局等を通じて国土交通大臣に報告することが義務付けられました。
なお、2人以上の死者が発生するなど特に重大な事故については、発生後24時間以内に、可能な限り速やかに運輸支局等へ報告しなければなりません。
国土交通省の対応が入るほどの重大事故は、業界の信用にも大きく影響します。報告義務と同時に企業が迅速な対応策を打ち出し、社会に向けて改善努力を示すことが、信頼回復の大切なステップとなるでしょう。
初任運転者(特別な指導および適性診断を過去一度も受けていない者)、高齢運転者(65歳以上)、事故惹起運転者(死傷者を生じた事故を起こした者)に対して、特別な指導教育の実施と、国土交通大臣が認定する適性診断の受診が義務付けられました。
適性診断では、運転者の健康状態や交通ルールの理解度をチェックし、必要に応じて補習や再講習を受けさせるなどの措置を行います。これにより、本人もリスク意識を再確認し、安全運転に対する取り組みを強化できます。また、運転者の氏名、当該運転者に対する指導や適性診断の受診の状況などを記載した「貨物軽自動車運転者等台帳」を作成し、運転者等が所属する営業所に備える必要があります。

貨物軽自動車安全管理者の選任義務化に伴い、事業者が従来から取り組んでいる安全対策の徹底も引き続き求められています。以下の3項目です。
順に詳しく解説します。
乗務前の点呼は、引き続き実施が義務付けられています。運転者や車両に何らかの問題が確認された場合、運行させてはいけません。
点呼の内容は「点呼記録簿」に記録し、1年間保存しなければなりません。また、アルコール検知器を常時有効に保持し、いつでも正確に測定できる環境を整備する必要があります。
一人で事業を行っている場合は、自ら確認を行う必要があります。
安全運行を実現するために、法令で定められている拘束時間や休息時間、運転時間などの基準を遵守し、運転者に休息を十分に与えることが重要です。
過労運転を防ぐため、法定労働時間や休憩時間を考慮した適正な乗務割を作成し、それに基づいて運転者を運行業務に従事させます。
すべての運転者に対して、指導と監督を毎年実施する必要があります。実施した日時と場所、実施内容、実施した者と受けた者を記録し、3年間保存しなければなりません。
事故防止対策に関する指導・監督や、国土交通大臣または地方運輸局長から事故防止対策に関する通知があった場合、運行の安全確保について運転者への指導・監督を行います。

令和7年4月施行の新制度において、猶予期間以降も対応しなかった場合、以下の罰則が定められています。
安全管理者が業務を怠った結果、従業員が安全運行に支障をきたし、飲酒運転などで事故を惹起した場合、従業員に車両を提供した者として会社も罰則を受ける可能性があります。
既存事業者(令和7年3月31日までに貨物軽自動車運送事業経営届出を提出した事業者)に対しては、以下の猶予期間が設けられています。
まずは管理者やドライバー全員が、貨物軽自動車安全管理者制度の内容を正しく理解することが欠かせません。講習や社内研修を通じて、記録義務や報告手順をしっかり周知徹底させる必要があります。
次に、定期的な記録のチェックや教育の実施が重要です。管理者が日常的にドライバーから運行状況をヒアリングし、早期に問題点を洗い出して改善策を講じることで、大きなトラブルを未然に防ぎます。
最後に、経営陣からの積極的な支援も不可欠です。安全管理に必要な人員や予算を確保し、組織全体で安全性向上を目指す姿勢を示すことが違反抑止に大きく貢献します。

今回義務化された「貨物軽自動車安全管理者」の選任は、増加する軽貨物運送の安全性向上を目的としています。安心な物流社会を実現し、安全な運行業務を確保するために、早めに準備を進めましょう。
その一方で、貨物軽自動車安全管理者の業務内容は多岐にわたり、徹底しようとすると業務負担が増加する可能性があります。法改正対応を効率的に進めたい・貨物軽自動車安全管理者の業務負担を軽減したいとお考えの方には「IT点呼キーパー」の活用が有効です。
IT点呼キーパーは、業務効率化・人的負担軽減・虚偽報告防止など、安心安全な運行管理を実現する総合クラウド点呼システムです。点呼結果はクラウドサーバーに自動保存・1年間保管されるので、運転日報の作成やデータ管理の手間を削減できます。コストはかかりますが、長期的には事故や罰則のリスク低減につながります。
専用フォームからお問い合わせいただいた方全員に、IT点呼キーパーの詳細がわかる無料カタログをプレゼントしています。詳細はこちらから確認できますのでぜひご覧ください。
【出典】
貨物軽自動車運送事業における安全対策を強化するための制度改正について|国土交通省(参照2025-07-01)
「宅配事業とEC事業の生産性向上連絡会」の開催について|経済産業省・国土交通省(参照2025-07-01)
貨物自動車運送事業法|e-Gov法令検索(参照2025-07-01)
貨物自動車運送事業輸送安全規則|e-Gov法令検索(参照2025-07-01)
労働基準法|e-Gov法令検索(参照2025-07-01)

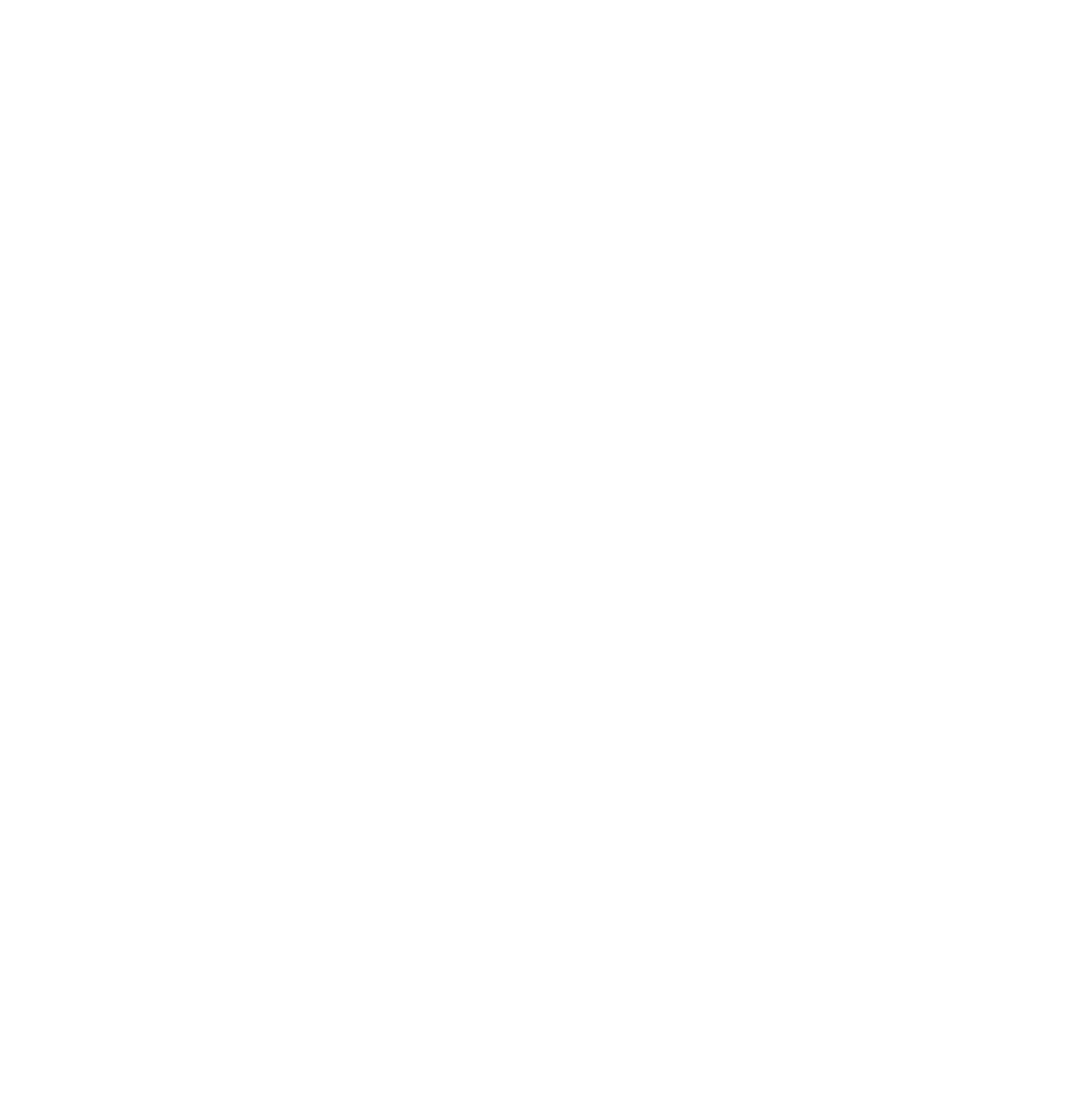 この記事をシェアする
この記事をシェアする
1

最終更新日:
自動車運送業における点呼業務は、貨物自動車運送事業輸送安全規則の第7条で実施が義務付けられています。基本は対面で実施しなければなりませんが、近年はICT技術の高度化によって対面点呼や電話点呼に代わる「遠隔点呼」が実施できるようになりました。法令で義務付けられている一方で、守っていない運送事業者が存在するのも事実です。国土交通省近畿運輸局が令和6年度7月26日に公表した、令和5年度「自動車運送事業者に対する監査と処分結果」の内容分析結果によると、運送事業者の最も多い違反は点呼だと判明しています。そこで今回は、あらためて正しい点呼の方法や点呼に関する違反時の罰則をご紹介します。点呼業務を効率化させるための方法もご紹介しているので、ぜひ最後までご覧ください。
2

最終更新日:
2022年(令和4年)4月より開始した「遠隔点呼」ですが、2023年(令和5年)3月31日以降ちょっとした変化があったことをご存じでしょうか。これに伴い、遠隔点呼の要件や申請方法が変更されました。そこで本記事では遠隔点呼の定義をおさらいし、2023年4月1日以降の申請方法について解説しますのでトラック事業者の方は参考にしてください。
3

最終更新日:
令和4(2022)年4月より、「遠隔点呼実施要領」に基づいた遠隔点呼の申請が開始されています。すでに実施されている「IT点呼」と新たに申請できるようになった「遠隔点呼」には、どのような違いがあるのでしょうか?対面点呼と比べると遠隔点呼とIT点呼は同義に見えることから、どうしても混乱しがちです。本記事では遠隔点呼とIT点呼の違いをまとめましたので、ぜひ参考にしてください。
4

最終更新日:
自社のドライバーだけでなく、他のドライバーや歩行者などの安全確保のために法律で義務付けられている点呼。平成23年5月1日より、運送事業者がドライバーに対して実施することとされている点呼において、ドライバーの酒気帯びの有無を確認する際にアルコール検知器を使用することとなりました。そういった経緯もあり、点呼内容の記録や保管は複雑で、運用に不安を抱えている管理者の方も多いのではないでしょうか。そこで本記事では、事業用自動車(緑ナンバー)運送業者向けに点呼記録簿に関するさまざまな情報をご紹介します。点呼に関する不安がなくなり、管理が楽になるツールもご紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。
5

最終更新日:
新型コロナウイルス感染症の流行後、通販や宅配サービスの利用が急増し、狭い住宅地でも荷物をスムーズに運べる軽貨物運送の需要が高まっています。しかし、軽貨物運送事業を始めるにはさまざまな規定があり、「何から手をつけてよいかわからない」と悩んでいる方も多いのではないでしょうか。そこで今回は、軽貨物運送の基本情報や登録に必要な要件、そして点呼についてわかりやすく解説します。軽貨物車を使った事業を始めたい方はもちろん、すでに事業を営んでいる方もぜひ最後までご覧いただき、顧客の多様なニーズに対応できる事業展開にお役立てください。
お役立ちコンテンツ
サポートメニュー
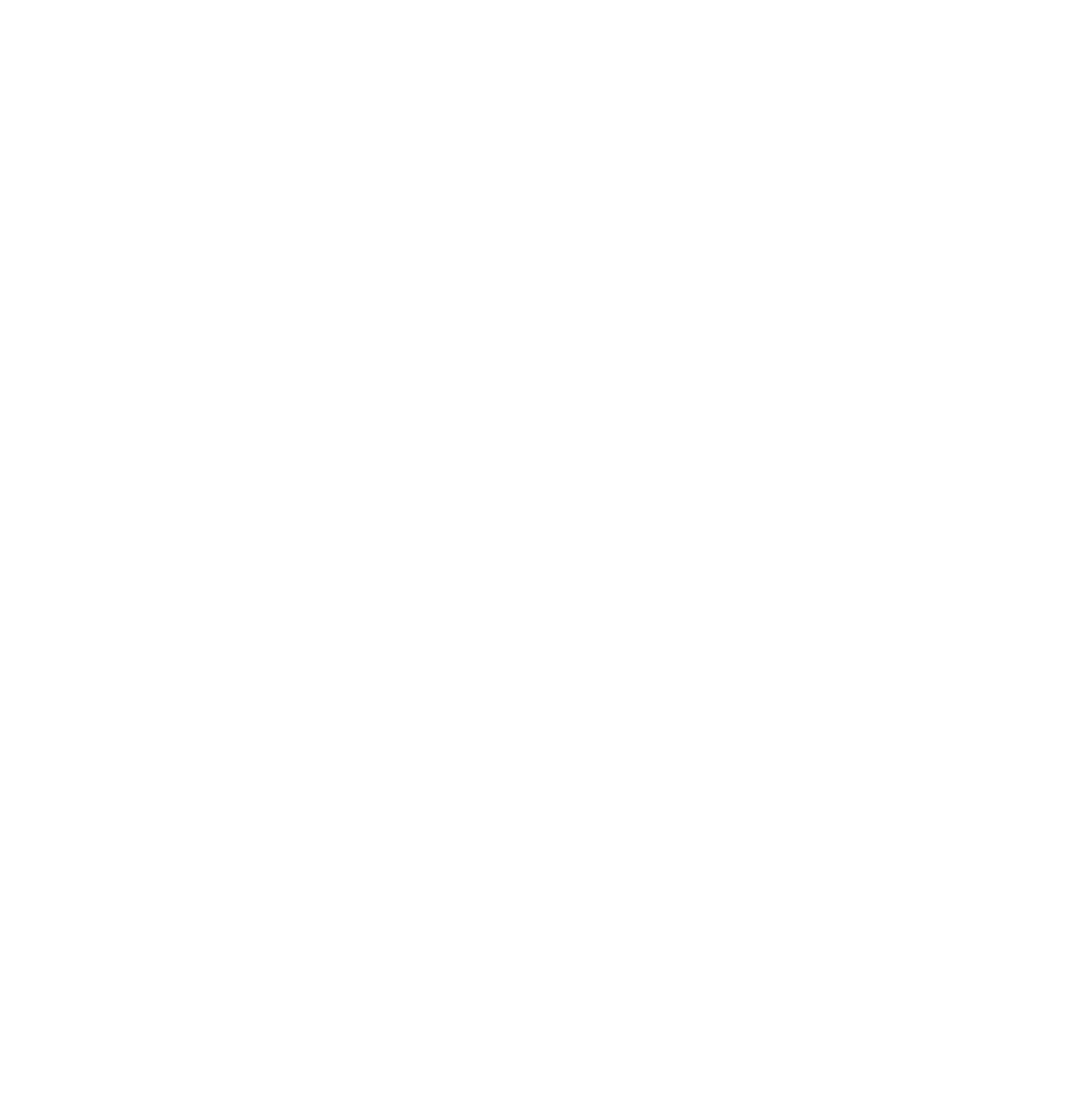 IT点呼キーパーをフォローする
IT点呼キーパーをフォローする