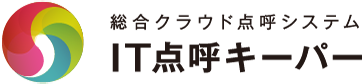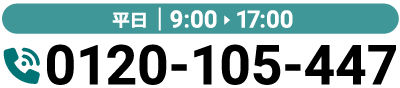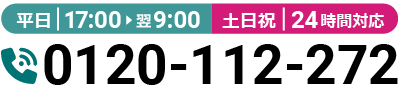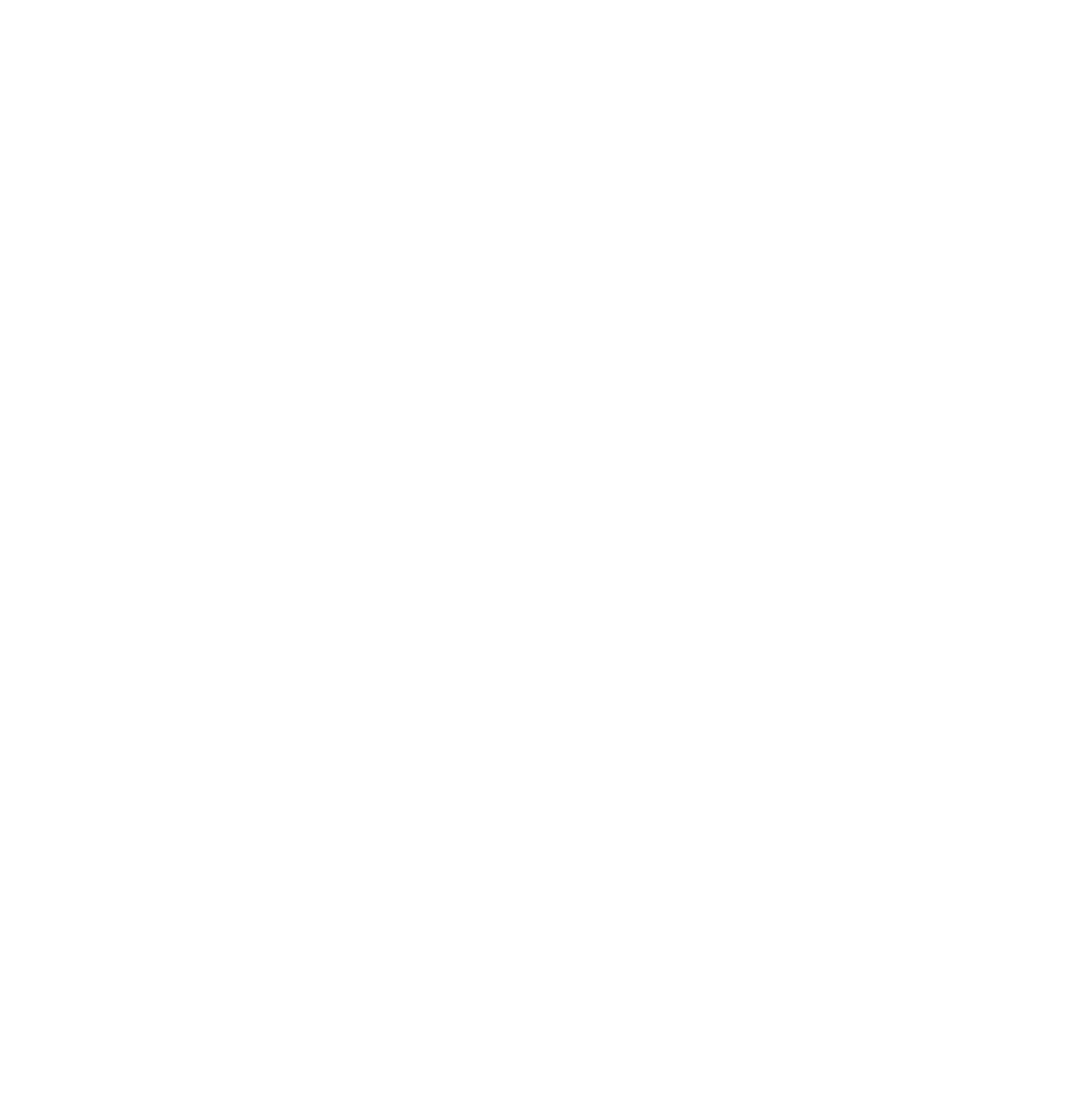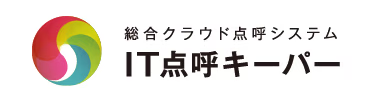飲酒運転の罰則規定(2024年7月時点)
飲酒運転とは、アルコール分を体内に保有した状態で運転する行為です。
飲酒運転は重大な犯罪であり、その結果として多くの悲劇的な事故が発生しています。そのため社会的影響が大きい事業用自動車のドライバーによる飲酒運転の罰則は、ドライバーおよび事業者の両方に対して厳しく設定されています。これは飲酒運転が社会に及ぼす影響の大きさと事故防止の観点から強化されてきた経緯があります。
それでは、具体的な罰則内容を見ていきましょう。
飲酒運転は、「酒酔い運転」と「酒気帯び運転」の2種類に分類されています。
アルコール量からみた「酒酔い運転」と「酒気帯び運転」の違いは、次のとおりです。
- 酒酔い運転
呼気中アルコールの濃度にかかわらず、アルコールの影響により車両等の正常な運転ができない状態
- 酒気帯び運転
呼気中にアルコール濃度が道路交通法における基準値の0.15mg/Lを超えている状態で運転をしていた場合
酒気帯び運転はさらに2段階に分かれています。
呼気中アルコール濃度が「0.15mg/L以上0.25mg/L未満」と「0.25mg/L以上」の状態があり、たくさん飲酒している後者が罰則は重くなります。
0.15mg/L未満であれば絶対に大丈夫かと言うと、そうではありません。
呼気中アルコール濃度がたとえ0.15mg/L未満でも、アルコールが原因で正常に運転が出来ない状態に該当した場合、酒酔い運転とみなされる可能性があります。
運送事業者の場合、点呼時にドライバーに対して「酒気帯びの有無」を確認することが義務付けられています。
アルコールチェックでは、数値が0.15mg/L未満であるか否かは考慮されません。
つまりドライバーからアルコール分が微量でも検知された時は、運行管理者はそのドライバーに乗務をさせてはいけないということになります。
以上を踏まえて、ここでは2024年7月時点の飲酒運転にかかる罰則規定について見ていきましょう。
ドライバーに対する罰則
飲酒運転を行ったドライバーには厳しい罰則が課されます。
飲酒運転は重大な交通事故を引き起こす可能性が高いため、厳しい罰則を課すことで抑止効果を期待しています。例えば、飲酒運転が発覚した場合、免許の停止や取り消し、罰金、さらには懲役刑が科されることがあります。また、交通事故を起こした場合は賠償金が発生することもあります。
現在のドライバーに対する行政処分の内容は、次のとおりです。
左右にスライドすると表を見ることができます
|
呼気1リットル中の
アルコール濃度 |
交通
違反点数 |
行政処分
(免許証) |
刑事罰 |
| 酒気帯び運転 |
0.15mg/L以上
0.25mg/L未満 |
13点 |
免許停止90日 ※前歴及びその他の累計点数がない場合 |
3年以下の懲役又は
50万円以下の罰金 |
| 酒気帯び運転 |
0.25mg/以上 |
25点 |
免許取り消し
(欠格期間2年) |
3年以下の懲役又は
50万円以下の罰金 |
| 酒酔い運転 |
規定なし
(無条件) |
35点 |
免許取り消し
(欠格期間3年) |
5年以下の懲役又は
100万円以下の罰金 |
【出典】:みんなで守る「飲酒運転を絶対にしない、させない」|警視庁(参照2024-07-19)
欠格期間とは、運転免許が取り消された場合、運転免許を再度受けることができない期間のことです。
また道路交通法は飲酒運転に対する取り締まりを強化しており、ドライバーの呼気中のアルコール濃度が基準値を超える場合、即座に厳しい処罰が科されることになります。具体的には、呼気中のアルコール濃度が0.15mg以上の場合、違反点数が加算され、基礎点数に基づいて免許の取り消しや処分が行われます。状況によっては、飲酒運転だけでなく、同乗者や酒類提供者にも罰則が適用される場合があります。周囲の人も運転免許の有無にかかわらず飲酒ドライバーと同様に厳しく罰せられるほか、免許保有者は免許停止または免許取り消しになる可能性があります。飲食店も処罰の対象となるので、酒類を提供する際には注意が必要です。
左右にスライドすると表を見ることができます
|
ドライバーが酒酔い運転を
した場合 |
ドライバーが酒気帯び運転を
した場合 |
| 車両提供者 |
5年以下の懲役又は
100万円以下の罰金 |
3年以下の懲役又は
50万円以下の罰金 |
酒類提供者
車両の同乗者 |
3年以下の懲役又は
50万円以下の罰金 |
2年以下の懲役又は
30万円以下の罰金 |
【出典】:みんなで守る「飲酒運転を絶対にしない、させない」|警視庁(参照2024-07-19)
また自動車運転の悪質性や危険性等の実態に応じた処罰を行えるよう「自動車運転死傷処罰法」が成立し、平成26年5月に施行されました。
そこでアルコール等の影響により正常な運転が困難な状況で人を死傷させた場合には、従来の危険運転致死傷罪より刑を軽減した、新しい「危険運転致死傷罪」が新設されています。
従来の「自動車運転過失致死傷罪」が刑法から移され、「過失運転致死傷罪」として規定されていることも知っておきましょう。
なお加入が義務付けられている自賠責保険においては、飲酒運転で事故を起こした当事者は補償適用の対象外です。
被害者は、保険制度における被害者救済の観点から、補償対象となります。
事業者に対する行政処分
「事業用自動車総合 安全プラン2009」(平成21年3月)を踏まえ、自動車運送事業の飲酒運転等に対する処分強化がなされました。
現在の事業者に対する行政処分の内容は、次のとおりです。
|
行政処分 |
事業者が
飲酒運転等を
下命・容認した場合 |
14日間の事業停止 |
飲酒運転等+
重大事故に係る
指導監督義務違反の場合 |
7日間の事業停止 |
飲酒運転等に係る
指導監督義務違反の場合 |
3日間の事業停止 |
飲酒運転等に
対する処分
(旅客自動車運送事業、貨物自動車運送事業) |
初違反:
100日車の車両使用停止
再違反:
200日車の車両使用停止 |
このように、従業員が飲酒運転を行った場合、事業者も厳しい行政処分の対象となります。
これは事業者が従業員の管理責任を負っており、公共の安全を確保するために必要だからです。例えば、飲酒運転が発覚した場合、事業許可の取消しや営業停止などの処分が下されることがあります。
事業者は従業員の飲酒運転防止のために、アルコール検知器の導入や定期的な教育を実施する必要があります。

アルコール検知器の精度について
点呼時にドライバーのアルコールチェックを行う際に使用するアルコール検知器の精度は重要です。
アルコール検知器は、飲酒運転防止のための重要なツールですが、その精度には大きな差があります。
今回は、その精度について詳しく解説します。
アルコール検知器の精度は、メーカーや使用されているセンサーの種類によって異なります。
適切な製品選びと管理が、飲酒運転の防止に直結します。
正確なアルコール検知ができないと、飲酒運転を確実に取り締まることができず、重大な事故を防ぐことが難しくなります。例えば、精度の低いアルコール検知器を使用すると、少量のアルコール摂取やタバコの煙などで誤検知する可能性があります。このような誤検知により、無実の人が処罰されたり、逆に飲酒ドライバーが見逃されるリスクがあります。飲酒運転に関わる重い罰則を受けない為にも、点呼時にドライバーのアルコールチェックを行う際に使用するアルコール検知器の精度は非常に重要です。
アルコール検知器の精度は内部のアルコールを検知するセンサーによって変わります。
センサーは「電気化学式センサー」と「半導体式センサー」の2種類に大別されますので、それぞれの特徴を押さえておきましょう。
各センサーの特徴は下記のとおりです。
各センサーの特徴
電気化学式センサー
- アルコール以外の成分で反応することが少ない
- 外気の環境の影響は受けにくい
- 校正間隔が長い
- 製造コストが高い
半導体式センサー
- 製造コストが安い(安価で購入しやすい)
- 安定性・再現性が高くない
- 経年変化が大きく、使い捨てが基本となる
※特徴は一般的な内容で製造メーカーによって異なることがあります。
点呼業務で使用するアルコール検知器は、再現性が高く、誤検知の少ない「電気化学式センサー」がおすすめです。
またGマークを取得している事業者なら、IT点呼や遠隔点呼と連動できるタイプのアルコール検知器をおすすめします。
IT点呼キーパーは、IT点呼・遠隔点呼・対面点呼・電話点呼・スマホ点呼を一元管理できる総合クラウド点呼システムです。点呼結果はクラウドサーバー上に自動保存されるので、虚偽報告の防止が可能です。さらに点呼結果をデジタル化して一元管理することで、離れた拠点の点呼記録もリアルタイムで確認できます。
安心安全な点呼管理を実現したいという運送事業者の方は是非ご覧ください。
IT点呼キーパーが対応しているアルコール検知器は「電気化学式センサー」を搭載した検知器が多いです。
毎日検知器を活用する運送業の方向けに、誤検知が少ない検知器を採用しています。
据置型、携帯型など、お客様の運用に応じて検知器をお選びください。
フィガロ技研株式会社
左右にスライドすると表を見ることができます
| 製品名 |
センサー |
設置方法 |
パソコンに記憶 |
特徴 |
FuGo-Pro
FALC-11 |
電気化学式
センサー |
据置型
携帯型 |
◎ |
- ハンディタイプ、据置記録型・遠隔地管理用いずれの使い方も可能
- 本体機器に検査結果を2,500件まで記憶
|
株式会社東洋マーク製作所
左右にスライドすると表を見ることができます
| 製品名 |
センサー |
設置方法 |
パソコンに記憶 |
特徴 |
AC-015
AC-015BT |
電気化学式
センサー |
携帯型 |
◎ |
- パソコン管理対応タイプとスマートフォン接続タイプの2タイプ
- 各社デジタルタコグラフとも連動(一部メーカーを除く)
|
| AC-011IT |
半導体&
電気化学式
センサー |
据置型 |
◎ |
- 半導体センサー・電気化学式センサーの両方を搭載
- スピーディーな連続検査の点呼に優れている半導体センサーでチェック
- アルコール反応があった場合は、より正確な電気化学式で最終確認
|