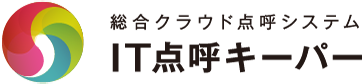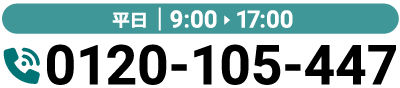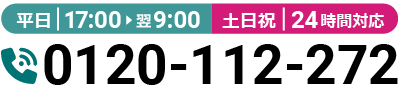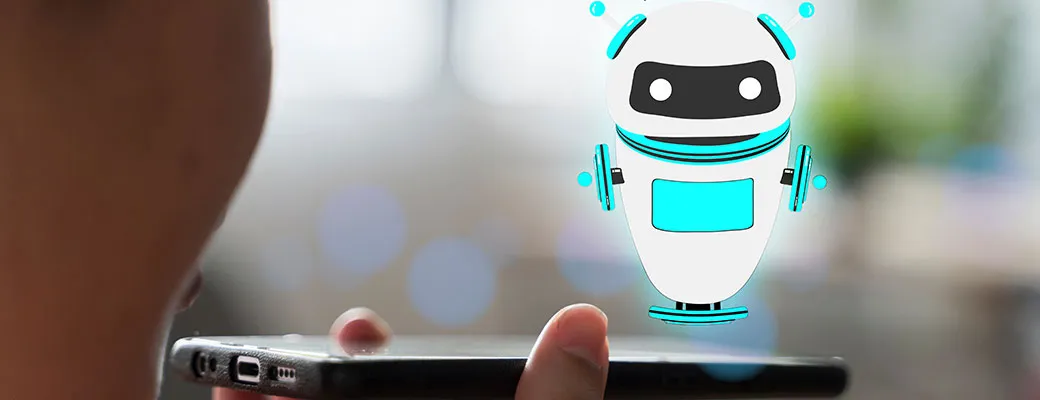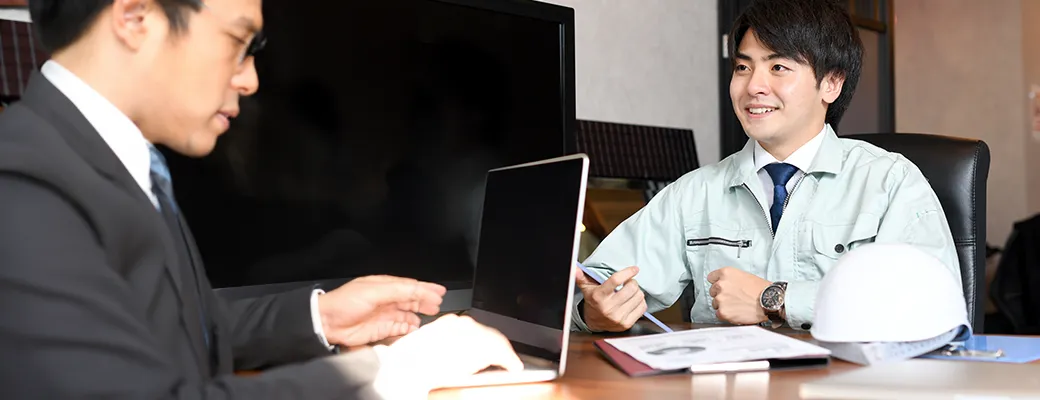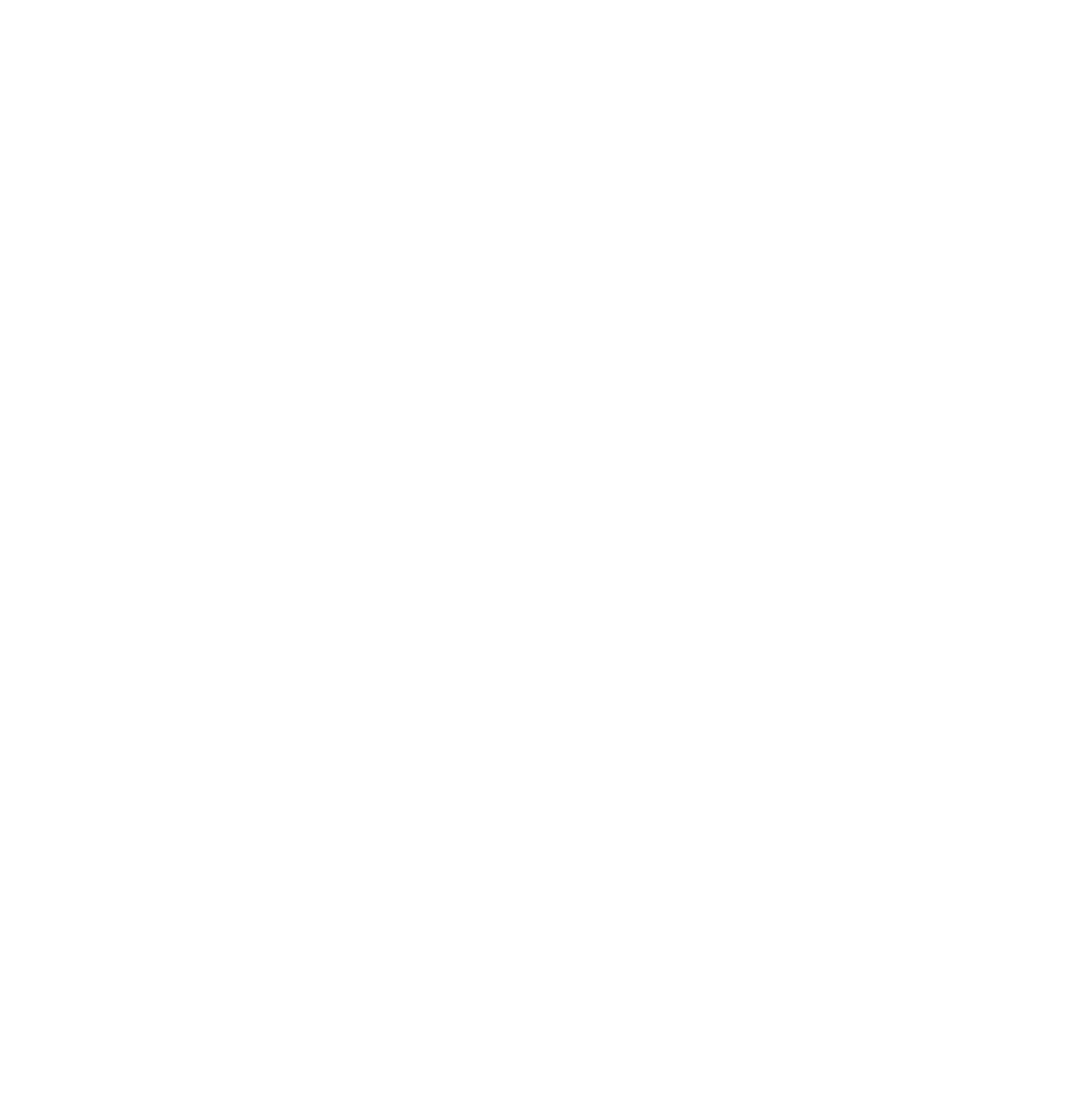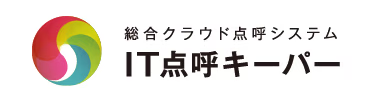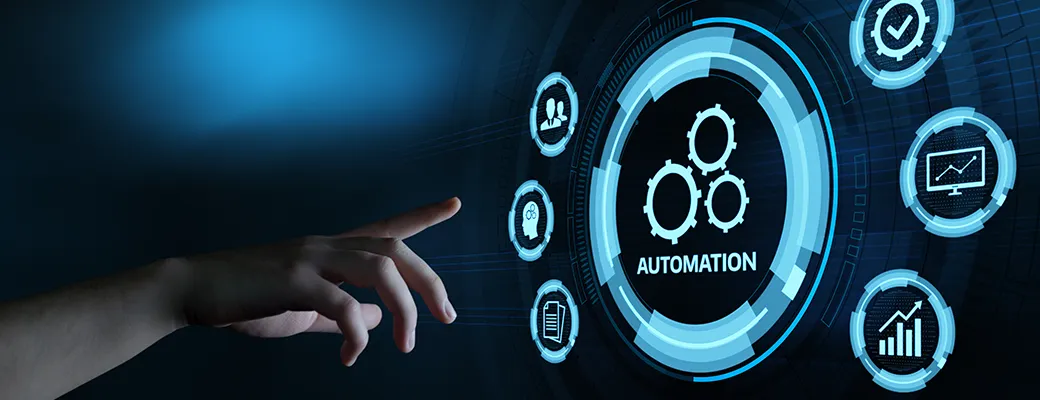
業務前自動点呼とは?
業務前自動点呼とは、業務前に実施する点呼において、確認や指示、判断、記録の一部またはすべてを、国が定める要件をクリアした自動点呼機器に代替した点呼です。運送事業者は安全な運送とドライバーを守る目的で、業務を始める前と終わったときに点呼業務が義務付けられています(貨物自動車運送事業輸送安全規則の第7条)。
業務前自動点呼の制度概要
運送業ではドライバーの健康状態や酒気帯びを確認し、業務を行えるかどうかを判断するために業務前点呼を行っています。これまで点呼業務は、国家資格を持つ運行管理者や補助者などが対面で行う必要がありましたが、2025年4月1日に公布・施行された改正点呼告示によって、自動点呼が可能となりました。
これにより、従来は早朝や深夜、休日に関係なく運行管理者や補助者が対応する必要がありましたが、自動点呼が可能になったことで運行管理者の負担軽減につながります。また、点呼記録が機器によって保存・管理されるようになり、コンプライアンスの向上も期待できます。
業務前自動点呼が導入されるに至った背景
安全な運行を守るために義務付けられていた点呼業務ですが、近年の配送量増加により、早朝や休日なども対応が増え、ドライバーや運行管理者の負担は増えている状態でした。特に運行管理者はドライバーの運行スケジュールに合わせないといけないため、勤務時間が不規則になりやすく、さらに管理責任も問われることから、負担の大きさとプレッシャーに耐えきれず、辞めてしまう人も少なくありません。
こうした課題を解消するために、業務前自動点呼の導入が検討されてきました。2023年から実証実験がスタートし、2024年5月からは先行実施事業も始まっています。そして2025年4月30日に改正点呼告示が公布・施行され、8月から認証機器の情報が公開されたことで、本格的に業務前自動点呼が始動したのです。
業務後自動点呼との違い
業務後自動点呼は2023年から制度化されており、運転業務終了後における点呼を、一部またはすべて認定機器を使って自動で実施する仕組みです。本人確認に加え、以下の情報を確認・記録する必要があります。
- 酒気帯びの有無
- 車両・道路の状況
- 運行内容の報告
- 積荷の状態や苦情の有無
一方、業務前自動点呼ではこれらに加え、次の3点についても記録と確認が求められます。
- 運転者の疾病・疲労・睡眠不足の状況(自己申告による確認)
- 日常点検の実施有無
- 当日の運行に関する指示事項
特に疾病や疲労、睡眠不足については、体温や血圧の測定値だけで判断するものではありません。これらは自己申告により確認・記録を行うことが基本とされており、体温や血圧については個別に測定値を保存する必要があります。
加えて、業務前自動点呼では確認結果に応じて「中断」または「中止」の対応が制度上定められています。たとえば以下のようなケースです。
- 酒気帯びの反応がある場合
- 日常点検が未実施、または不備がある場合
これらは即時「中止」となり、自動点呼の再開はできません。一方で、次のような場合には一時的に「中断」となり、運行管理者の判断が必要です。
- 体温や血圧の異常値が出た場合
- 疾病・疲労・睡眠不足の申告により運行可否が懸念される場合
この「中断」の後、管理者が安全に問題ないと判断すれば点呼は再開されますが、そうでなければ「中止」へと切り替えられます。
このように「中止」と「中断」では制度上の位置づけと対応が明確に異なります。誤った表現を用いると、法令違反や運用ミスにつながるおそれがあるため、正確な理解と伝達が重要です。