
運行管理補助者とは?
運行管理補助者とは、運行管理者の業務をサポートする人です。運行管理者の監督・指示下で運行管理に関する業務の一部を運行管理者に代わって行います。
運行管理者の指示にもとづき業務を行うことを基本としているため、運行管理補助者を単独で置くことはできません。
最終更新日:

事業用自動車の運行を陰で支える運行管理者をサポートする運行管理補助者。
文字通り運行管理者の業務を補助するのですが、誰が何をどこまで行えるのかを正確に把握している人は少ないのではないでしょうか。そこで本記事では、運行管理補助者の業務内容や選任方法などを解説します。運行管理補助者を適切に配置し業務に従事させると、運行管理者の業務負担が軽減し、厳しさを増す労働時間管理等が楽になる可能性があります。
ぜひ最後までご覧ください。

運行管理補助者とは、運行管理者の業務をサポートする人です。運行管理者の監督・指示下で運行管理に関する業務の一部を運行管理者に代わって行います。
運行管理者の指示にもとづき業務を行うことを基本としているため、運行管理補助者を単独で置くことはできません。

運行管理補助者と運行管理者の最大の違いは、業務についての判断ができるかできないかにあり、これによって運行管理補助者が行える業務の範囲が決められています。
ここでは、運行管理補助者と運行管理者の違いに焦点をあててご紹介します。
運行管理者には業務内容に関して自ら判断を下す権限が与えられており、下記のような業務について、内容と方法を自分で決められます。
一方、運行管理補助者は業務に関して自ら判断を下せません。
(引用)補助者は、運行管理者の履行補助を行う者であって、代理業務を行える者ではない。
法律上、運行管理補助者に認められているのは、運行管理者が下した判断と決めた方法に従って「作業をすること」だけです。
運行管理補助者ができる業務は、運行管理者が判断・決定した業務内容を指示通りに実行することのみです。
それ以外の行為は原則として運行管理者にしかできません。
例えば運行指示書を作成する際に、指示内容や作成方法を考え決める行為は運行管理者にしかできませんが、決定した作成方法に従って運行指示書に指示内容を記載する行為は運行管理補助者も行えます。
原則、運行管理補助者は判断や意思決定ができませんが、例外として点呼においてドライバーの点呼結果に問題がなく運行させることができる場合に限り「問題なしと判断する」行為が認められています。
運行管理者に選任されるには、事業種別に応じた運行管理者資格者証の取得が必須になります。運行管理者資格者証を取得するには基礎講習を受講し、運行管理者試験に合格しなければなりません。
一方、運行管理補助者の場合は、運行管理者基礎講習を受講すれば選任を受けられます。
両者の資格要件をまとめると、以下の表の通りとなります。
| 講習の受講 | 試験の合格 | |
|---|---|---|
| 運行管理者 | 必要 | 必要 |
| 運行管理補助者 | 必要 | 不要 |

ここでは運行管理補助者が行う主な業務内容2つについて詳しくご紹介します。
運行管理補助者は点呼業務の一部とそれに付随するサポート業務を行います。
以下に具体的な業務例を紹介します。
なお、1か月当たりの総点呼回数のうち、少なくとも3分の1は運行管理者が実施することと定められています。
そのため、運行管理補助者が行う点呼は総回数の3分の2未満に収めなければなりません。
運行管理補助者は運行に必要な資料の作成を行います。
以下に具体的な業務例を紹介します。
運行管理補助者ができるのは資料の「作成行為」のみです。
資料に盛り込む指示内容の選定やどのように作成するか(書面またはデータで作成など)などは運行管理者でないと決められません。

運行管理補助者は、以下の2つのいずれかに該当する者から運行管理者が選任します。
運行管理者基礎講習は、独立行政法人自動車事故対策機構(NASVA)をはじめ、国土交通大臣が認定した機関で受講できます。認定機関についてはこちらのページでご確認いただけます。
【出典】:講習認定機関一覧|国土交通省(参照2025-03-10)
なお、機関によって認定を受けている講習の種類が異なります。
「認定を受けている講習の名称」欄に受講したい講習の種類が記載されていることをご確認ください。
運行管理補助者の選任には、事業者の種類によって手続きの要・不要が異なります。
| 事業者の種類 | 手続きの必要性 |
|---|---|
| 旅客事業者(貸切バスなど) | 必要 |
| 一般貨物自動車運送事業者(トラック) | 不要 |
なお、一般貨物自動車運送事業者は、選任手続きは不要ですが運行管理規程を定める義務があり、規程の中で職務内容や権限などをまとめておかなければなりません。
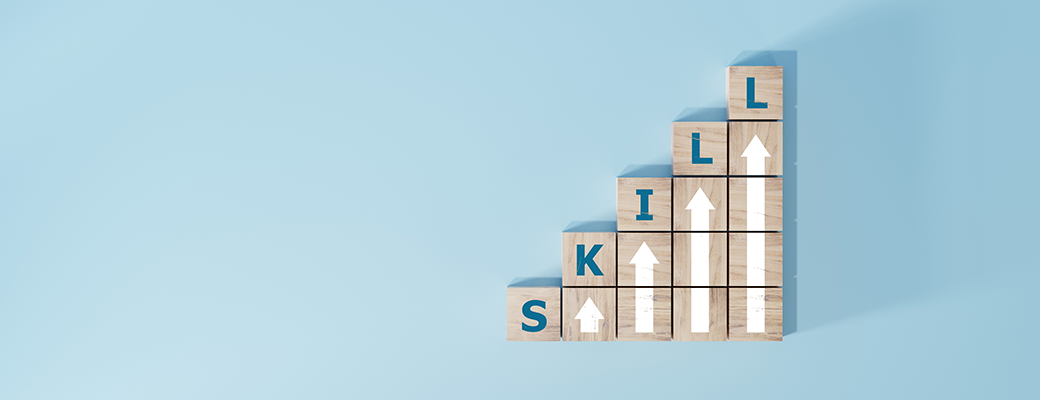
運行管理補助者に必要なスキルは以下の4つです。
ひとつずつ、詳しくご紹介します。
運行管理補助者には運行管理者と同レベルの法令や規則に関する理解が求められます。自ら判断を下せない立場であっても、知識がなければ業務を円滑に行えないからです。
法令と規則に関して求められる知識は事業の種類によって異なります。
以下にまとめましたので従事する事業に応じて必要な知識の習得に努めましょう。
運行管理補助者には運行管理者から指示された運行スケジュールを理解するスキルと、運行管理指示書など所定の資料として作成するスキルが必要です。具体的には法令・規則の理解やパソコンの基本操作能力などが求められます。
また、スケジュール内容を見て業務がより効率化される施策を運行管理者に提案できると運行管理補助者としての評価が上がります。
運行管理者がいつも正しい判断を下せるとは限りません。運行管理者に判断材料を提供し、より良い判断を下せるようサポートする能力があると、自らが運行管理者となる道も見えてくるでしょう。
運行管理補助者にはドライバーとのコミュニケーションスキルが求められます。管理者とドライバーが密に情報交換を行う点呼に立ち会うからです。
点呼で管理者側に求められるのは雰囲気づくりです。
こうした雰囲気をつくってドライバーの健康状態を正確に把握し、必要な措置を講じて事故防止に努めるスキルが運行管理補助者には求められます。
コミュニケーションスキルはすぐに養われるものではありません。
話の聞き方、伝え方など普段からの他人との接し方を意識して行動する必要があります。
運行管理補助者には安全管理とリスクマネジメントのスキルが求められます。
正確な情報を提供し、従業員の安全を確保するための判断を運行管理者が下せるサポートをしなければなりません。
具体的には以下のようなことができると喜ばれます。
自分が運行管理者であると想定してさまざまなことを日頃から考えると、よりスキルが養われます。

運行管理業務には複数の人が関わるのが一般的です。特に点呼は管理者だけでなく点呼作業に不慣れなドライバーも作業に関わるため抜け漏れが出やすく、思わぬトラブルに発展することもあります。
そこで導入をご検討していただきたいのが、テレニシの点呼システム「IT点呼キーパー」です。
IT点呼キーパーは点呼に関する以下のようなお悩みをまるっと解決します。
不安を感じることなくIT点呼キーパーを導入していただくために、無料デモ体験期間を14日から21日へ延長。使用感を無料でしっかり確認してから導入いただけます。
最短2週間で導入可能なIT点呼キーパーは、経営者、運行管理者、ドライバーそれぞれにメリットをもたらす点呼システムです。
さらに、IT点呼キーパーは、国土交通省が実施する「事故防止対策支援推進事業の過労運転防止のための先進的な取り組み」における支援対象機器として、国土交通大臣に累計9回認定された実績を持つシステムです。認定には厳格な条件が設けられていますが、IT点呼キーパーはその全てをクリアし、多くの企業に導入されています。
ぜひこの機会に、導入をご検討ください。

運行管理補助者が担える役割には限りがありますが、運行管理者の負担を減らすには十分な業務を行えます。
また運行管理補助者に必要な知識と実務経験は、近年難易度が上昇傾向にある運行管理者試験合格に向けて大いに役立つはずです。
労働時間の規制による2030年問題に対応するだけでなく、従業員の心身を充実させ笑顔で働ける社内環境をつくるためにも、運行管理補助者の役割を理解し適材適所への配置を検討しましょう。
【出典】
運行管理補助者とは?業務内容や選任の要件・キャリアについて解説|スタンバイplus(参照2025-03-10)
自動車運送事業の運行管理者になるには|国土交通省(参照2025-03-10)
貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について|国土交通省(参照2025-03-10)
旅客自動車運送事業の運行管理に関する基本的考え方|国土交通省(参照2025-03-10)
運行管理者について|国土交通省(参照2025-03-10)
運行管理業務と安全マニュアル|公益社団法人全日本トラック協会(参照2025-03-10)
新規受験概要|公益財団法人運行管理者試験センター(参照2025-03-10)

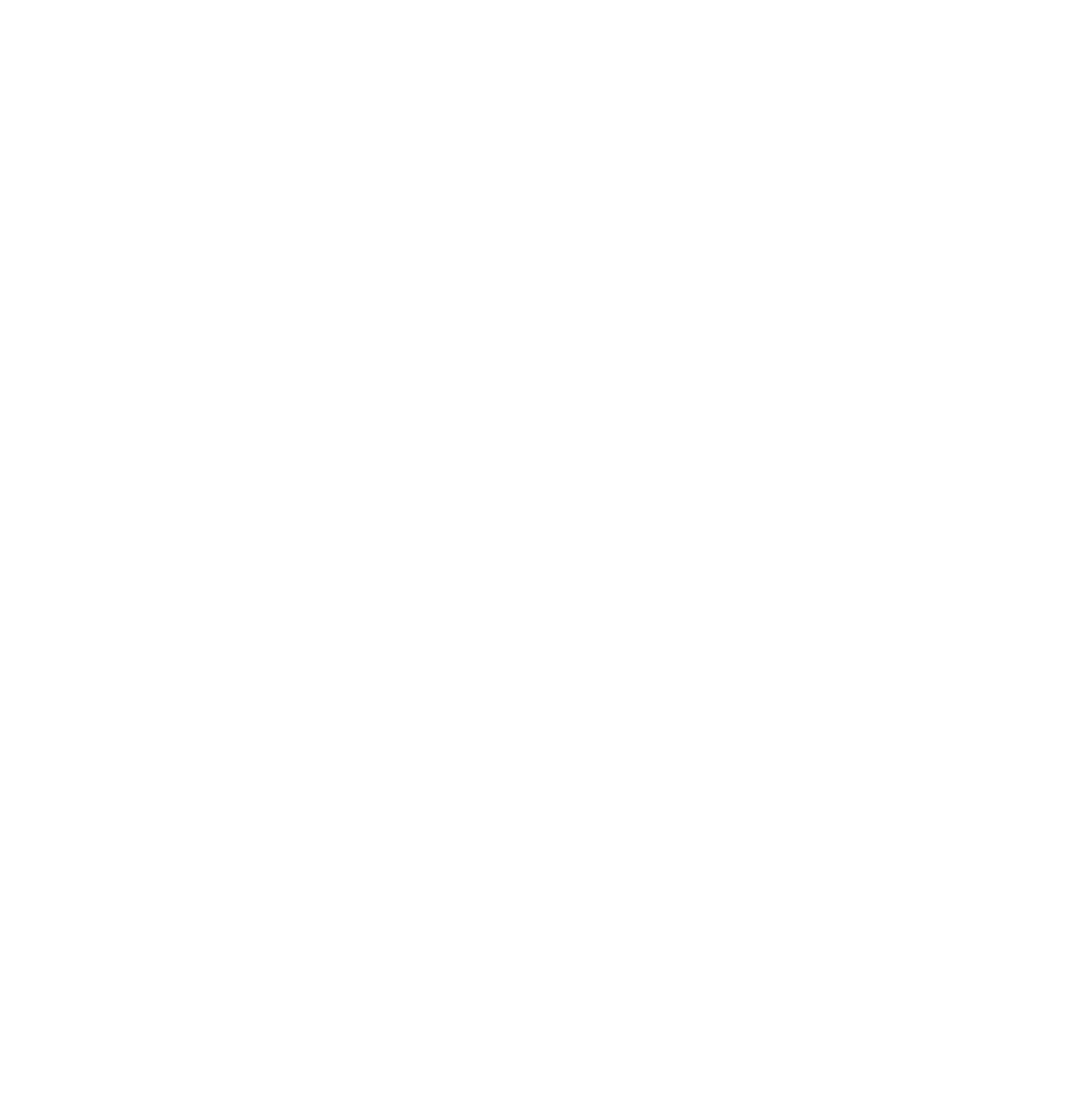 この記事をシェアする
この記事をシェアする
1

最終更新日:
自動車運送業における点呼業務は、貨物自動車運送事業輸送安全規則の第7条で実施が義務付けられています。基本は対面で実施しなければなりませんが、近年はICT技術の高度化によって対面点呼や電話点呼に代わる「遠隔点呼」が実施できるようになりました。法令で義務付けられている一方で、守っていない運送事業者が存在するのも事実です。国土交通省近畿運輸局が令和6年度7月26日に公表した、令和5年度「自動車運送事業者に対する監査と処分結果」の内容分析結果によると、運送事業者の最も多い違反は点呼だと判明しています。そこで今回は、あらためて正しい点呼の方法や点呼に関する違反時の罰則をご紹介します。点呼業務を効率化させるための方法もご紹介しているので、ぜひ最後までご覧ください。
2

最終更新日:
2022年(令和4年)4月より開始した「遠隔点呼」ですが、2023年(令和5年)3月31日以降ちょっとした変化があったことをご存じでしょうか。これに伴い、遠隔点呼の要件や申請方法が変更されました。そこで本記事では遠隔点呼の定義をおさらいし、2023年4月1日以降の申請方法について解説しますのでトラック事業者の方は参考にしてください。
3

最終更新日:
令和4(2022)年4月より、「遠隔点呼実施要領」に基づいた遠隔点呼の申請が開始されています。すでに実施されている「IT点呼」と新たに申請できるようになった「遠隔点呼」には、どのような違いがあるのでしょうか?対面点呼と比べると遠隔点呼とIT点呼は同義に見えることから、どうしても混乱しがちです。本記事では遠隔点呼とIT点呼の違いをまとめましたので、ぜひ参考にしてください。
4

最終更新日:
自社のドライバーだけでなく、他のドライバーや歩行者などの安全確保のために法律で義務付けられている点呼。平成23年5月1日より、運送事業者がドライバーに対して実施することとされている点呼において、ドライバーの酒気帯びの有無を確認する際にアルコール検知器を使用することとなりました。そういった経緯もあり、点呼内容の記録や保管は複雑で、運用に不安を抱えている管理者の方も多いのではないでしょうか。そこで本記事では、事業用自動車(緑ナンバー)運送業者向けに点呼記録簿に関するさまざまな情報をご紹介します。点呼に関する不安がなくなり、管理が楽になるツールもご紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。
5

最終更新日:
新型コロナウイルス感染症の流行後、通販や宅配サービスの利用が急増し、狭い住宅地でも荷物をスムーズに運べる軽貨物運送の需要が高まっています。しかし、軽貨物運送事業を始めるにはさまざまな規定があり、「何から手をつけてよいかわからない」と悩んでいる方も多いのではないでしょうか。そこで今回は、軽貨物運送の基本情報や登録に必要な要件、そして点呼についてわかりやすく解説します。軽貨物車を使った事業を始めたい方はもちろん、すでに事業を営んでいる方もぜひ最後までご覧いただき、顧客の多様なニーズに対応できる事業展開にお役立てください。
お役立ちコンテンツ
サポートメニュー
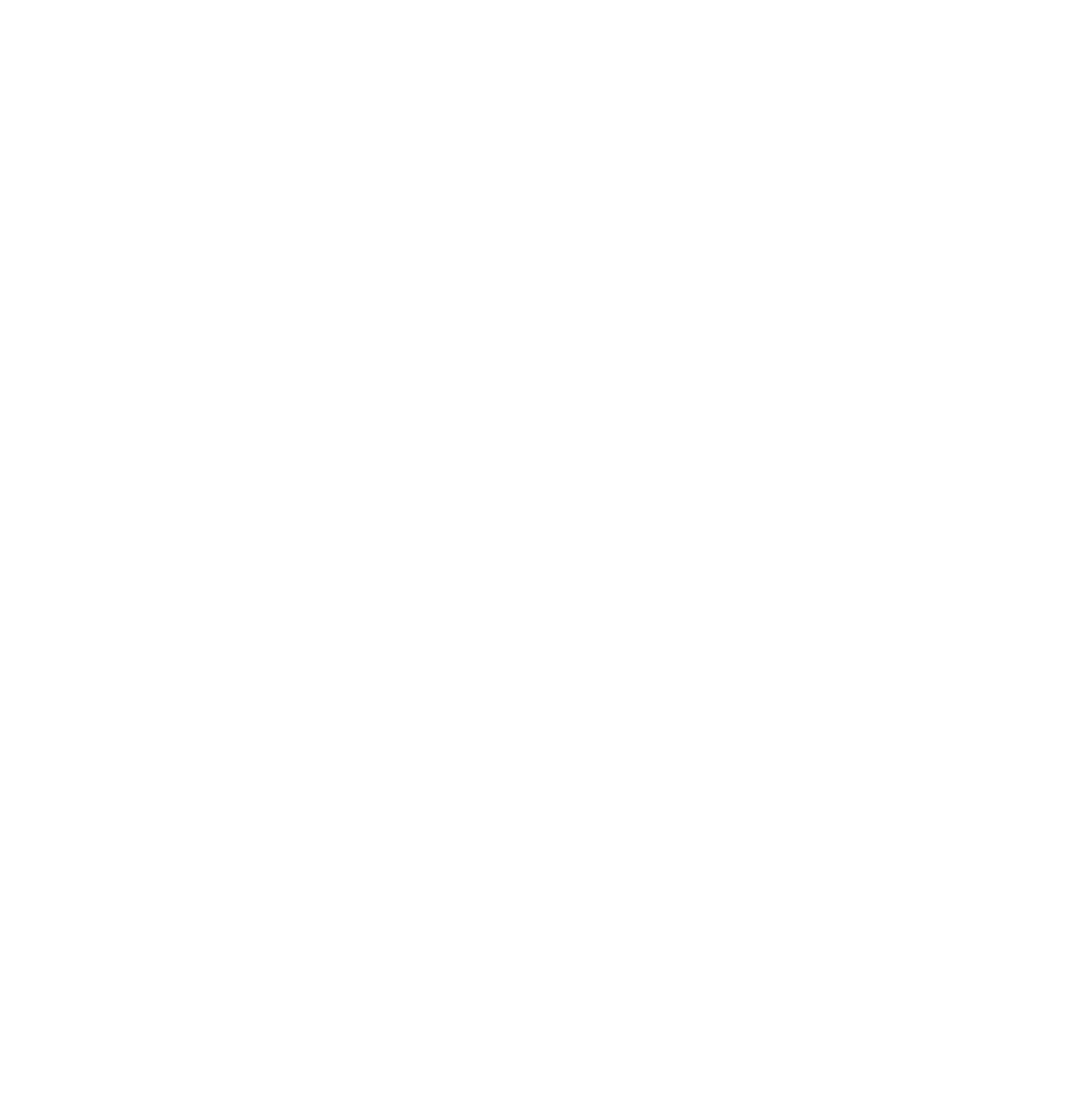 IT点呼キーパーをフォローする
IT点呼キーパーをフォローする