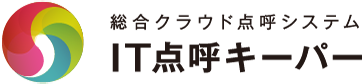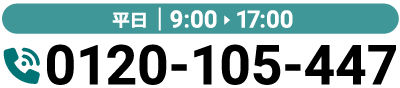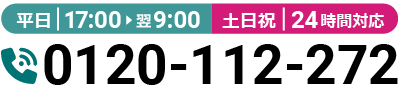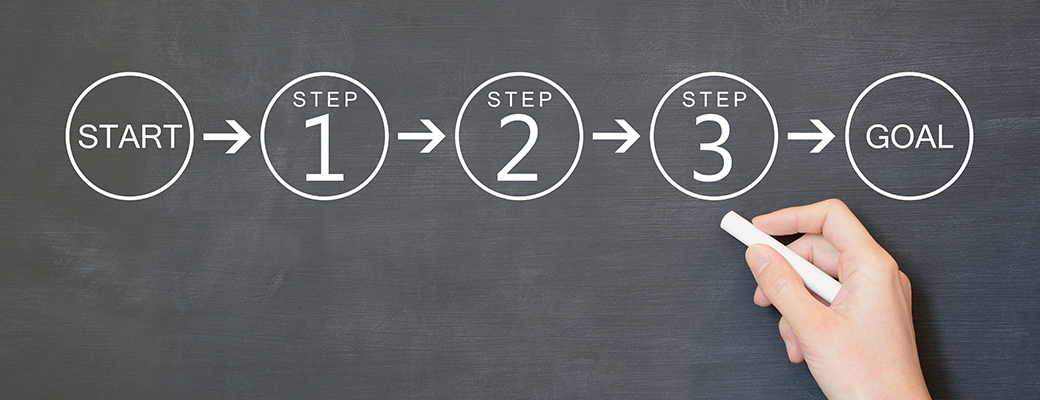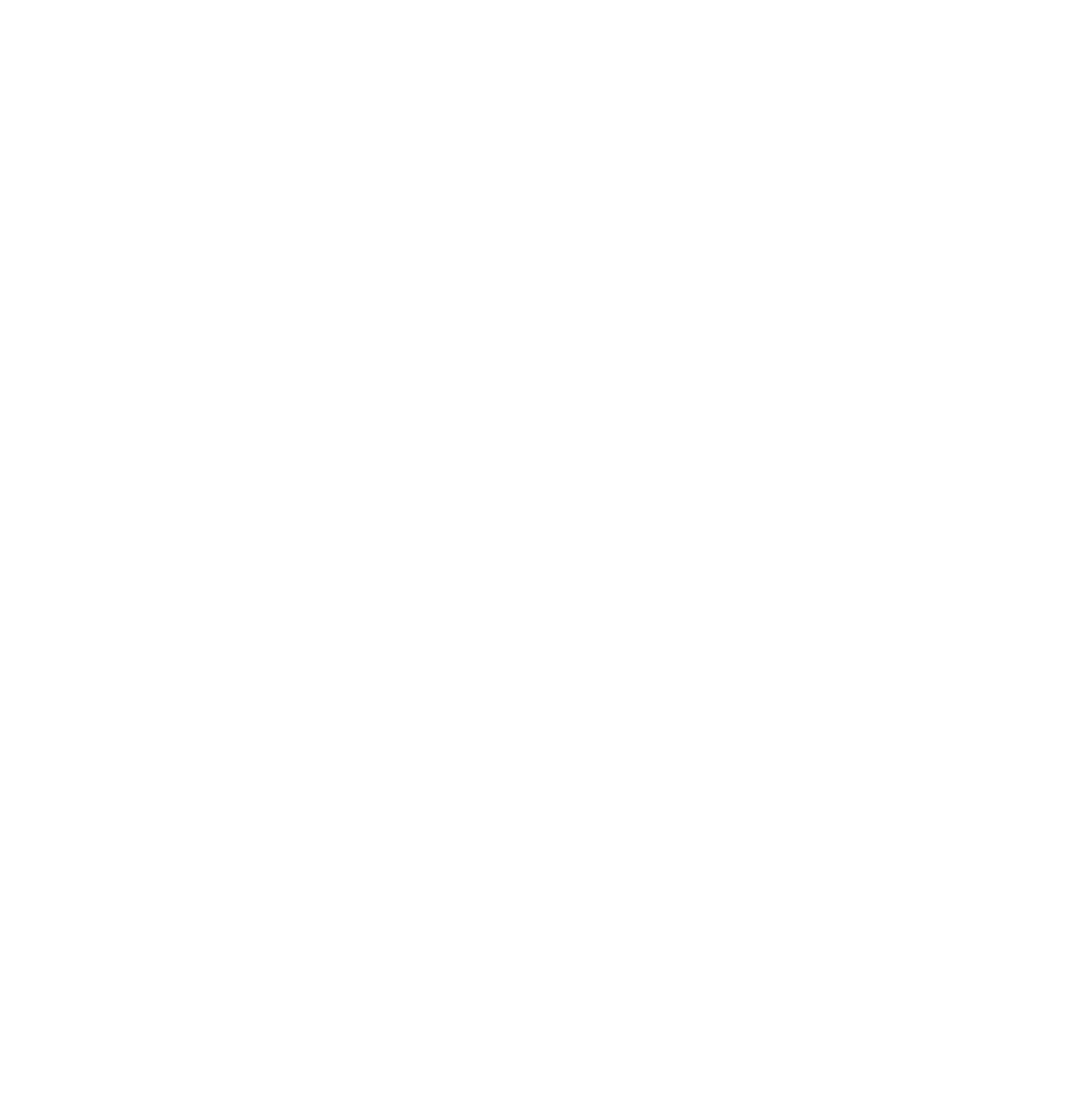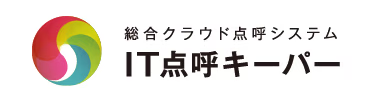その他行政の補助金・助成金も紹介
国土交通省以外の行政からも、幅広い業種に対応した補助金・助成金が提供されています。
いまあらゆる業界で、ITツール導入による業務効率化が推進されています。運送業界においても同様で、運行管理・在庫管理・配送計画など、様々な業務をシステム導入で効率化して、ミスや無駄を減らす事例が増えています。
ここでは特に注目度の高い補助金・助成金をピックアップしてご紹介いたします。運送業の皆さまはぜひチェックしてみてください。
システム導入・システム開発に関する補助金・助成金
IT導入補助金2025
IT導入補助金は、中小企業・小規模事業者等のITツール導入を支援するための補助金です。通常枠・インボイス枠(インボイス対応類型)・インボイス枠(電子取引類額)・セキュリティ対策推進枠・複数社連携IT導入枠の5つの枠から、自身の目的に合致するものに申請できます。
上限金額:
- 1プロセス以上:5万円以上150万円未満
- 4プロセス以上:150万円以上450万円以下
申請受付期間・申請方法
- 4次締切分・5次締切分を受付中です。
- 各申請枠によって、補助率・上限金額が異なります。
詳細は、IT導入補助金2025事務局にご確認ください。
【出典】:IT導入補助金2025|経済産業省(参照2025-08-12)
弊社のIT点呼キーパーは、「通常枠」にて補助金申請が行えます。自社の課題に合ったITツールを導入して、業務効率化を図りたいとお考えの運送事業者さまはぜひチェックしてみてください。
ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助事業(通称:ものづくり補助金)
ものづくり補助金は、新しい技術やサービスの開発・導入を支援する大規模な制度です。
運送業でも、先端技術を使った配送システムや車両管理システムの導入など、大規模な設備投資に活用できます。革新的な新製品・新サービス開発の取組に必要な設備・システム投資等を支援を目的とした「製品・サービス高付加価値化枠」、海外事業の拡大・強化等を目的とした「グローバル枠」の2つの枠から、事業内容に合致するものに申請できます。
各申請枠によって、補助率・上限金額が異なります。詳細は、全国中小企業団体中央会にご確認ください。
【出典】:ものづくり補助金|全国中小企業団体中央会(参照2025-08-12)
労働・雇用に関する補助金・助成金
企業の支出の中でも大きな割合を占める傾向が高い人件費。そのため、雇用に関する助成金の数は非常にたくさんあります。運送業界でも、ドライバー不足・長時間労働の慢性化が問題視されており、労働・雇用に関する課題が大きく、離職率を下げる工夫が求められています。
雇用関係助成金
ここでは、厚生労働省のホームページに掲載されている助成金一覧ページをご紹介いたします。
雇用関係助成金検索ツールを利用して、取扱内容・対象者・キーワードなどから助成金を検索することができます。助成対象の一例としては、再就職支援、中途採用の拡大、高齢者の雇用、障がい者の雇用、労働時間の削減、有休を取りやすい環境作りなどに取り組む企業に助成金が交付されます。
労働環境を改善することで優秀な人材が確保しやすくなり人手不足の解消に効果的です。労働環境の改善で受給できる助成金もありますので、ぜひこの機会にご検討されてみてはいかがでしょうか。
【出典】:事業主の方のための雇用関係助成金|厚生労働省(参照2025-08-12)
新型コロナウイルス対策支援に関する補助金・助成金
事業再構築補助金
ポストコロナの時代の経済社会の変化に対応するために、新市場進出(新分野展開、業態転換)、事業・業種転換、事業再編、国内回帰、地域サプライチェーン維持・強靱化又はこれらの取組を通じた規模の拡大など、思い切った事業再構築に意欲を有する、中小企業等の挑戦を支援する制度です。
成長分野進出枠(通常類型)・成長分野進出枠(GX進出類型)・コロナ回復加速化枠(最低賃金類型)の3つの枠から、自身の目的に合致するものに申請できます。
令和7年度の公募は終了していますが、来年度に向けた参考として掲載しました。
各申請枠によって、補助率・上限金額が異なります。詳細は、事業再構築補助金事務局にご確認ください。
【出典】:事業再構築補助金|経済産業省(参照2025-08-12)
なお、行政の補助金・助成金を電子申請する際には「GビズID」が必要です。
GビズIDとは、法人・個人事業主が行政手続きを行う際に必要となる共通IDシステムです。今後、多くの補助金・助成金が電子申請に対応予定ですので、まだGビズIDをお持ちでない事業者さまは、この機会に検討してみてはいかがでしょうか。GビズIDの発行は無料です。
【出典】:GビズID|デジタル庁(参照2025-08-12)